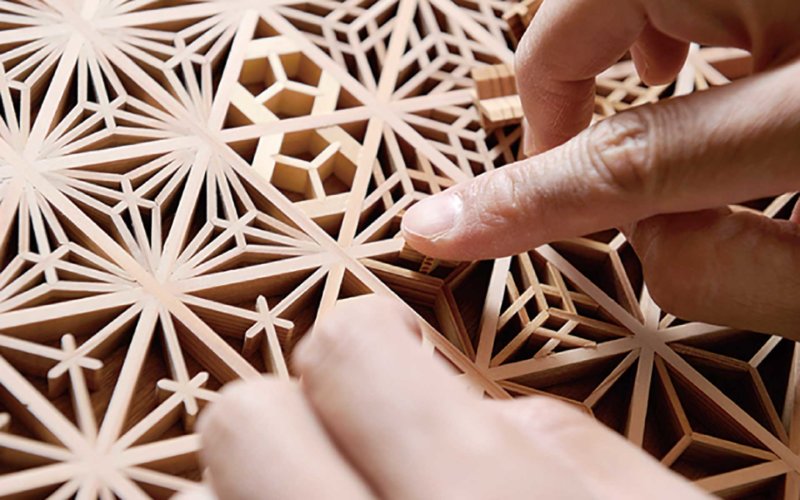仙巌園・尚古集成館
エリア

仙巌園 (せんがんえん) は、江戸時代初期の1658 (万治元) 年に19代島津光久の別邸として造られた。その敷地は50,000平方メートルにも及び、桜島を築山 (つきやま) に、別名・錦江湾 (きんこうわん) とも呼ばれる鹿児島湾を池に見立てたスケールの大きな大名庭園となっている。南の玄関口といわれた薩摩の国だけに、園内には中国文化の影響も色濃く残り、その気候から南国らしい珍しい植物の姿も見られる。
風光明媚な名勝地としてだけでなく、歴史遺産としての価値も高い。幕末から近代にかけては、28代島津斉彬によって富国強兵と殖産興業が推し進められ、園内やその周辺には製鉄やガラス、陶器のほか、造船や大砲などの工場が集まった。これらの事業は「集成館事業」と呼ばれ、近代日本における産業革命の先駆けとなった。2015年7月には、集成館事業の史跡や建物が「明治日本の産業革命遺産」として世界文化遺産に登録されている。
仙厳園のすぐ隣にある尚古集成館の建物もその一つ。日本最古の石造洋式機械工場で、現在では島津家の歴史や薩摩の文化を紹介する博物館となっている。
薩摩の雄大な景色と、近代日本の胎動を同時に感じられる場所だ。