まさに「工芸のエントランス」京都のものづくりを身近に感じるカフェ
エリア

京都駅と中心地の間に位置する、七条河原町。ここに、京都の工芸品と気負いなく出会えるカフェがあります。
カフェの名前は、Kaikado Café。日本で最も歴史ある茶筒の老舗、明治8年創業の開化堂が運営しています。



工芸をもっと身近に
カフェを立ち上げたのは開化堂6代目の八木隆裕さん。かねてから「若い人が伝統の技や道具に触れる機会や場所を作りたい」という思いがあったのだそう。そこにコーヒー界のカリスマである中川ワニさんと京都の職人でコーヒー道具を作ろうという取り組みや、先代が喫茶店をやりたいと話していたことなどが重なり、2016年にカフェオープンという形で思いが現実のものに。
店内では、八木さんも所属する京都の工芸の若き後継者たちのプロジェクトユニット「GO ON (ゴオン) 」のメンバーが作ったものが多数使われています。遠い存在に感じてしまいそうな老舗の工芸品を、身近なものとして使えるのは嬉しいですね。



インテリアは、「GO ON」と親交のあるデンマークのデザインオフィスOeOが手がけました。
コンクリートの壁や鉄の窓枠など元のままの意匠と、開化堂で製作したランプシェードや茶筒と同じ銅板を用いたカウンターの前板、無垢のテーブルやベンチといった新しいデザインが見事に融合。高い天井と大きな窓が光を取り込む心地よい空間となっています。




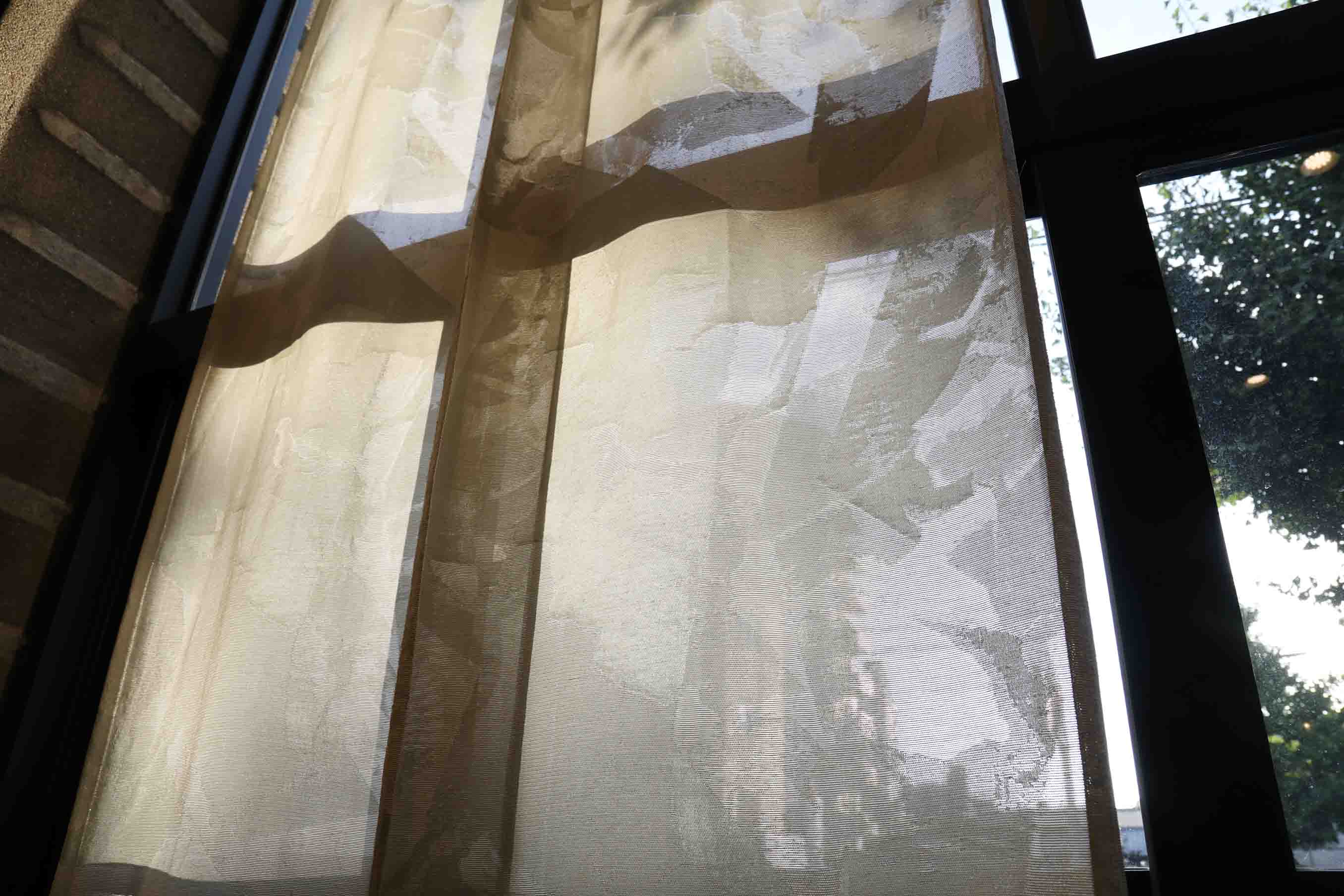
せっかくなので、工芸の技術が生かされた器や道具を詳しく見せていただきました。
使い心地を考え抜く

カップ&ソーサーを手がけたのは400年の歴史をもつ宇治の「朝日焼」。千利休が茶の湯を大成した時代に活躍した茶人、小堀遠州から「朝日」の字を与えられた由緒ある窯元です。
朝日焼の茶盌 (ちゃわん) の特徴は美しい真円にあるといいます。しかしこのカップの飲み口は横に広がる楕円形。

茶盌より径の小さいコーヒーカップやティーカップの口あたりの良さを追求した結果、この形が生まれました。熱い飲み物が入っていても持ちやすいように取っ手も工夫されたデザインになっています。

「作り手だけでなく使い手の視点をしっかりと取り入れるものづくりを進めました。使い手を考えた中川ワニさんの視点から、『楕円にする』というアイデアが生まれました。
美しい真円を歪めるなんてもったいない気もしますけれど、それで飲みやすくなるなら、と朝日焼さんが引き受けてくださったんです。真円とはまた異なる美しさのあるものができあがりました」と、店長の川口清高さんが制作秘話を教えてくださいました。
世にある道具より良いものを
京金網でできたコーヒードリッパーも道具としての機能が追求されています。

「コーヒードリッパーは、表面の凹凸でペーパーとの密着性をコントロールしたり、穴の径でコーヒーの落ちる速度を変えたりしています。金網の編み方や大きさでコーヒーの味が大きく変わります。中川ワニさんに実際に使っていただきながら、辻さんに何度も試作していただきました。
編み方を上と下で変えることで、水の落ちるスピードが変わるようになっています。また、網の周りを包んだ方が味や香りがよくなるということがわかったので、辻さんの提案で銅製カバーをつけることになりました。
工芸の技術を使いながら、既存のものに形を似せるのはそれほど難しいことではないようです。でもそれだけでは不十分ですよね。機能が同じかそれ以上でなければ、単に形を真似ただけになってしまいます。道具としての本質的な価値を考えるようにしています」

「いま世にあるものより良い道具を」と考え抜かれたものづくり。工芸を受け継ぐ職人さんたちの矜持を感じました。
5年がかりでやっとできあがったこのコーヒードリッパーは、今や金網つじの人気商品となっているのだそう。
なお、家庭用サイズは完成し、カフェで販売もしていますが、業務用サイズの開発はカフェオープンから2年経った今も続いているのだとか。
使う動きから逆算してできた、「完璧すぎる」道具
道具としての機能を追求する職人さんのものづくり。中川ワニさんが驚いたこともあったのだそう。
「中川さん用のコーヒーポットを作ったことがありました。参考となるものが中川さんから届いたのですが、それだけでは作り方が定まらなかったんです。それで、実際に中川さんがコーヒーを淹れる姿を職人さんに見てもらいました。
ポットを使うときに指をかける場所や注ぐ角度を観察した後に出来上がったポットは、『ブレがなくて完璧すぎる』と中川さんを驚かせていました」

コーヒーの淹れ方も日々修行
Kaikado Caféが淹れるコーヒーは、中川ワニさん直伝。カフェスタッフのみなさんは職人さんのように日々淹れ方の修行を積んでいるのだとか。
「ここでの淹れ方は、お湯の温度や時間を測ることをしません。日によって気温も湿度も違いますし、豆も日々変化しています。コーヒーの表面に現れる泡の状態を観察しながら、豆の様子を察知して淹れます。
コーヒーにお湯を注ぐといろんな表情を見せます。泡を見て注ぐ量を考えて、豆にお湯をなじませながらドリップしていく。味を重ねていくようなイメージです。一本調子に入れると単調な味になってしまいます。
コーヒーと向き合うというか感覚的なこともありますが、口に入れるものも開化堂らしく、職人のように体に染み込ませた技術で提供していけたらと思います。美味しいと喜んでいただきたいですからね」
店内で扱われている器や道具だけでなくカフェで働く方からも、ものづくりを大切にしてきた開化堂の精神を垣間見ることができました。
そんなKaikado Café。メニューも開化堂ならではのものが並びます。
コーヒーと紅茶はここでしか飲めないオリジナル。「中川ワニ珈琲」、ロンドンの「ポストカード ティーズ」によるもの。ほかにも、「EN TEA」の四季折々のお茶、「丸久小山園」の抹茶ラテや「利招園茶舗」の玉露の雁金、城崎の地ビール、那須高原の人気店「チーズガーデン」のチーズケーキ、人気の「あんバタ」など、味わってみたいものばかりで目移りしてしまいます。

工芸の技術が使われた器や道具に触れながら、ゆっくりとお茶の時間をたのしめる場所。新しい出会いを期待して、京都を訪れるたびに通いたいお店でした。
<取材協力>
Kaikado Café
京都府京都市下京区住吉町 (河原町通) 352 河原町通七条上ル
075-353-5668
http://www.kaikado-cafe.jp/
文:小俣荘子
写真:山下桂子 (外観写真:Kunihiro Fukumori)








