グッバイ、志賀直哉
エリア

こんにちは、BACHの幅允孝です。
さんち編集長の中川淳さんと旅をし、そこでの発見や紐づく本を紹介する「気ままな旅、本」のコーナー。
第1回目は中川さんのお膝元、奈良県編をお送りします。ほとんど食レポになっておりますが、ご愛嬌。
奈良の「うまいもん」を探す旅をおたのしみください。
奈良にうまいものはない。小説家の志賀直哉が随筆『奈良』の中でぽつりつぶやいた一言が、現代まで奈良県民を苦しめることになろうとは、彼自身も想像していなかったに違いない。
そもそも『奈良』とは、1938年に奈良県が発行した冊子「観光の大和」創刊号に志賀が書いた僅か4ページほどの短い文章。一読すると、たしかに「食ひものはうまひ物のない所だ」という記述がある。ふうむ、原稿を受け取った県の職員もなぜ訂正をお願いしなかったのか。しかし、よく読んでみると奈良のわらび粉や豆腐、がんもどきを褒めている。牛肉もいいと書いている。そう、このエッセイは奈良を離れる直前の志賀直哉が奈良愛を綴ったものなのだ。つまり、志賀が書いたとされる「奈良にうまいものなし」は、前後の文脈から外れ、残念な一人歩きをしてしまっているわけだ。
というわけで、今回の旅のテーマは志賀直哉の言説におさらばしたくなるような奈良県のおいしいものを紹介することに急遽決定。まず訪れたお店は「清澄の里 粟」である。
市内から15分ほど車で走り高樋町に。大和盆地を見渡せる小高い丘の上にあるレストランへ到着した。少し息を切らして坂を登るとお出迎えしてくれたのは、ヤギのペーター。彼は放牧中というか、店の周辺をうろうろし、草などをもぐもぐしておる。僕はかなりびっくりしたのだが、やはり奈良の人は鹿で慣れているからか、動物がその辺りをのそのそ歩いていても驚かない。ちなみにペーターは人が食事を始めると、物いいたげな顔で店内を覗き込んでくる茶目っ気たっぷりの牡ヤギ。そして、彼らの暮らすこの場所が、大和伝統野菜とエアルーム野菜が食べられるレストラン「清澄の里 粟」だ。

少しだけ説明すると、大和伝統野菜とは戦前から奈良県内で栽培をしている野菜で「味・香り・形態・来歴」に特徴があるもの。一方、エアルーム野菜とは、世界中の様々な地域・民族間で受け継がれてきた伝統野菜で「家宝種」などと訳される。ここ「清澄の里 粟」は、そんな貴重な野菜を地元農家と連携しながら栽培し、調理、提供するお店。そして、オーナーの三浦さんが大事にする「不易流行」の言葉通り、変えてはいけないものを大切にしながら、未来の伝統野菜を考える場でもある。
靴を脱ぎ、机がいくつも並ぶ店内にあがると、卓上には見たこともない野菜がごろごろ。その中でも最もインパクトのあった隕石のような野菜について聞いてみると、何でも「宇宙芋」と呼ぶのだとか。実のところ、これは巨大なむかごで、15センチほどにもなって蔓にできるのだという。他にも、ズッキーニの一種である「ジャンヌ・エ・ベルテ」や、「はやとうり」、瓢箪のような「バターナッツ」という甘みのあるカボチャや「スター・オブ・デイビッド」というオクラなど、普段なかなかお目にかかれない古来から伝わる野菜を、少しずつ60種類も食べられるのである。


前菜から始まり、小さな鍋、季節食材の煮物、てんぷらなどなど、ゆっくりじっくりと味わう野菜料理は、まさに土地の滋養。味付けも尻あがりというか、噛めば噛む程じわじわと旨味がにじみ出る。また、個々の野菜がそれぞれ持つ細やかな違いにも敏感になれるのもこのお店の特徴。例えば、「ジャガイモ」と僕らは大まかに呼ぶけれど、ここで食した「ノーザンルビー」と「野川芋」は同じジャガイモながら全く異なる味わい。小さな単位で野菜について考えるきっかけになる。
「むこだまし」というこの地の特有の粟を使った和菓子「粟生」まで、たっぷり3時間の昼食。気持ちよくゆったりしていたら、いつの間にか午後も深くなってしまった。大和伝統野菜を中心とした土地の滋養と、ゆるやかに流れる時間と、ペーターとの触れ合いが愉快な「清澄の里 粟」は、時空がすこし歪んでいる心地よい場所だった。奈良の自然を愛した志賀直哉に彼らの活動は響くと思うのだが、いかがだろうか。

さて、次に訪ねた一軒は、蕎麦の名店として奈良で名高い「玄」。日本酒「春鹿」で知られる今西清兵衛商店所有の書院の一角にある木造平屋建築に店を構えている。夜は「蕎麦遊膳」という懐石のみだが、ここの蕎麦を志賀が食べていたら、『奈良』の原稿も少し違った表現になっていたかもしれないと思えた。
食事は蕎麦豆腐から始まり、水蕎麦、田舎蕎麦、焼き物、ご飯、水菓子などが続く。なかでも僕が驚いたのが、ふわふわの蕎麦がきである。ほのかに温かい「玄」の蕎麦がきは、まるで赤ん坊のような柔らかさ、ぬくもり。まさに生まれたての蕎麦がきである。まずは何もつけずに一口。素朴な味わいの奥に蕎麦という植物の甘みがじんわり浮かび上がってくる。二口目は塩をはらはらと振っていただくと、円みのある甘さが際立ち、三口目に醤油とワサビで食せば、今度は蕎麦の香りが引き立つ。
そもそも蕎麦を食べるのに、麺状にするようになったのが600年ほど昔。それ以前は、殻を外して手で挽いて、つなぎなしでかき混ぜて作る蕎麦がきか、米の代用品としての蕎麦雑炊が、蕎麦の主な食べ方だったとか。「玄」の蕎麦がきは、ちゃんと手間暇をかけているのに、昔から連綿と続く原初的な味がする。蕎麦とはこういうものなのだと感じさせる清らかな体験である。

ちなみに、その次に登場した水蕎麦も驚くほど素の蕎麦。余計なものを削ぎ落とし、裸になった十割蕎麦である。玄蕎麦を石臼で挽き、ひとり分ずつ茹で締めて出される。茹で上がりから口に入れるまでの時間がとても重要らしく、仲居さんが早歩きで蕎麦を運んでくるのもこだわりの一部。あのきびきびした給仕は見ていて気持がよい。その水蕎麦、まずは何もつけずにそのまま口に入れると、ふむむ、透明な味がする。続いて(名前の通り)軟水が入る蕎麦猪口に浸して蕎麦をすすると、今度は蕎麦の甘さとさらさらした喉越しがよくわかる。その後、塩や梅肉でいただくのだが、時間や食べ合わせと共にくるくると味が変容する。感動は言葉を超えているが、頭のなかで音楽が鳴り出すような蕎麦である。この晩は、蕎麦に合わせ日本酒とのマッチングも提案してもらったのだが、春鹿の純米超辛口のような旨くてキレのある辛口の酒も蕎麦のソースのように愉しめた。そして、その後も続く蕎麦と日本酒のめくるめく邂逅にふらふら、くらくらしたのは言うまでもない。奈良の夜では素晴らしい酩酊が味わえると志賀先生の墓前に報告したくなってきたぞ…。

ほろ酔いの奈良の宵を締めるのは、この人しかいないだろう。奈良ホテルのヘッドバーテンダーを務める宮崎剛志さん。僕は以前、対談のお仕事でもご一緒している。彼は奈良ホテルにバーテンダーとして就職したものの、なぜか案内係、ソムリエ、総務企画の担当に。けれど、バーテンダーの夢を捨てきれず独学で修行を続け(家にバーカウンターをつくり「ラボ」と呼んでいたそうです)、2013年に開かれたバーテンダーの世界大会で入賞。その技と努力が認められ奈良ホテルのメインバーに返り咲いた人である。
久しぶりにお会いした彼は、相変わらずのカクテル狂。様々な実験を繰り返しながら、新しい味わいについて考案しているのだという。「以前に比べてオーソドックスなカクテルを大切にしています」といい、実際に一杯目でいただいたマティーニは威風堂々といった風情。甘み、酸味、苦味、渋味といった味の構成要素を想像しながら理詰めでカクテルをつくるという宮崎さんらしいニュースタンダードである。
一方、バーカウンターには数々のスピリッツに混ざってなぜか「九重桜の本みりん」が置いてある。突っ込まないわけにいかないので尋ねると、最近は日本酒を用いたカクテルをいくつか考えているのだとか。本みりんはメキシコのプレミアムテキーラ「Don Julio」のレポサドと合わせたり、奈良県橿原市にある河合酒造「出世男」の蔵出しにごり酒とオランダで造られる小麦100%のウォッカ「Ketel One」を組み合わせてみたりと、宮崎さんの探求はとどまるところを知らない。日本酒を味の中心に据えすぎると外国人など日本酒を飲みなれていない人には難しいカクテルになってしまうが、メインのお酒を後ろから支え、ほのかに米の旨みが下から浮かんでくるような宮崎風日本酒カクテルは実に面白い発想。縁の下の力持ち的な存在が、世界のカクテル界で戦う日本酒には似つかわしいのかもしれない。まあ、そんなこんなで飲み食いばかりの奈良旅の初日は幕を閉じるのだった。


翌日、二日酔いもなく元気に僕が訪れたのは奈良市高畑にある志賀直哉旧居。430坪の大きな敷地に建つ実に優雅な邸宅である。小説家は当時そんなに儲かる仕事だったのか? と素朴な疑問を持ちつつ眺めるそれは、隅々まで志賀直哉の美意識が行き届いた贅沢な家。ここは1929年に志賀直哉自身が設計し、13年間住み続けた場所だ。じつのところ、志賀はとにかくひと所に居続けられない性分で、人生で28回も引越しをしたといわれている。そんな彼が13年間も住み続け、3人だった子供が6人にもなった奈良を愛していなかったはずがないではないか。
入館して最初にあがる2階の客間から見える庭は見事。窓際の畳に座り、外から吹く風を感じると自然に歌でも詠みたくなる。(やったことはないけれど。)「こりゃ、いいものが書けそうだ」と文才をうっちゃり環境を羨むが、実際に志賀はこの旧居で代表作の『暗夜行路』を脱稿したらしい。
そんな中、この志賀の旧家でもっとも印象に残ったのが、食堂(ダイニングルーム)と台所だった。実は家の中で最も大きな部屋が家族みなで食事をとるダイニングルーム。しかも、部屋の角には革張りの大きなソファーがしつらえられており、志賀直哉がこの食堂を自由な団欒の場所として設計していたことがよくわかる。『衣食住』という本で、志賀は食について「毎日三度、一生の事だから、少しでもうまくして、自分だけでなく、家中の者までが喜ぶようにしてやるのが本統だと思う」と書いている。また食堂のすぐ隣には和風のサンルーム(瓦敷のヴェランダと呼ばれていた)と台所につながり、この一帯が家内サロンとして賑わっていたという記録も残っている。


もうひとつこの志賀直哉旧居で忘れてはいけないのが台所だ。1930年前後では画期的なことにガス、水道、電気、氷冷式冷蔵庫といった当時の最新設備が揃い、食堂と直につながっていた。しかも、引き出しは台所、食堂の双方から引くことができる機能的なものだったようだ。ダイニングキッチンが第二次世界大戦後に普及したことを考えると、志賀直哉の合理的でモダンな考え方はずいぶん早かった。しかも、住み込みの女中たちがきっと必死で調理を日々していたのだろう。なにせ、先述の『衣食住』で志賀はこんな言葉も残している。「私が一番不愉快に思うのは一寸気をつければうまくなる材料を不親切と骨惜みから不味いものにして出される時である」。なかなかのプレッシャーのかけ方ではないか。

僕は志賀直哉の旧居を訪れ、この食堂や台所をみて、彼がずいぶん長い時間をここで過ごしていたのだろうなと想起した。妻や6人の子供との時間。「高畑サロン」という名が残っているように白樺派の文人や、異分野の文化人もずいぶんこの家に押しかけ、志賀を囲んだに違いない。そうすると、そもそも志賀は家以外の場所で奈良のご飯を食べることが少なかったのかもしれない。だからこその、あの言葉である。「食ひものはうまひ物のない所だ」。
女中たちの料理に厳しかった側面も垣間見えるが、それでも志賀直哉は奈良の自分のおうちが大好きだった。ゆえに、今回の旅で僕が経験したような、奈良に息づく食を探す必要もなかったのかもしれない。もし、もっと積極的に志賀が外食をしていたら、きっと彼はこう言ったはずだ。「奈良にはうまいものしかない」。そう確信するほど、おいしい奈良を満喫した竜宮城コースの旅だった。
《今回の本たち》
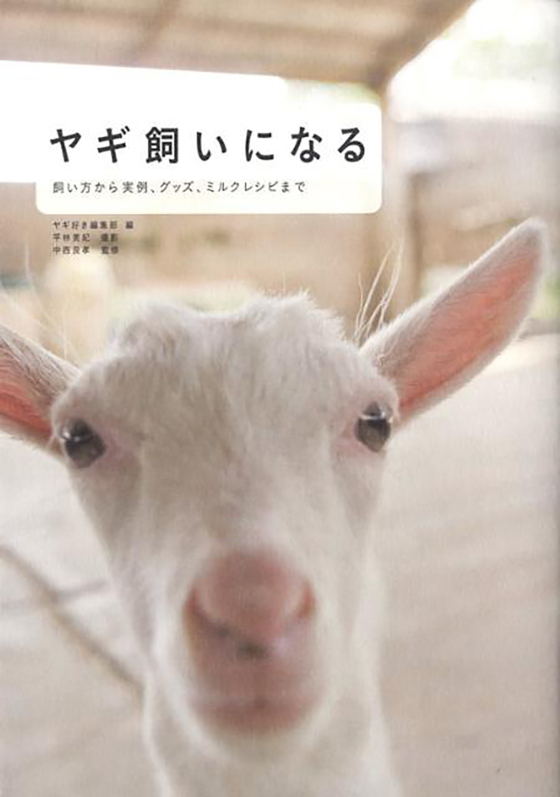
『ヤギ飼いになる』
美味しいミルクを提供する家畜であり、ペットとしての愛くるしさも併せ持つ、ヤギ。そんな彼らの魅力や飼育方法を、ヤギ飼いの先輩たちの声も拾いながらじっくりと紹介していきます。

『家族野菜を未来につなぐ』
「清澄の里 粟」のオーナーである三浦夫妻が記した1冊。大和伝統野菜のエッセンスである「家族野菜」という考え方について、レストランオープンまでの道のりと一緒に丁寧に語ってくれます。

『大和の野菜 いろはカルタ』
44枚の絵札に大和の伝統野菜をあしらった、思わずお腹が鳴ってしまいそうなカルタ。制作のきっかけは、三浦さんの取り組む家族野菜でした。読み札には、調理方法もしっかり書いてあるので安心です。

『蕎麦の事典』
簡潔なタイトルの通り、1155項目に渡る蕎麦の用語を50音順に網羅した、まさに蕎麦の読む事典。原材料から行事、蕎麦にまつわる諺まで、蕎麦への愛が十二分に詰まった1冊です。

『そばと私』
1960年の創刊以来、「蕎麦の文化誌」として親しまれてきた季刊『新そば』。そこに寄せられた蕎麦好き67人の声をまとめたアンソロジー集には、独特の熱気が詰まっています。
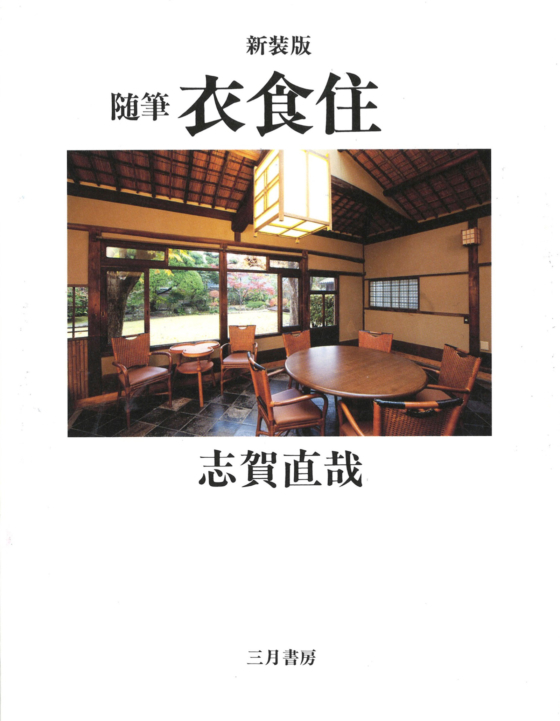
『衣食住』
志賀直哉の作品から随筆28篇、短篇5篇を選び再構成した1冊。作家らしい日常生活への鋭い観察眼とともに、合間に挟まれる「城の崎にて」などの小説が小気味良いリズムを生み出しています。
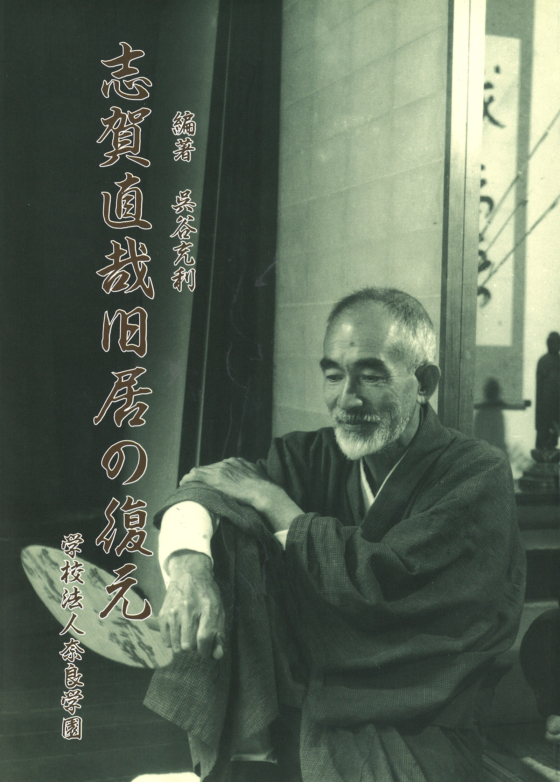
2008年、志賀直哉が建築した当初の姿に修復された、彼の旧邸。その過程をまとめたこの本は、志賀直哉旧居でのみ販売されています。志賀の暮らしぶりを堪能した後は、本書もぜひ。
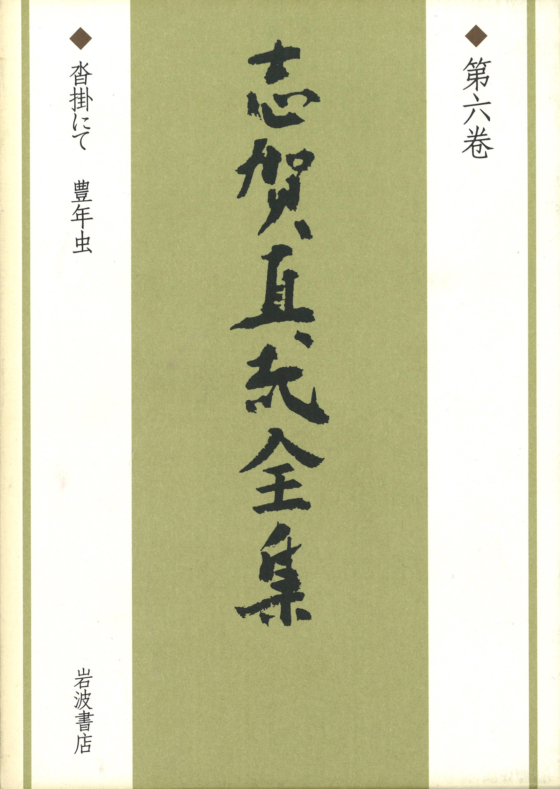
「東京人の方が好きだ」「奈良の欠点は税金の高い事」などの手厳しい言葉が続きますが、最後には「兎に角、奈良は美しい所だ」と締めくくる。忌憚のない物言いは、長く奈良を愛した彼だからこそのものですね。
幅允孝 はばよしたか
ブックディレクター。未知なる本を手にする機会をつくるため、本屋と異業種を結びつける売場やライブラリーの制作をしている。最近の仕事として「ワコールスタディホール京都」「ISETAN The Japan Store Kuala Lumpur」書籍フロアなど。著書に『本なんて読まなくたっていいのだけれど、』(晶文社)『幅書店の88冊』(マガジンハウス)、『つかう本』(ポプラ社)。
www.bach-inc.com
文:幅允孝








