「和紙屋のどら息子がおかしなことやっとる、くらいが丁度いい」 ── 伝統を受け継ぐ、若き和紙職人のサブカルチャーな目論み
エリア

はじめてそれを見たのはもう2年以上前になるだろうか。
和紙である。でも、ただの和紙ではなく、そこには何かが混ざっていた。よく見ると印刷された文字や写真のようなものが‥‥。


これは、いったい何なのか。もちろん和紙である。和紙ではあるけれど、その1枚には何か意味があるような、新しい可能性を示唆しているような‥‥そして単純に思った。和紙ってこういうこともできるんだ、面白いなあ‥‥それが最初の印象だった。
和紙とは何なのか?
「あれは和紙の原料に、雑誌や紙箱を細かくして混ぜ込んで、すいたものなんです」

そう話すのはつくり手である谷口弦さんだ。佐賀市大和町の名尾地区にある「名尾手すき和紙」の7代目。300年以上の歴史を誇る名尾和紙の伝統を、現代に受け継ぐ若き和紙職人である。
同地区にはかつて100軒ほどの工房が並んでいたが、今では1軒のみに。
※詳しくは「名尾の山里でたった1軒の和紙工房が“残しておきた紙づくり”」をご覧下さい

そんな工房の後を継いだのがおよそ7年前。大学卒業後、アパレルショップの店員として働いたこともある。が、結局のところ「自分にしかできないことをやりたい」と家業の紙すきを選んだ。もちろんゼロからのスタートだ。
紙の原料となる“梶(かじ)の木”を栽培。一般的に使われるのは楮(コウゾ)や三椏(みつまた)などだが、梶の木は楮の原種。これを使うことが名尾和紙の特長の一つだ。

刈り取った梶の木は蒸して皮を剝き、乾燥させる。再び煮て、水にさらし、打解して柔らかな繊維にする、といった途方もない手間暇をかけて、ようやく紙すきを行うことができる。そして、そこからは来る日も来る日も紙をすく、

すく、

すく。

そうした日々を繰り返し続けた谷口さんの頭のなかに、あるとき、一つの疑問が生まれた。
── 和紙っていったい何なのか?
「和紙の定義みたいなやつですね。これをしなければならないといった決まりごとがあるのかなって。偉い和紙職人の先生に聞いてみたことがあるんです。『和紙の定義って何なんですか?』って。そうしたら、何て言ったと思います? 」

「『俺にも分からん』だって(笑)。そうか、こんなにすごい人でも分からない曖昧なことなんだ、と思って自分なりに調べてみたんです」
分かったことといえば“和紙”という名前だけど、流通しているものは国内でつくられているものばかりではないこと。手すきもあれば、機械すきもあること。
和紙の歴史は1400年以上あるといわれるけど、そもそも“和紙”という言葉が登場したのはたった150年前の明治期であること。欧米からもたらされた“洋紙”と差別化するために、“和紙”という名前をつけたのだということ‥‥。
そうしたことの一つひとつが面白かった。紙にまつわる書物や図録を読み漁り、学べば学ぶほどに奥深さを感じた。そして“紙”というものにのめり込んでいった。
紙の再生=魂を宿す紙づくり
そのなかで谷口さんのアンテナに引っかかったのが“還魂紙(かんこんし)”だった。
「還魂紙は使い古しの紙を集めてつくる再生紙のことですけど、中国から伝えられたとき、日本人はそれを文字通り“魂が還る紙”ととらえた。日本人の宗教観にマッチしたというか、当時の誰かがものすごく勘違いをしたというか(笑)。
それでも日本における還魂紙は独自の文化として、完全なるカウンターカルチャーとして発展した歴史があるんです」
たとえば、鎌倉時代には紙をすくときに遺灰をすきこんだ。その紙に写経をして故人を弔う風習があったとか。
また古紙回収・再生が当たり前のように行われていた江戸時代。大切な人からもらった手紙や帳面をすき込んでは、ここぞという大事な場面で使っていたという。
「還魂紙の別名を“宿紙(しゅくし)”ともいうんですが、確かに何かを混ぜることで紙の中にその何かが宿るな、と。そうした考え方が面白くて、ものすごく好きで。
手ですく→再生する→魂を還す→俺、できる!みたいに思ったんですよね(笑)」
何かを混ぜて再生させる ──。
白くてきれいな和紙もいいけれど、思いや願い、希望、そのものに込められた物語といったものを一緒にすいて紙にする。そこに現代の和紙としての価値を見出した。
紛れ込んだ「闘」の一文字
「和紙職人としてはまだまだ30%くらい」と谷口さんは言うけれど、それでも紙すきの技術や背景を、体で覚え、頭で考え、心で感じながら作業をしてきた。
これから先、自分にできることは。自分にしかできないことは何だろうかと模索していた、そんなとき。

「紙をすいていたらゴミが入ったことがあって。ピンセットで取り除くんですけど、そのときのゴミというのが新聞紙の1文字で『闘』だったんです。うわ!これって、今の俺に対する言葉なんじゃないかって(笑)。
紙に浮かんだ文字からそうしたメッセージを感じたんです。でね、もしかして還魂紙でいうところの“魂”とは、現代なら情報みたいなものにも当てはまるのかな、と思ったんです」
そうこうして誕生したのが、雑誌「ポパイ」やアディダスの空箱をすき込んだ和紙である。
「できたとき、これってなんじゃろと思って。面白いものなのか、それとも価値のないただのゴミなのか。実のところ、よく分からなかったんです。
それでもいろんな人に見せたら突拍子もない、っていう驚きではなくて、なるほどっていうインパクトを感じてもらえた。
それに『こういう素材を混ぜることもできる?』『これを崩すとどうなりますか?』っていう質問をいろいろもらえて、ああこれは面白いな、無限の可能性があるなと思ったんです」
ほかにもいろいろなものを混ぜてみた。


カラフルなチラシだったり、モノクロの漫画だったり。庭の泥や砂、珈琲の出がらし、チョコレートの原料であるカカオ‥‥面白そうだと思うものを片っ端から試してみた。
かつて和紙業界において別の素材を混ぜることはある意味、御法度とされてきた。けれど、先々代にあたる祖父はいろんな素材を混ぜて新しい和紙をつくっていたし、先代の父はといえばタブーとされる色づけを行った。
最後に残る1軒の工房として名尾和紙の伝統を守りながらも、最後の1軒だからこそ名尾和紙の伝統をアップデートしていく。
「うちの家系は元来、守るだけじゃなくて、新しいことに前向きなマインドがあるんでしょうね。僕自身も、和紙屋のどら息子がおかしいことやっとるなー、くらいに思ってもらえれば丁度いいな、と」
祈りを無駄にしない
そして谷口さんは還魂紙をメインとした活動を行うブランド「KAMINARI PAPER WORKS (カミナリペーパーワークス) 」を立ち上げた。
ロゴマークは雷を模したデザインだが曰く、
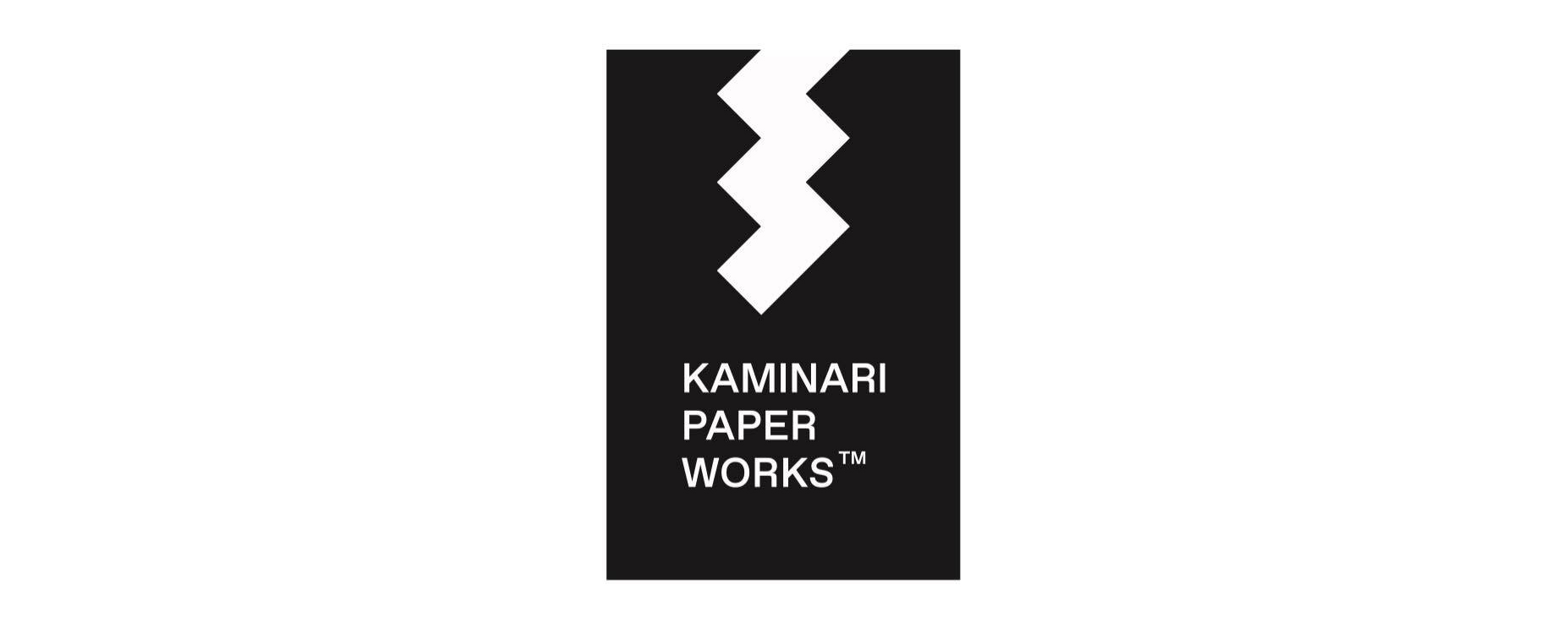
「これは注連縄(しめなわ)についている紙垂(しで/注連縄などについているギザギザの紙のこと)をイメージしたもの。注連縄は雲を、紙垂は雷を表し、雷が落ちた場所は五穀豊饒が叶うとされていて、言うなれば和紙業界全体に雷を落とせればいいなと。あとは単純に『なんでも紙になります』ってことなんですけど」
紙になります‥‥かみになり‥‥かみなり‥‥。コホン。
今ではその活動が、いろいろなカタチになり始めている。たとえば、これ。

大小さまざまなサイズの、多彩な色合いの紙が混ぜ込まれているが、その正体は、

千羽鶴だ。
長崎の原爆資料館に届くたくさんの千羽鶴を、そこに込められた祈りごと残せないかとこの葉書が生まれた。
「意味合い的にも、いいものができたと思います」
破棄してしまうのではなく、和紙にすき込むことで新しい形に生まれ変わり、人の思いが残っていくのだ。
カミナリペーパーワークスの取り組みは、東京・渋谷に新しくオープンした「渋谷PARCO」でもお目にかかることができる。美術専門誌の「美術手帖」が展開する直営店「OIL by 美術手帖」のカウンターに、歴代の『美術手帖』を細かく混ぜてすいた和紙が使われているのだ。

新しい和紙のカタチが、これまでの和紙の概念をふわっと軽やかに超えていく。谷口さんは言う。
「今までやってきたことを守りつつ、つなぎつつ、可能性をもっと先に延ばしていけたら」
絶賛、発展途上中。その道のりは果てしなく続くだろう。どこまでも、どこへでも。
<取材協力>
名尾手すき和紙
佐賀県佐賀市大和町大字名尾4756
0952-63-0334
https://naowashi.com/
文:葛山あかね
写真:藤本幸一郎








