【職人さんに聞きました】3児の父が手がけた、親子のための器
エリア

家で過ごす時間が増えた2020年。
中川政七商店から、親子の「食べる時間」をいつもよりちょっと深くする食器がデビューしました。
その名も「親子のための器」シリーズ。
お子さん向けの食器というと、落としても安心な木製やプラスチックのものも多いですが、
このシリーズはちょっと違います。
「落としたら割れてしまうという経験も込みで、ものに触れる時間を楽しんでもらいたい」
自身も4歳の子を持つデザイナーがそんな思いから企画したのが、つるつる、ざらざら、「触感」を楽しめるやきものの食器です。

たとえばマグカップは、底の部分に器をコーティングする釉薬をかけていません。
持った時に手の中でつるつる、ざらざらと違った手触りが感じられるようになっています。


一方で、子どもが持った時の安全性や、使いやすさも妥協はしたくない。
重すぎず、軽すぎず、丈夫で、やきものの風合いが楽しめる素材‥‥
検討に検討を重ねてたどり着いたのが、陶器と磁器のあいだの性質を持つ、「せっ器(半磁器)」でした。
やきものの中でも作るメーカーの少ないせっ器を手掛け、親心の詰まった商品のアイデアをかなえたのが、山功高木製陶です。

デザイナーの親心をかなえた、せっ器(半磁器)とは?
「ざらざらとした土の触感を味わうなら陶器ですが、陶器は薄く作ると欠けたり、割れたりしやすいんです。かといって厚くすると重みが出る。
薄く作っても丈夫なのは磁器ですが、今度は土っぽさがなくなります。
せっ器はある程度薄く作っても丈夫で、土っぽい手触りも味わえる。ちょうど陶器と磁器の中間のようなやきものなんですよ」

そう教えてくれたのは代表の髙木崇さん。デザイナーと一緒に試行錯誤しながらシリーズを作り上げました。

工房のある岐阜県土岐市は、古くから美濃焼を作ってきた町。陶器も磁器も手掛ける一大産地です。

「産地は分業制が進んでいて、たとえば駄知という町はどんぶりの産地として有名です。同じ市の中でも地域ごとに作るものが分かれているんですね。
うちの工房がある泉町は、『玉煎茶 (たませんちゃ) 』ってわかります?昔、公民館に行くと必ず見かけたような、青地に白い水玉模様の入った湯呑みをずっと作ってきた町でした」

しかし、こうした湯呑みを使ってお茶を飲むニーズが年々少なくなり、山功さんは作れるものを増やそうと、せっ器を手掛けるように。
陶器と磁器のいいとこ取りのような性質を持つせっ器ですが、あまり知られていないのは、作られるようになったのが比較的新しい時代だからだそう。

日本有数のやきもの産地であるこの一帯でも、手掛けるメーカーは限られるそうです。
「時代の変化に対応していきつつ、いろいろやっていくうちに扱う素材が増えて、アイテムもマグやプレートのような洋食器が増えて。気付いたら何でもできるようになってしまったっていう感じですね」

実は今回の器シリーズ、シンプルなつくりのようで、親子で使うシーンを想定したさまざまな設計の工夫がこらされています。

たとえば飯碗は、子どもの手で持った時に全体は「つるつる」、高台付近だけ「ざらざら」の触感を楽しめるように大きさ、厚み、重さを調整。
欠けやすい縁の部分は、厚めの「玉縁仕上げ」で丈夫になるようひと工夫。


平皿は、中の料理がすくいやすく、汁気のあるものも入れやすいように縁を立たせてあります。

デザイナーのイメージ、設計図と、前工程を担う生地屋さんや型屋さんの意見、高木さんの経験を掛け合わせながら、何度も試作をしてたどりついたかたちです。
「それと」
と髙木さんがおもむろに平皿の裏を見せてくれました。
「平皿だけは裏面にも釉薬をかけて、つるつるにした方がいいですよと提案させてもらいました」
重心が低く、置いて食べることが多い平皿は底部分を手で持つことが少ないので、釉薬が全体にかかっています。

その分サッと洗いやすく、親にも優しい設計です。
実は高木さん自身も、3人のお子さんを持つパパ。
作り手として、親として、どちらの経験ともが「親子のための器」のディティールに活きています。

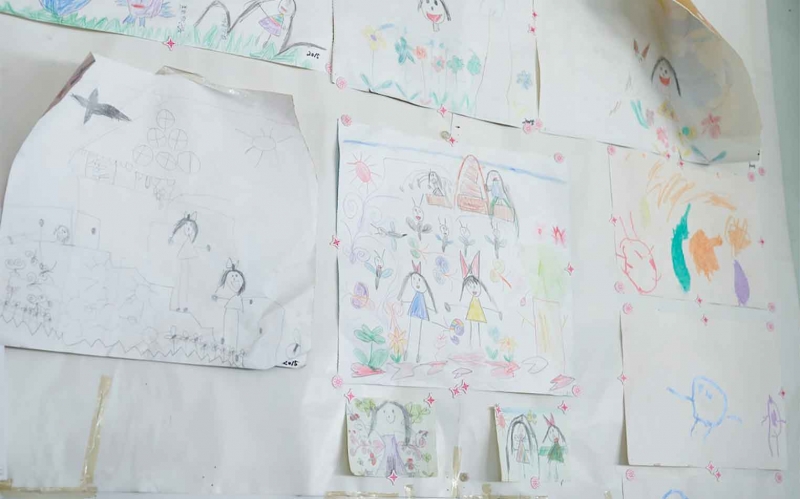

「上の子は、学校から帰ってくると家に帰らずに真っすぐ工房に寄るんですよ。
後を継ぐのかわかりませんが、もし将来やりたいといった時に、ものづくりが変わらずできる環境は残してあげたいですね」

親子のための器シリーズは、大きくなっても使えるシンプルなデザイン。
いつかデザイナーや高木さんのお子さんが大きくなった時に、食卓を囲みながら「この器はね‥‥」と語る日がくるかもしれません。
企画から製造の現場まで、親心がたっぷり詰まった「親子のための器」シリーズでした。
<取材協力>
株式会社 山功髙木製陶
<掲載商品>
親子のための器
<合わせて読みたい>
【デザイナーが話したくなる】親子のための器
関連商品
-

ずっと使えるベビースプーン
1,870円(税込)









