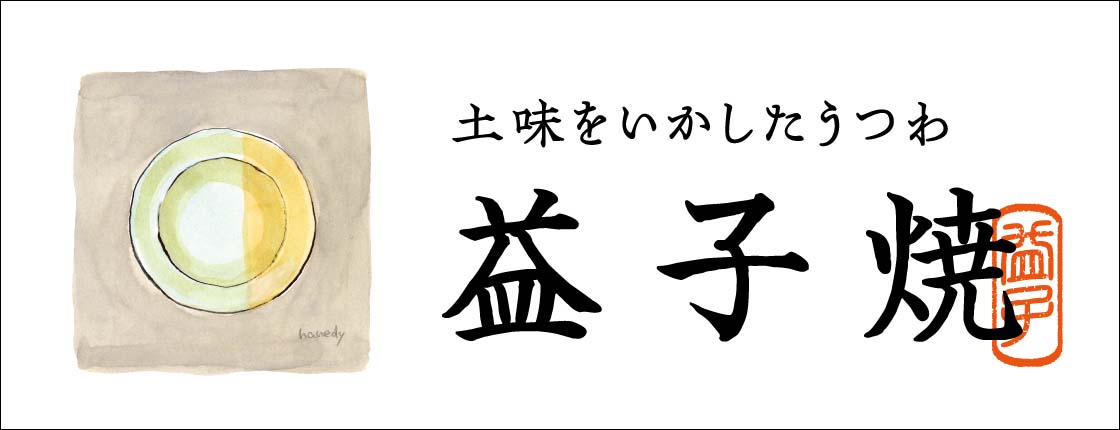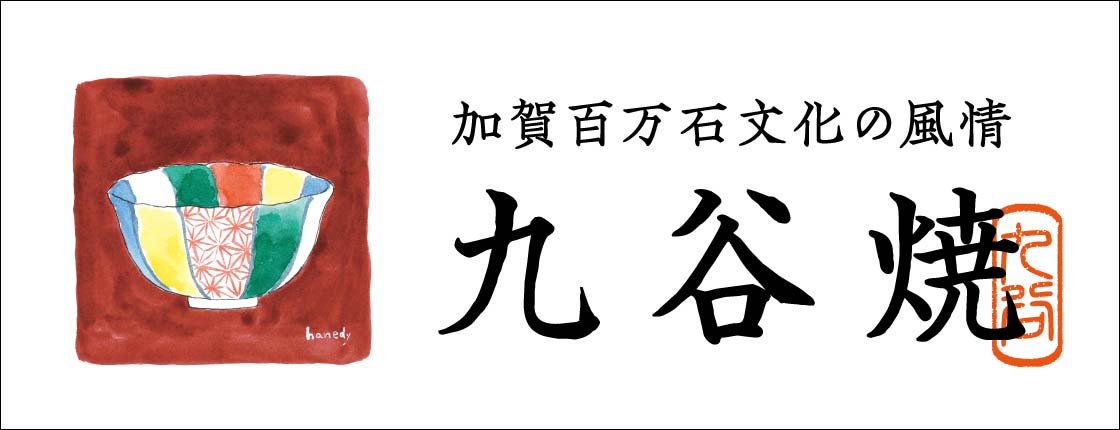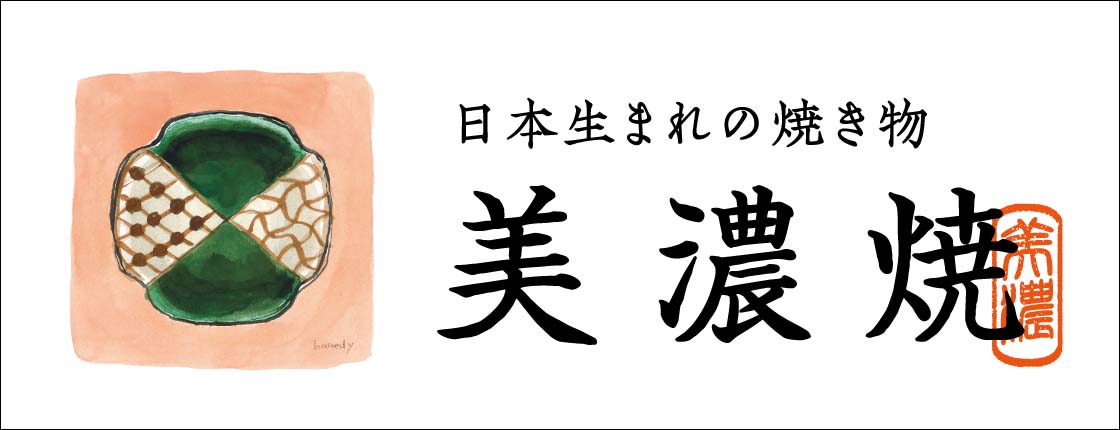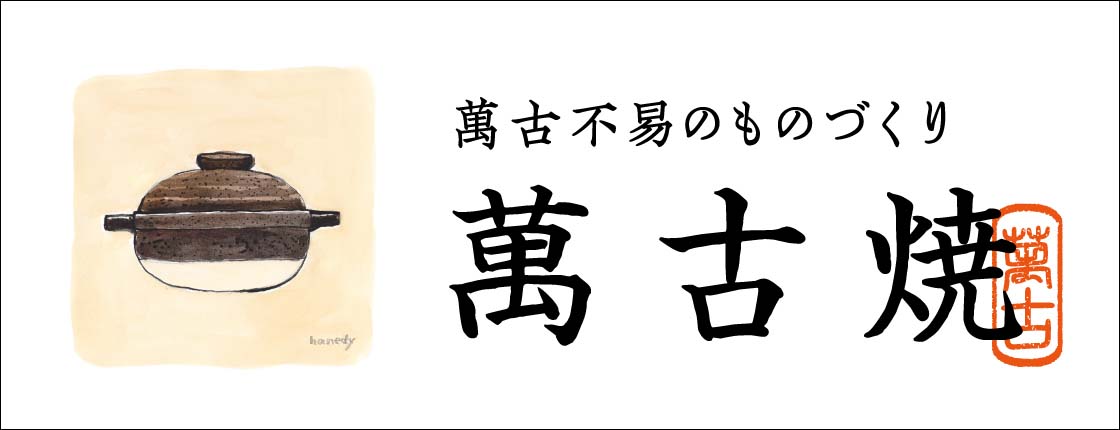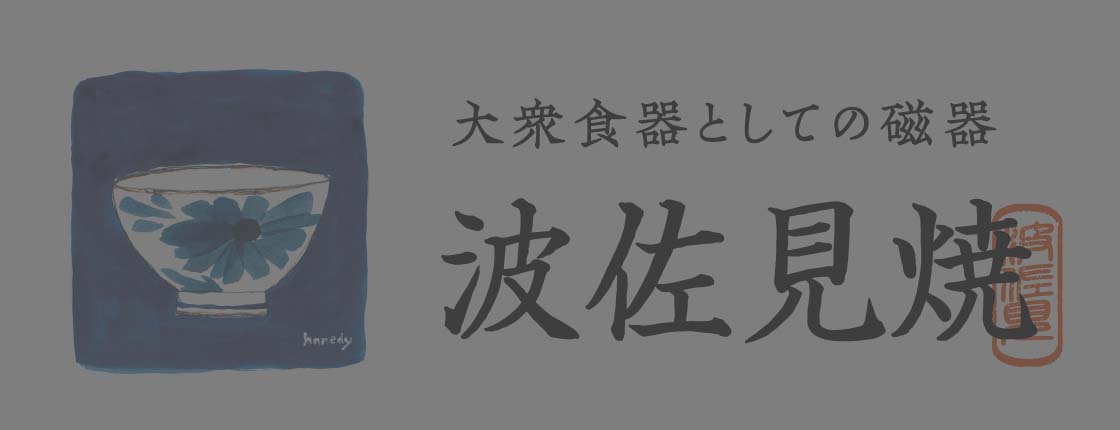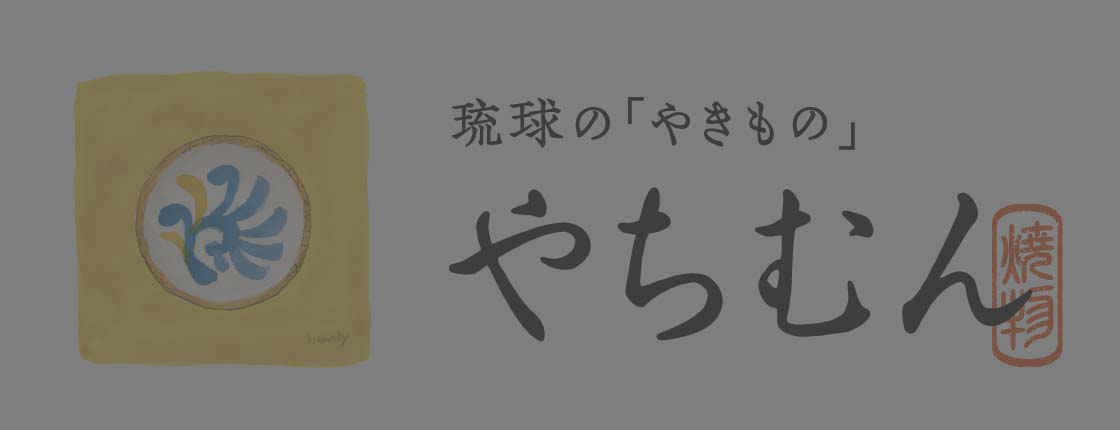有田焼の染付豆皿(梶謙製磁社)
エリア

特集「産地のうつわはじめ」

はじまりは、調味料用の「手塩皿」
今回ご紹介するのは、有田焼の「染付」シリーズです。小ぶりな佇まいと、中央に描かれたワンポイントの絵付けがなんとも愛らしい豆皿。

そのはじまりは、有田で生産されていた調味料用の「手塩皿」だといわれています。
古くは食膳の不浄を払うため、また好みで少量の塩や薬味を盛って食膳に添えるため、数多くつくられました。

こうしたゆかりのある地で、創業から250年以上焼き物を続けている老舗窯元「梶謙製磁社」とともに、素地に藍色のみで絵付けをした染付の豆皿をつくりました。
鹿・鶴・松・竹・梅と縁起のよいモチーフを、一つひとつ、女性の絵付け師さんが手描きで表現しています。さりげない濃淡や細やかな線が、職人の手仕事ならではの味わいです。

料理を引き立てる美しい白磁に素朴な絵柄を合わせたお皿は、おもてなしはもちろん、普段の食卓にも使いやすいのが魅力です。

国内で最初につくられた磁器「有田焼」

「有田焼」のはじまり
江戸時代の初め、朝鮮人陶工・李参平らによって有田町の泉山で磁器の原料となる陶石を発見し、日本で初めて白磁のうつわを焼いたことから「有田焼」が始まったと伝えられています。透き通るような素地の白さと、繊細で華やかな絵付けが特徴です。