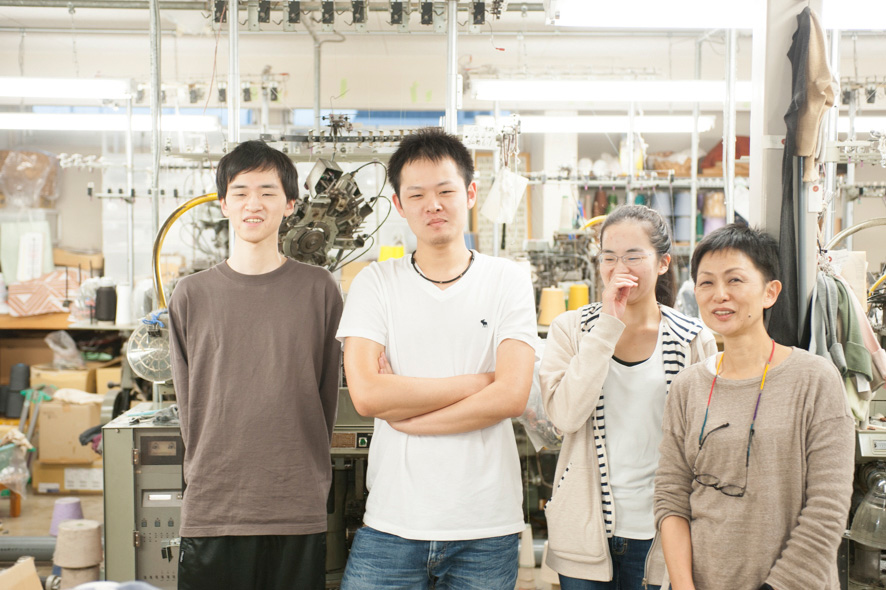「こんなに綺麗な青の鎌倉彫があるんだ」
三橋鎌幽さんの作品を初めて目にしたとき、心地よい驚きにしばらく見入ってしまいました。
鎌倉の街に住み、日頃から何気なく鎌倉彫を眺めてきた私の中で「鎌倉彫」のイメージが大きく変わった瞬間でした。
今回は、鎌倉の地で生まれた伝統工芸品「鎌倉彫」の物語をお届けします。
朱や黒の漆で塗られ、ごつごつとした彫り目が印象的で、どこか武家の力強さを感じさせられる鎌倉彫。
その誕生から、歴史に翻弄された過去、そして、現代のつくり手による新たな挑戦まで、壮大なロマンが広がる鎌倉彫の世界を、どうぞお楽しみください。
鎌倉で生まれた、武家由来の伝統工芸。

「鎌倉彫」の起源は、鎌倉時代。
源頼朝が鎌倉に幕府を開き、中国から禅宗の文化が入ってきた時代。寺社を建てるため、運慶、快慶の流れを引く慶派の仏師をはじめとする一級の職人たちが全国各地から鎌倉に呼び集められました。
当時の仏師たちは、仏像をつくるだけでなく、周辺の仏具の制作すべてを任されていました。その頃流行だった中国からの渡来物の中でも、堆朱(ついしゅ)や堆黒(ついこく)(漆を塗り重ねてから彫る技法)に魅せられた彼らが、その技術をどうにか仏具に使えないかと試行錯誤した結果、木を彫ってから漆を塗るという「鎌倉彫」の祖型となる技術が生まれたと言われています。

漆を塗り重ねて層を作って彫るという技術は、当時の日本では、実現がなかなか難しかったのでしょう。堆朱を追い求め、日本独自の木彫りと漆塗り器の技術を組み合わせて「鎌倉彫」の技法を生み出すまでに、実に100年もの年月が費やされたと考えられています。
そこから、700~800年の時を経た今なおその技術が受け継がれているのです。

「鎌倉彫」というのは、「木を彫り、漆を塗る」という技術とむすびついた総称。鎌倉でつくられているからではなく、鎌倉時代に生まれた技術だから「鎌倉彫」と呼ばれているのだと考えられています。
鎌倉彫は、江戸時代までお寺の仏像や、儀式で使用する香合などの仏具として発展をつづけてきました。しかし、明治時代になると文明開化や廃仏毀釈(仏教寺院や僧侶の大規模な弾圧政策)により、多くの職人が仏具の制作を続けられない状況に。仕事がなくなった職人たちは、鎌倉彫の技術を活かして、茶道具や一般の暮らしで使われる工芸品をつくるようになっていきました。

鎌倉の土産物屋さんでよく見かける、鎌倉彫のお盆やお皿などの生活用品がつくられるようになったのは、ここ150年くらいのことなのです。
そして、そんな激動の時代を生き延び、今でも建長寺や円覚寺の仏具制作を担っている数少ない仏師の血筋のひとつに、二陽堂の三橋家があります。
今回は、二陽堂の若手職人である三橋鎌幽さんにお話を伺いました。
800年の技術を受け継ぐ現代のつくり手。三橋鎌幽さんに聞く

二陽堂の職人として、仏具や茶道具制作をはじめ、一般の人たちに鎌倉彫の技術を教える鎌倉彫教室の講師業、国内の百貨店およびパリでの個展開催など、とても幅広く活躍されている三橋さん。
「伝統工芸というと“変わらずにいるもの”というイメージを持たれることが多いのですが、ずっと古いままではないんです。車のモデルチェンジのように、デザインや色、形、アイテムなどを時代に合わせて変えていく。これしか作ってはいけないと凝り固まるのではなく、時代が求めるものを常に考えています」
鎌倉彫を家業とする家に生まれ育ち、お父さんもお祖父さんも職人でした。そのため、子どもの頃は家に帰ると、そばで家族が木地を彫ったり塗っている姿が日常の風景だったといいます。
毎日の食卓にも鎌倉彫のお皿が普通に使われていたこともあり、三橋さんにとって、鎌倉彫は特別なものではなく、ごく日常的なもの。あえて意識しないくらい、いつもそばにあるものでした。

小学校高学年のときには、伝統工芸体験の一環で鎌倉彫の授業があり、お父さんが講師に来たことも。そのとき初めて、家業が伝統工芸なのだと自覚したそうです。
「子どもの頃はとくにものづくりが好きというわけではなく、野球少年でした。でも、彫刻はずっと身近でしたね。今思うと、小さな頃になんとなく彫っていた時間というのが財産になっているのだと思います」
そして、一度は大学の法学部へ進学したものの、最愛のお祖父さんが病に倒れたこともあり、就職活動を目前に家業を継ぐ決意をしました。
「自分しかできない仕事が身近にある、これは継がないといけないのではないかという心情になったんです」

“彫刻の街” パリで出会った運命の色。

鎌倉彫を継いだ三橋さんにとって、転機となったのは2017年の夏。2週間のパリ滞在でした。
「世界の彫刻家はだいたいパリに集まるんです。ミロのヴィーナスもありますし。石や鉄など素材は違いますが、彫るという動作は同じです。私も技術を求めてパリへ行きました。たぶん運慶たちが今の時代に生まれたら、彼らもきっと行っているはず」
地元の芸術家たちから多くの共感を得たことが鎌倉彫職人としての自信につながったのだそう。

「ミロのヴィーナスやニケの彫刻を目にしたときは、(技術的には)思っていたほどじゃない、という感覚がありました。日本で見てきた運慶の仏像の方がすごいな、と。一方で、ヨーロッパの彫刻には、日本にはない美しさがあるとも思いました。
パリに行ったことで自分の技術に対して自信が持てたというか、世界でも鎌倉彫の技術は胸を張っていけるのだと。ヨーロッパの人たちと話したことで気づきました」
そしてこのとき、後の三橋さんの作品づくりに大きな影響を与えることとなる、忘れられない出会いがありました。
パリのサントシャペル教会で目にした、ロイヤルブルーと金のコントラストです。
「じつはずっと漆器の青は邪道だと思っていたんです。でも、パリに行くと教会はだいたい青と金と黒がベースカラー。初めて目にしたときは、『おお!』という感じでしたね。青がとにかくきれいでした。作品に青を取り入れるようになったのは、パリに行ったからなのです」
自分が目にした感動を、鎌倉彫の作品で表現したい。
そんな思いから、三橋さんは以来、青と金のコントラストを積極的に作品に取り入れています。

かつて自分にも抵抗感があったように、鎌倉彫の青は日本の人たちに受け入れられるのだろうか。
帰国後、不安を抱えながら開いた日本の個展では、思いの外、幅広い層の人々から青い鎌倉彫への高い評価を得ることができたのです。新しい鎌倉彫が時代から求められていることを三橋さんは強く感じたのでした。
ちなみに、漆の青というのは塗料の技術の中でも新しく、100年前にはあまりなかったのだそう。漆の艶感を持った青色は、現代の人だからこそ実物で見ることができる色なのです。
鎌倉彫ができるまで。100年後に残すものづくり

鎌倉彫のものづくりは、100年もの持続年数を見込んでつくられます。
100年と聞くと、現代人にとっては想像もつかないようなスケールです。でも、例えば、昔は衣服も直しながら何十年と着ていたように、当時はものを長く使い続けることが“ごく自然な感覚”だったのでしょう。
結果として、漆器や、特に仏具のものは、それこそ100年、200年と使われることもあるそうです。
そんな鎌倉彫の漆器は、実際のところ、どのような工程でつくられていくのでしょう?
三橋さんに彫刻作業を実演していただきました。




鎌倉彫の作品づくりは大きく分けて、「デザインを考える」「木地をつくる」「彫刻をする」「漆を塗る」の工程があります。
とくに木材の決まりはないものの、仏像をつくっていたという経緯から、仏像や仏具制作に使われる桂、朴、檜、銀杏などの木が選ばれることが多いようです。

製造工程のなかで、漆塗りの50工程のため、ひとつの鎌倉彫作品ができるまでには最低1〜2か月はかかるといいます。
そんな風に、自然にまかせて、人の力ではどうにもならない時間があるのが、工芸というものなのかもしれません。


できあがった作品は、10年、30年と、時間が経つことで、色味も落ち着いていきます。塗りたてからしばらくの間は光を表層で反射する漆も、50年くらい経つと内部の硬化も進み、さらに透けていくという特性があるのです。
「漆器は仮にまっぷたつに割れても、荒っぽく言うと上から漆を塗って固めれば元通りに戻せます。耐久年数は、日本の工芸が持つ強みだと思いますね」
未来につなぐ。鎌倉彫の新たな挑戦。

海外での個展開催や、鎌倉彫作品における青の探求に加え、2018年から三橋さんが新たに挑んでいるのがファッションの世界です。
フランス人のクリエイティブディレクターを迎えて始動したファッションブランド「Niyodo Style」では、国内外のクリエイターとコラボレーションしながら、名刺入れやブローチ、バッグなど、これまでの鎌倉彫のイメージを刷新するようなモダンで洗練された作品を創り出しています。

「現代でデザインが一番反映されるのはファッションだと思うんです。誰もが生活に欠かせず、流行が顕著にあらわれるからこそ、かなり速いスピードで具現化されていきます。一方で、鎌倉彫は100年くらいのスケールでものづくりをします。
ファッションのようにものすごくファストなものと、ロングスパンなものの両方に身をおくことで、何か刺激的なものや、新しい可能性が生まれるんじゃないかと思っています」

時代に翻弄されながらも、800年の時を超えて受け継がれ、独自の発展の道を歩んできた「鎌倉彫」。
この唯一無二の芸術品を次の世代へと残していくために、日本から世界へ、三橋さんの果敢な挑戦は続きます。
<取材協力>
鎌倉彫二陽堂
住所:神奈川県鎌倉市坂の下12-6
TEL:0467-22-6443
文:西谷渉
写真:長谷川賢人
*こちらは、2019年3月8日の記事を再編集して公開しました。
合わせて読みたい
〈 工芸の新たなる挑戦 〉
伝統を受け継ぎ、未来を拓く。全国に芽吹く、職人の挑戦を追いました。
「飛騨の匠」の技術で木の新しい可能性を引き出す、飛騨産業の家具づくり

時代を超え、その伝統技術を受け継いだ家具をつくっているのが、飛騨産業株式会社。進化し続ける独自の技術や、流行に左右されず愛され続けているデザインについて紐解いていきます。
金型屋がなぜ名刺入れを作るのか?ものづくりの町の若き会社MGNETの挑戦

金型ですが、日本の技術は精度が高く、世界一を誇っています。ものづくりの縁の下の力持ち、金型を作る会社の挑戦をご紹介します。
里山から始まる堆肥革命~“飛騨高山のフンコロガシ”の挑戦~

いま、一部の農家でとんでもなく大きな注目を集めている「堆肥」がある。
まだ日本でもごく一部にしか知られていないこの堆肥は、もしかすると農業に革命をもたらすかもしれないのだ。