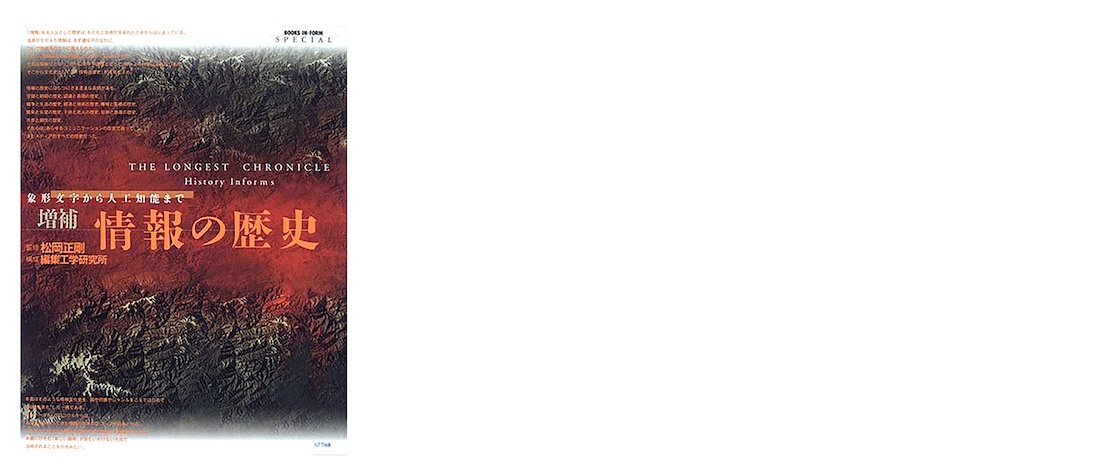2016年に創業三百周年を迎えた株式会社中川政七商店。その十三代当主である中川政七と、各界を代表するゲストが互いの専門分野をクロスさせて語らう対談企画。
第1回のテーマは「工芸と歴史」。”知の巨人”として名高い日本文化研究の第一人者、松岡正剛氏をゲストに迎えます。事前に寄せて頂いたコメント冒頭の一文は、「今、工芸の半分が、死んでいる」。いきなり核心に迫る幕開けです。
(以下、松岡正剛氏発言は「松岡:」、中川政七発言は「中川:」と表記)
バックミラーで歴史を映す
中川:今年、中川政七商店は三百周年を迎えたのですが、様々な角度から工芸を捉え直してみたいと考えました。そこで、各界で活躍されている方と対談をして知見を深めていこうというのが、今回の企画の主旨です。
第1回は、未来を考えるにはまず過去を知らなければいうことで、工芸×歴史をテーマに選びました。工芸も含めた日本の文化の変遷を紐解くなら、この方以外にはまず考えられないだろうと思います、記念すべきお一人目のゲストは“知の巨人”、松岡正剛さんです。どうぞ、よろしくお願いいたします。
松岡:今日はよろしくお願いします。三百周年、おめでとうございます。
中川:ありがとうございます。実は正剛さんとお会いするのはこれが初めてではないんですね。そもそも三百周年を機に、社史をちゃんと整えようと思ったのですが、自社の資料がたいして残ってないので、どうせならもうちょっと広げて工芸の歴史全体を読み解きたいなと思ったのです。
ちょうどその時に松岡さんの『情報の歴史』(NTT出版)がイメージに浮かんで、松岡さんをたずねました。最初にお会いした時に松岡さんが言われた「歴史というものは未来を作るためにある」という言葉が、いまでも印象に残ってます。
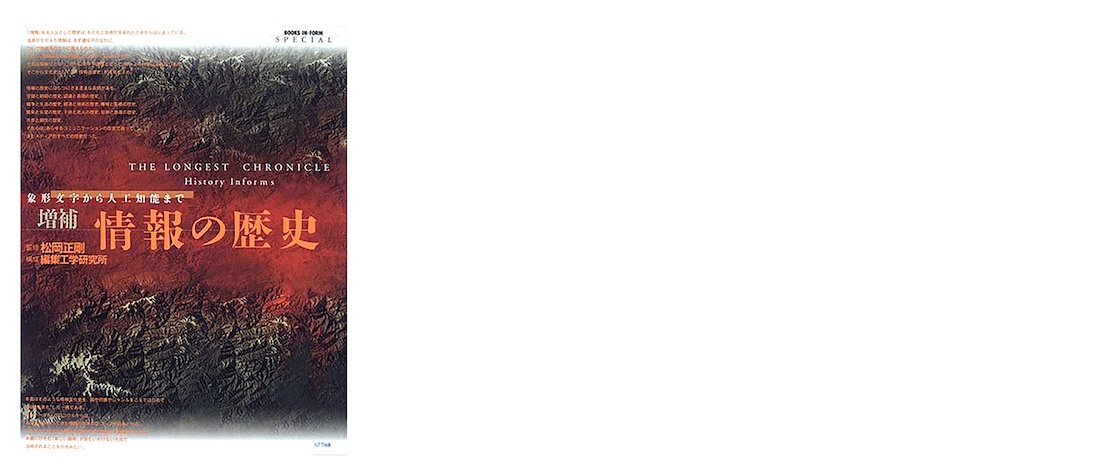 対談のきっかけとなった『情報の歴史』(NTT出版)
対談のきっかけとなった『情報の歴史』(NTT出版)松岡:最初に中川さんと交わした時の歴史と未来というのは、「バックミラーで歴史を映しながら前へ進む」ということです。そのバックミラーは一個である必要はない。いくつものフィルターやミラーで歴史をセレクトするのがいい。歴史を選定して前へ持って行くということです。その装置さえあればどんな未来へも進めます。その場に応じたものに歴史を持ってくることができるのは、未来が先行しているからです。
中川さん独特のセレクト感覚のもとで、立体的で不思議なバックミラーが作れれば面白いなというのが、僕が最初にあなたと会った時の「歴史は未来」と言った意味なんです。
中川:なるほど、今伺うと、よりはっきりとわかります。
松岡:そもそも中川さんが自分の会社の「のれん」に歴史を感じたのはいつ頃からなんですか。ビジネスコンサルティングという手法とシナリオと戦略を持って工芸の業界に入って、それが元々の家業とも重なっているわけだから、とてもユニークなケースだと思います。変なニュータイプ。「のれん」にこだわりがあるような、ないような。必然性があるような、ないような、ね。どの辺からそういうことをした方がいいと思い始めたんですか。
中川:変なニュータイプですか(笑)。工芸メーカーへのコンサルに関して言うと、何か戦略性が先にあったわけではなく、もう必要に迫られてなんですね。この仕事に入った頃、世の中ではファストファッションがどーんときている時で、要はたくさん作ることで安く作れる。それもあるかなと思ったのですが、こと工芸に関していうと、1000個作るから安くしてって言いに行ったらそもそも断られる。「いや、うち1000個も作られへん」って。
松岡:なるほど、工芸の特殊性に気づいたわけだね。小さなロットの注文生産だからね。
中川:1000個作るために100個作れるところを10軒探すのはすごく大変です。そして毎年のように廃業の挨拶に2、3軒来られる。このままいくとまずいなと思いました。それで、「日本の工芸を元気にする!」というビジョンを掲げました。元気にするには彼らが自活していく道を考えなきゃいけない。そうすると経営に直接手を入れるしかないって思ってやり始めたんです。戦略的にというよりは、生きるためにスタートしたんです。
松岡:工芸や民芸を支える文化や基盤が今の日本にしっかりあるかっていうと、無いと思います。例えば、言葉の歴史を見てみるとよく分かります。言葉は当初、非常に意味が多様なんです。「自由」という言葉でいうと、日本では「自由狼藉」のように「勝手気まま」という意味があった。
しかし、明治維新後に「リバティ」という言葉が入ってくると、西洋の価値観も流入してくるわけです。単なる「勝手気まま」ではなく、民主主義や自由主義を含めた「自由」という言葉に変わっていく。次第に、リバティ的「自由」の意味が主流になっていくんですね。そうすると、「自由」の意味の多様性が少しずつ失われていく。本来言語は正反対の意味を内包するほどに多様です。日本でいうと江戸の粋(イキ)に対して京都の粋(スイ)、公家の「あはれ」に対して武家の「あっぱれ」。
中川:確かに、「あはれ」と「あっぱれ」では全く意味が変わってきますね。
松岡:そこが言語の面白さなんですが、リバティだけになってしまうと価値観が単一になっていくんですね。これは「工芸」に関しても言えることです。一時期は多くの人が「工芸」はこれでいいのか、「民芸」と言う方がいいのか、という風に向き合った時期があった。けれど、主流に対する反対・アンチが出にくくなっているのではないかと思います。
かつて、工芸の中には信仰も祈りも縁起物も、たくさんの意味と価値観が含まれていたけれど、もうそれは細かく散ってしまっている。お土産品とか民芸品とかは一体何に使うんだろうとみんな思い始めています。そこにきて、中川さんが話したように、メーカーが非常に少ないロットの中で戦っているということは、中川政七商店だけが抱える問題というよりも日本全体がそろそろ考えなければいけないことでしょうね。もしこれから新しい工芸を作り直すのだとしたら、今言ったようなことを一挙に起こしていった方が面白いと思います。
中川:そのためにもきっと「バックミラーで歴史を映しながら前へ進む」ことが大事なんですね。
弁慶の七つ道具と工芸の意外な関係
中川:改めて工芸の歴史を振り返ってみると、工芸とは、そもそも自分たちが使うものを自分たちの手で作るところから始まっていると思います。そこから始まって、権力者がお抱えで作らせていた時代がある。利休の黒楽茶碗みたいに、自分で作るのではなくプロデューサー的な人が出てくる。
さらに時代が進んで一般庶民も工芸品を買うようになって、量が必要だから効率的に作るようになる。それが商売になると思ってだんだん産地が形成されて流通も発達してくる。時代背景が変わるとそれに応じて工芸を取り巻く環境も変わる。だからその度に工芸のあり方も変わってきたのです。
松岡:工芸はいつでもその時代の長所と短所を技術面と意匠面の両方で抱えながら生まれ育ってきています。ただ生活技術やファインな表現技術にくらべると、少し遅れてセットされていく。
中川:それが遅れると衰退になるし、遅れなければ常に産業として成立していく。ここ30年のことを言うと日本の産地の出荷額は1/4以下になってるわけで、間違いなく工芸の世界は衰退しているんですよね。衰退の理由ははっきり分かっています。それは物を作ってる人と使う人の間が、時代と共にすごく遠くなってしまったことです。その時期に商売として栄えたからこそ人が集まってくるんでしょうけど、結果的には距離ができてしまって衰退の時代を迎えて今に至っています。それが未来への一つの示唆でもあると思うんです。
松岡:そこを中川政七商店はどうしようとしているの?
中川:当たり前のようですけど、距離が近くなればいいんじゃないかって思いました。とはいえ、自分で作って自分で使うわけにいかないので、今の時代における近くなるって何なのかを考えました。
その一つの解答は、「産業観光」なんじゃないかと思っています。産業観光というと世界遺産に認定された富岡製糸場のような産業〈遺跡〉を見学に行くものを思い浮かべがちなのですが、僕の言う産業観光は、生の産業を見に行く観光です。
現在進行形で動いている工芸の現場を見るのは刺激的だと思います。その兆しは既に出ていて、新潟の燕三条地区が年に1回だけ「工場の祭典」というオープンファクトリーを開催しています。ふだん稼働している生の職人の現場を開放しているのですが、扱うものが金属なので火もあって派手なんです。見たら誰でも「おー」ってなるし、そこで作られた物が横で売られているとやっぱり欲しくなる。全国から3万5千人を超える人が来ています。そういう作る人と使う人の近さが、もしかしたら一つの未来像なんじゃないかなと思うんです。
昔は流通が発達して物を動かしたけれど、今は人を動かしてそっちへ寄せていく。そうするとその現場だけじゃなくその周辺の土地性も含めて楽しめる。産地に来て見てもらうことが工芸の未来だと思うんです。
松岡:そういう意味では、歴史の中にも産業観光的なことはあったと思います。例えば奥州平泉で秀衡椀という器が作られる。そこには金が関わりますね。産業があるレベルに達すると、「奥州でなぜかおもしろいものが出来上がって都にまできた」と伝播します。するとどんなものだろうとみんなが見に行くんですね。奥州街道をずっと越えて、未知のものを見に行く。 義経の奥州下りに出てくる金売吉次(かねうりきちじ)は金の商人だし、弁慶が持っていた七つ道具は鉱山開発の道具です。そのうち義経と弁慶の物語がそうだったように、工芸だったものがお芝居になり、技術だったことが謡曲にもなる。これも観光であり、文化なんです。
中川:弁慶の七つ道具も、実は土地の工芸と関係していたんですね。
松岡:奥州に不思議なものがあるというのが噂になって、メディアが伝える。物がいいということだけではなく、たくさんの物語がくっついて、進化するんです。これらがいずれ浮世絵にもなり、最後には童謡のようなものにもなる。メディアを次々と乗り換えながら工芸がアートや物語になっていきます。「工芸の復活」ということが我々の一つの目標だとして、そこに何が足りないかというと、もちろん投資や職人さんの力などもありますが、こういった「変換」が必要なんだと思うんです。
中川:変換というのはどういうことですか?
Historyから新しいStoryを生み出す
松岡:お茶を例にすると、お茶摘み自体の観光力も多少はありますが、それが茶の湯に変換されたことが大きかった。「ちゃっきり節」という民謡になったり、それが鉄道唱歌になったりした。そのうち駅弁とお茶がワンセットになっていった。そういう変換が起きていくことが重要なんです。 ありとあらゆるものがかつては工芸品にくっついていたんですね。これらの変換によって次々と観光の資源が生まれていたんです。
最近の浴衣にしても、夜店や花火に着ていく人は増えていますが、それだけでは物語の数が少なすぎる。もっと祭りやコンサートやスポーツ観戦にも結びつくべきです。 産業観光というものが起こるんだとすれば、もっといろいろなものが変換され、転用され、転写されて増えていった方がいい。
中川:なるほど。松岡さんが本で書かれていた「物語を構成する5つの要素」を思い出しました。 物語の舞台となる「ワールドモデル」がまずあって、そこで「ストーリー」が繰り広げられる。「ストーリー」を進めるのは物語を生きる「キャラクター」と象徴的な「シーン」、そして読み手と物語の世界をつなぐ「ナレーター」、でしたね。
僕は、そういう物語をちゃんと作って多くの人が興味を持ってくれれば結果的に生き残っていけるし、商売として成り立つと信じています。僕らはたまたま工芸にいるからそれが起点、「ワールドモデル」になるわけですが、それだけじゃ物語は起こらない。だから昔のことを調べるんです。あるいは職人さんに専門的なことをいっぱい教えてもらう。彼らが「キャラクター」になることもある。 昔からのいろんな面白い話があるわけじゃないですか。それがまさに文化だと思うんです。それらをていねいに勉強しながら、その中にある面白いタネ、「シーン」や「ストーリー」や「キャラクター」を見つけ出してきて、変換する。僕らが「ナレーター」になるんです。
変換してたくさんの物語にすることでそれは伝わるし、伝わるとそこに物が売れるということも付いてくる。それが膨らんできて、ある一定の膨らみになると人が来始めるんだと思います。それは、ずっと中川政七商店がやっていることです。だから工芸じゃなくても実はできると思うんです。お酒であっても農作物であっても。
松岡:そうそう、そういうふうになった方がいいですね。今の日本を面白くするには、工芸もお酒も書も花も全部が一斉に立ち上がらないと駄目なんです。 今の日本の多くの企業のように、グローバルで勝ち組になるしかないっていうロジックだけではいけません。だって勝つのは少数だから。勝っても負けても成立する物語がもっと増えないといけません。 Historyという言葉にStoryという言葉が入っているように、歴史をめぐる面白さはやっぱり物語性なんですよ。
中川:歴史や背景をきちんと見ない限り新しい物語は紡がれないと思っています。創業三百周年という節目は、まさに歴史をバックミラーで見ながら未来に向けた物語を考える、ちょうど良い機会だったと思います。歴史の中から工芸や産地の新しい物語を紡いでいくことを、ひたすらずっと、やっていくのが僕らの生業なのかなと思います。
松岡:ぜひそうして下さい。これからの活躍を楽しみにしています。
話者紹介
松岡 正剛(まつおか せいごう)
雑誌『遊』編集長、東京大学客員教授、帝塚山学院大学教授を経て、現在編集工学研究所所長、イシス編集学校校長。日本文化、芸術、生命哲学、システム工学など多方面におよぶ思索から情報文化技術に応用する「編集工学」を確立。日本文化研究の第一人者として「日本という方法」を提唱。システム開発、企業プロデュース、地域文化再生など多彩なプロジェクトを手掛ける。
中川 政七(なかがわ まさしち)
中川政七商店代表取締役社長 十三代。京都大学法学部卒、富士通株式会社を経て中川政七商店へ。「遊 中川」「中川政七商店」「日本市」などのブランドで直営店出店を加速させ、工芸をベースにしたSPA業態を確立。「日本の工芸を元気にする!」をビジョンに掲げ、業界特化型コンサルティングを各地で行う。2016年11月、十三代政七を襲名。
写真:井原悠一