こんにちは。
中川政七商店ラヂオのお時間です。
「工芸うんちく旅」は、工芸好き男子ふたりが、日本の工芸産地をめぐり、職人さんや地元の方々から聞いてきたうんちくや小ネタ、地域の風習、食文化などを紹介する番組です。
奈良県/祈りと工芸
工芸好きアラフォー男子ふたりが工芸産地を巡り、職人さんや地元の方々から聞いてきたうんちくを紹介する番組「工芸うんちく旅」。今回は中川政七商店の本拠地、奈良県を巡ります。
かつて日本の中心地であった奈良。その歴史を語る上で、神社仏閣とは切っても切り離せない関係にあります。そこで今回は「祈りと工芸」というテーマを軸に、奈良を巡りました。祈りの対象として工芸が発展してきた歴史を訪ねて、神社仏閣や工芸に通じるものづくりの現場に伺いました。
初回は、観光スポットの大定番にもなっている、東大寺の大仏を見に行ってきました。ご案内いただいたのは、奈良で宿泊施設や飲食店を経営されており、奈良の文化や仏像に詳しい古白の境 祐希さん。
現在でも謎多き、東大寺の歴史や、過去に2度の焼失を経て再建された経緯、南大門の金剛力士像にまつわるうんちく、さらには東大寺の3月の風物詩である『お水取り』の様子などなど、目白押しの内容でお届けします。これを聴けばあなたも奈良に行ってみたくなる!?奈良のディープなうんちく旅のスタートです。
プラットフォーム
ラヂオは7つのプラットフォームで配信しています。
お好きなプラットホームからお楽しみください。
・Spotify(一話・二話・三話・四話)
・Apple Podcast(一話・二話・三話・四話)
・Google Podcasts(一話・二話・三話・四話)
・Voicy(一話・二話・三話・四話)
・Amazon Music(一話・二話・三話・四話)
・Castbox(一話・二話・三話・四話)
・YouTube (一話・二話・三話・四話)
ナビゲータープロフィール
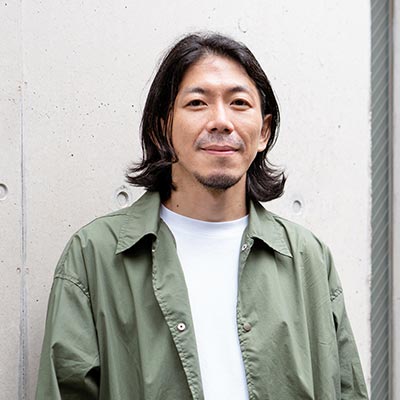
高倉泰(たかくらたいら)
中川政七商店による産地支援事業「合同展示会 大日本市」のディレクター・バイヤー。
大学卒業後、店舗デザイン・設計の会社を経て、2014年に中川政七商店に入社。日本各地のつくり手と共に展示会やイベントを開催し、商品の仕入れ・販売・プロモーションに携わる。
古いものや世界の民芸品が好きで、ならまちで築150年の古民家を改築し、 妻と2人の子どもと暮らす。山形県出身。日本酒ナビゲーター認定。ほとけ部主催。
twitterアカウントはこちら

引地海(ひきじかい)
Pomalo 株式会社 クリエイティブ・ディレクター。大学卒業後、広告代理店を経てフリーの編集者に。雑誌やWEBサイト、イベントの企画・制作・プロデュースを手がけ、2019年よりコンテンツ・エンジニアリング・カンパニー Pomalo(ポマーロ)に参加。11歳から17歳までをアメリカ・サンディエゴで過ごした帰国子女。2児のパパで、趣味はお弁当づくりとキャンプ。
Instagramアカウントはこちら
ご質問・ご感想を募集しております
パーソナリティへの質問や、ご視聴の感想、ここに行ってほしい!といったリクエストなど、お聞きしたいこと、お伝えしたいことがあれば、お気軽にコメントをお寄せください。
皆さまからのお便りをお待ちしております。

次回予告
次回「工芸うんちく旅」は、4月21日(金)配信を予定しています。
「中川政七商店ラヂオ」では、別番組「季節の手ざわり」も配信中です。
こちらは、月に一度、季節ごとの風習や、暮らしに取り入れたい日本の文化についてお届けしています。
次回は5月5日(金)配信予定です。
お楽しみに。









































