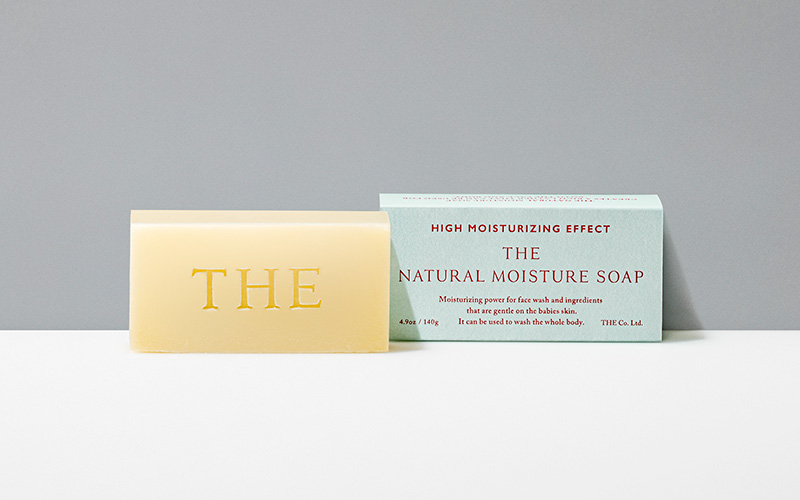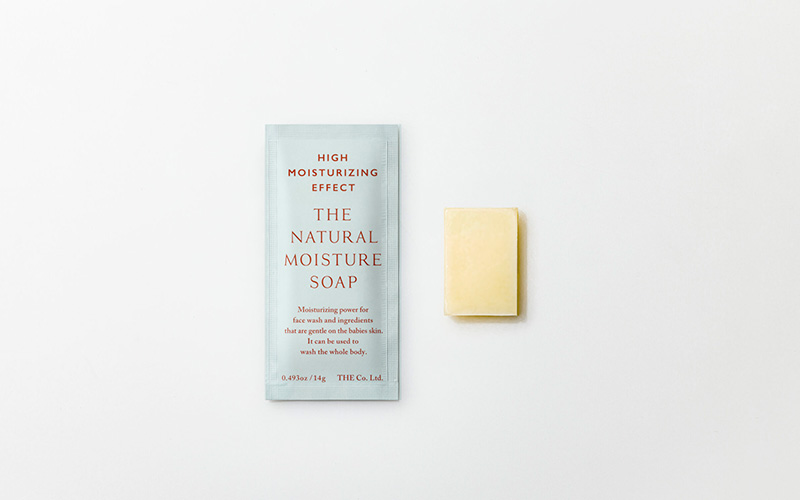お米が貴重になった今、見直したわが家の米びつ事情
2人暮らしのわたしたち夫婦は、そろって白米が大好きです。
炊飯器は使わず、土鍋や琺瑯鍋で炊くことが多いのも、わが家なりのちょっとしたこだわり。
そんな“お米LOVER”なわたしたちですが、実はひとつ後ろめたいことがありました。
それは、お米の保存方法がずっと適当だったこと。

買ってきた袋のまま棚にどーんと置き、口をぎゅっと閉じておくだけ。
(きっと、同じような方、たくさんいらっしゃいますよね‥‥汗)
「おいしいごはんのために、保存にも気を配りたい!」
そう思いながらも、理想の米びつにはなかなか出会えずにいました。
冷蔵庫で保存するのがいいとも聞きますが、わが家のストック量を考えると、とてもじゃないけど入りきりません。
そんな状態が、気づけば2年以上。
でも最近のお米の価格高騰をきっかけに、「一粒一粒をもっと大切に食べたい」と思うようになりました。
湿気が気になるこの季節の対策も兼ねて、ついに米びつを迎える決心をしました。
たくさん悩んで、素材や仕様を検討した末に選んだのが、「調湿できる桐の食品保存箱」 です。
「桐の食品保存箱」を米びつに選んだ理由
・優れた調湿機能で、梅雨や常温保存の強い味方に
桐には湿度を調整する力があるうえに、虫が嫌うタンニン・パウロニン・セサミンといった成分が含まれており、まさにお米保存にぴったりの素材。

ちょうど「古米の備蓄販売」のニュースを見て、「古いお米ってどんな感じなんだろう‥‥?」と気になり調べてみたところ、古米は新米以上に保存状態に気を遣ったほうがいいのだとか。
「今、見直しておいてよかった‥‥!」と、ちょっとした自己満足にもなりました。
・軽くてコンパクト、それでいて5kgも入る!
一般的な米びつの容量は2kg・5kg・10kgなどがありますが、わが家はいつも5kgを購入しているので、自然と5kgサイズに絞って探すことに。
ただ、5kg入る米びつって意外と大きいんですよね。賃貸の狭いキッチンにも置けるよう、できるだけコンパクトなものを探して比較した結果、候補の中で一番小さくて収納性に優れていたのがこの保存箱でした。

手元に届いたときには「えっ、これで本当に5kg入るの?」と疑ったものの、ぴったり収まりました!
残りが少なくなっても、本体が小さく軽いのでひっくり返して移し替えるのもラクちんです。

・とにかくシンプルな構造
当初は、よく見かけるスライド式の蓋つき木製米びつも検討していましたが、サイズが大きかったり見た目が少し主張しすぎる印象がありました。
その点こちらは、載せるだけのシンプルな蓋とすっきりとしたデザインで、インテリアにも自然になじみます。

蓋をパカッと開けて、さっとお米をすくうだけ。とにかく扱いやすくてストレスなしです。

米びつを変えただけなのに、なんだか炊飯の準備まで楽しくなりました。
お米が貴重な今だからこそ、日々のごはんの時間をもっと大切にしたい。
そんな気持ちに、そっと寄り添ってくれるアイテムです。
<紹介した商品>
調湿できる桐の食品保存箱
文:岩井