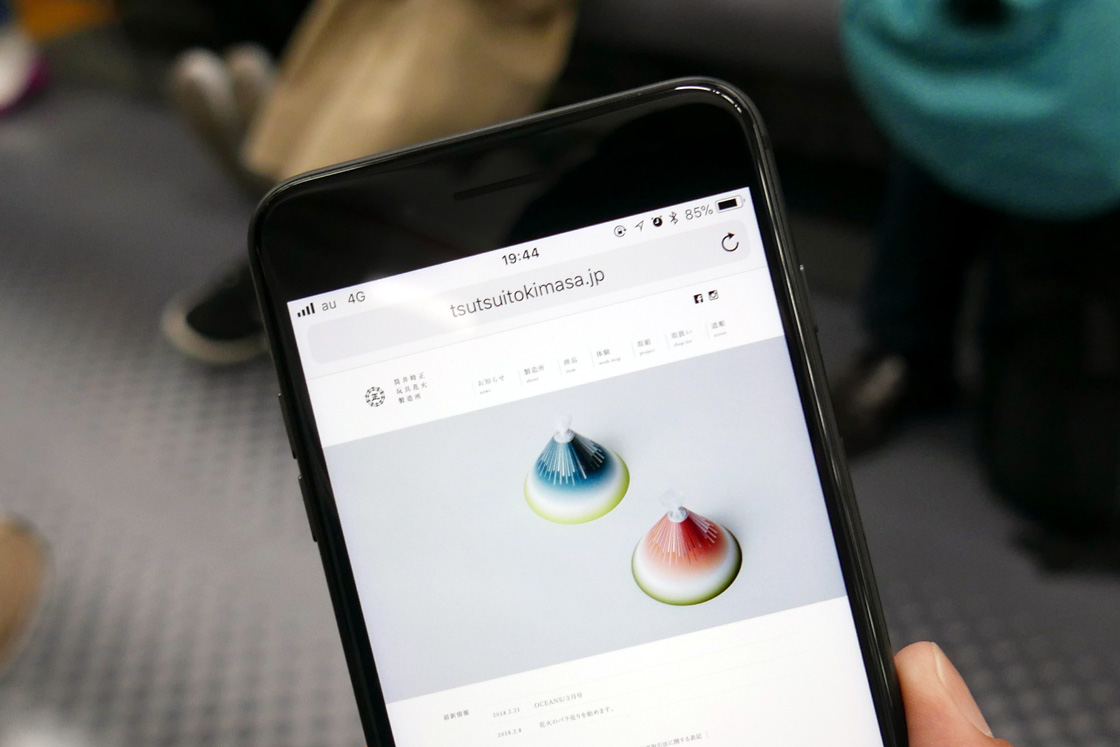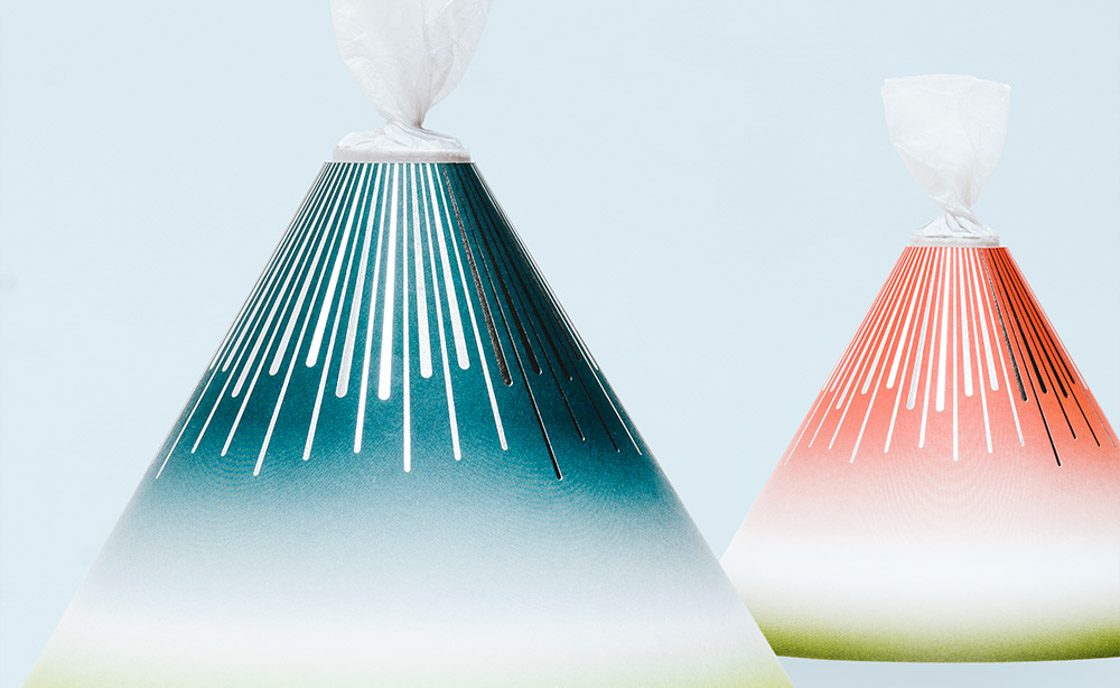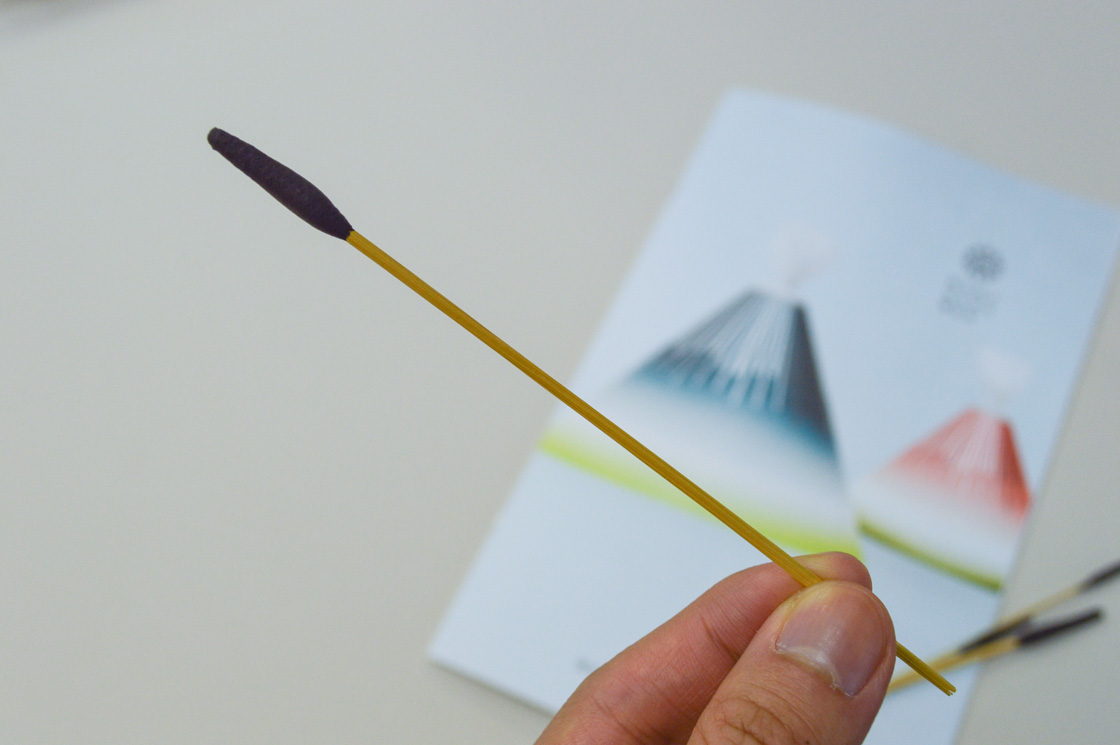京都・西陣。閑静な街並みに佇む豪奢な町家建築が、西陣織で栄華を極めたかつての面影を残している。
歴史ある建物のひとつに新たな息吹をもたらし、築160年の町家を再生させた「京旅籠 むげん」。
かつて全国を旅した永留和也さんとあふるさん夫妻が、この街に魅力を感じてオープンした5組限定の町家の宿だ。


随所に宿る、京都の職人技。
永留夫妻は、元呉服屋だった町家を2年もかけてリノベーション。床の間のしつらえや坪庭、部屋のランプに至るまで、ひとりずつの作家と何度も打ち合わせを重ねて仕上げていったそう。
そんな宿では、一晩過ごすだけでも京都の伝統や職人の息吹を肌で体感することができる。
例えば、洗面台に置かれた竹のコップ。こちらは御幸町錦にある竹と木のお店「ばんてら」のもの。店を運営するのは、良質な竹の産地・長岡京に工房を構える高野竹工株式会社だ。
「ガラスや陶器は危ないから、割れない素材を置こう。でも、せっかく置くなら京都の伝統文化を感じられるものがいい」。そうして見つけたのが、竹の香りと職人の技が生きたこのコップだった。
そんな小さな工芸品に宿泊客も興味を持ち、自分の家に置きたいという人もいる。「これは木なの?」と会話が始まり、そこから商品の歴史や成り立ち、職人の想いを伝えていく。

ぐい呑みや湯飲み、それを受けるお盆は、大徳寺の近くで味噌や醤油の樽などを制作する「桶屋 近藤」の商品。
部屋とバーのランプは、千本鞍馬口に工房を構える真鍮作家「Ren」の中根嶺さんが手掛けた。


テーマは「この街と繋がるきっかけを与える」。
宿に置かれた作家の作品は、宿泊客が実際に使用し、肌で感触を確かめることができる。
興味を持ってくれた人には作家の気持ちを代弁し、作品の魅力を伝える。そしてその人が、実際に作家を訪ねたりお店へ足を運べば、新たな出会いが生まれていく。
そうして宿から作り手への橋渡しをすることによって、京都という街と繋がるきっかけを与えるのがむげんのテーマだ。
置いてある作品は、その旅が日常として続いてほしいとの想いから、機能的にも価格帯的にも、手に取りやすく、生活にも取り入れやすいものを基準に選んでいる。無理強いするのではなく、旅人がこの街と繋がるきっかけを、自然と築いていけるよう心がけているという。

また、床の間のしつらえは、大徳寺の敷地内に居を構える「陶々舎」の中山福太朗さんが担当。10年以上裏千家の茶の湯を学び、教える立場にもある中山さんが、独自の考え方で日本の文化や四季を表現する。
リビングから見える坪庭と縁側に吊るされた球体ガラスは、「Re:cycle×Plants」を信条に、現代社会に適した盆栽を提案する「Re:planter」の村瀬貴昭さんが手掛けた。
実際に手に取るものだけでなく、ここに滞在するからこそ感じられる伝統や職人技が宿の随所に見てとれる。

![球体ガラスの中に盆栽を閉じ込めた[Re:planter]の作品「Space Colony」](https://story.nakagawa-masashichi.jp/wp-content/uploads/2018/09/18090648470008_2018-08-18_16-28-42_tt_6512_3.jpg)
変わることで、残していく。
歴史ある伝統は、時に柔軟に変化していくことも必要だ。
「例えば桶屋 近藤さんは、最初から桶のぐい呑みカップを作ろうとしていたわけじゃない。次の世代にも自分の技術を伝えたいから作っているんです。でも、いきなり桶を買うってすごくハードルが高い。だからぐい呑みや湯飲みをここで最初に手にすることによって、プラスチックにはない自然の香りに気付いて欲しいんです」
実際、このぐい呑みで日本酒をいただくと、木の香りがうつって樽仕込みのような味わいになるのだそう。木ならではの魅力を感じることができる。
「良いものを作っているだけじゃ生きていけないなんて、作っている人たちが一番良く知っています。それでも歴史ある伝統を背負って、それを生業にして、新しいことに挑戦しようとしている。
何で勝負するか、何を入口にするかをものすごく真剣に、未来を見据えて考えています。そんな人たちの活動に対して、むげんが少しでも多くの人へ気付きを与えてあげられたら」
そう話すあふるさんも、歴史ある建物を受け継いだ一人だ。

安政2年(1885年)築の元呉服屋だった建物は、大型で梁が太く、奥には蔵を備える典型的な商家の町家だ。冬は底冷えするイメージをもたれがちな町家だが、冬に寒いのは宿泊施設ではNG。そこで1Fのリビングや畳の部屋に床暖房を設置した。
近年は、現代の生活と町家がミスマッチを起こし、歴史ある建物が次々に取り壊されているという。しかし、本当にそうだろうか。
町家に見られる漆喰の壁は防火性にすぐれ、湿気を吸収してくれる機能もある。盆地で湿度の高い京都では、特に重要な役割を果たしている。煉瓦のかまどは絶大な火力を保ち、火袋と呼ばれる高い天井は炊事の際の熱を逃がす。入口から奥の坪庭まで通り庭が直線に伸び、風の通り道を作る。
先人の叡智が詰まった町家建築は、京都という環境に対しとても合理的に作られている。
そこに現代のテクノロジーを取り入れることで、もっと快適に使える。それを率先し、実践しているのがこのむげんという宿だ。
伝統ある建築をより使いやすくすることで、次の世代にもバトンを渡したいと考えている。

本当の意味で、「暮らすように旅する」
「暮らすように旅する」とはどういうことだろうか。
宿の周辺のことを調べそこへ出かけてみても、相手は自分の顔を知らない。あくまで自分は「観光客」だ。
「行きつけの魚屋さんがあって、お惣菜屋さんがあって、銭湯があって。そういう場所があって初めて“暮らす”という意味が生まれると思います。お客様には、私たちの普段の行きつけを旅に加えてもらうことで、より京都の日常の部分を体験してほしいと思っています」
横の繋がりが強い京都で、誰の紹介で来たかということはとても重要だ。旅行者である一見が「むげんに泊まっている」というだけで、地元客のように受け入れてもらえることもある。そうした貴重な体験も、宿と街の信頼関係があってこそ。
また最近の京都では、卸業を中心に行っていた問屋が対面販売の専門店を始める傾向が増えているという。そんな街の傾向を、あふるさんも後押ししたいと話す。
竹屋さんに竹のものだけを買いに行く、桶屋さんに桶を買いに行く。行かないといけないところは多いけれど、足を運ぶ分だけ出会いが生まれ、専門的な知識も聞ける。そんな体験もまた、暮らすように旅することの一部であり、次の日常へと繋がっていくひとつのきっかけになるのかもしれない。


旅がその先の日常へと続いていく。
屋号の「むげん」に込めた想いを、あふるさんに聞いてみた。
「ここにあるものに出会い、それを持ち帰り、日常で使うたびにむげんのことを思い出してもらえたら。この宿が、その先の日常にずっと続いていく何かのきっかけになればという願いを込めて名付けました」
決して宿だけで完結せず、宿のある街と密接に繋がる。
そこで生まれた出会いが、その先の人生においてなにか重要な意味をもたらすかもしれない。
そんな無限の可能性を秘めた旅が、この宿から始まってゆく。

<取材協力>
京旅籠 むげん
京都市上京区黒門通上長者町下ル北小大門町548-1
075-366-3206
http://kyoto-machiya-ryokan.com/
文:佐藤桂子
写真:高見尊裕