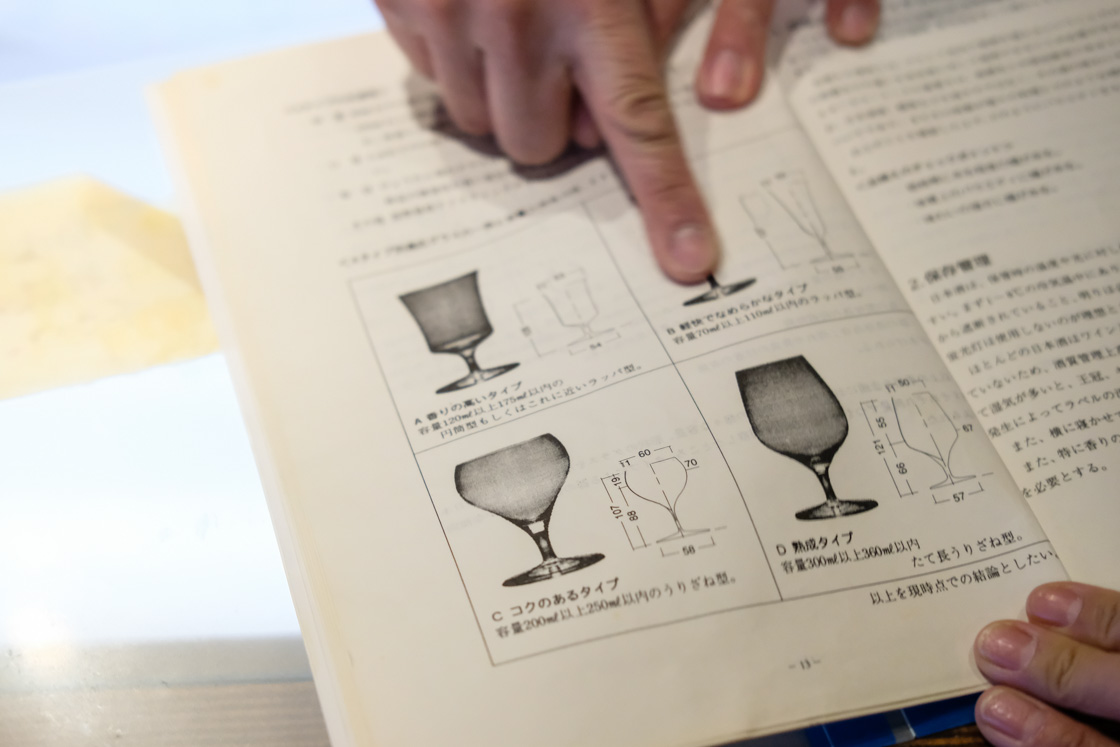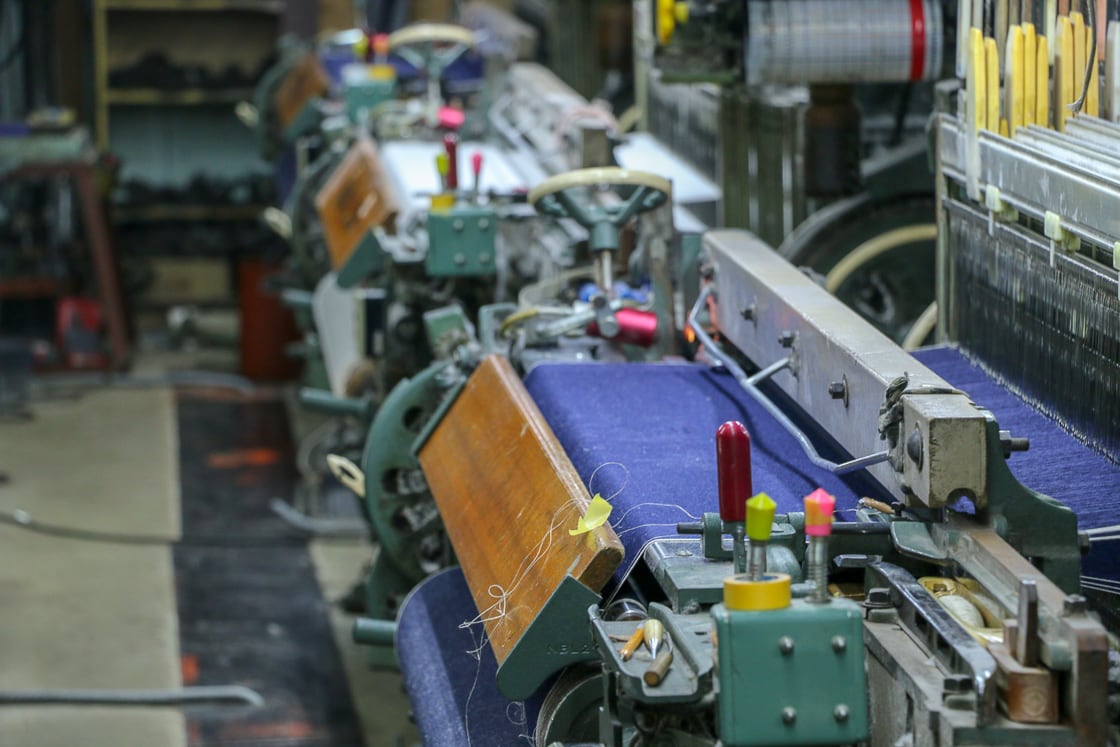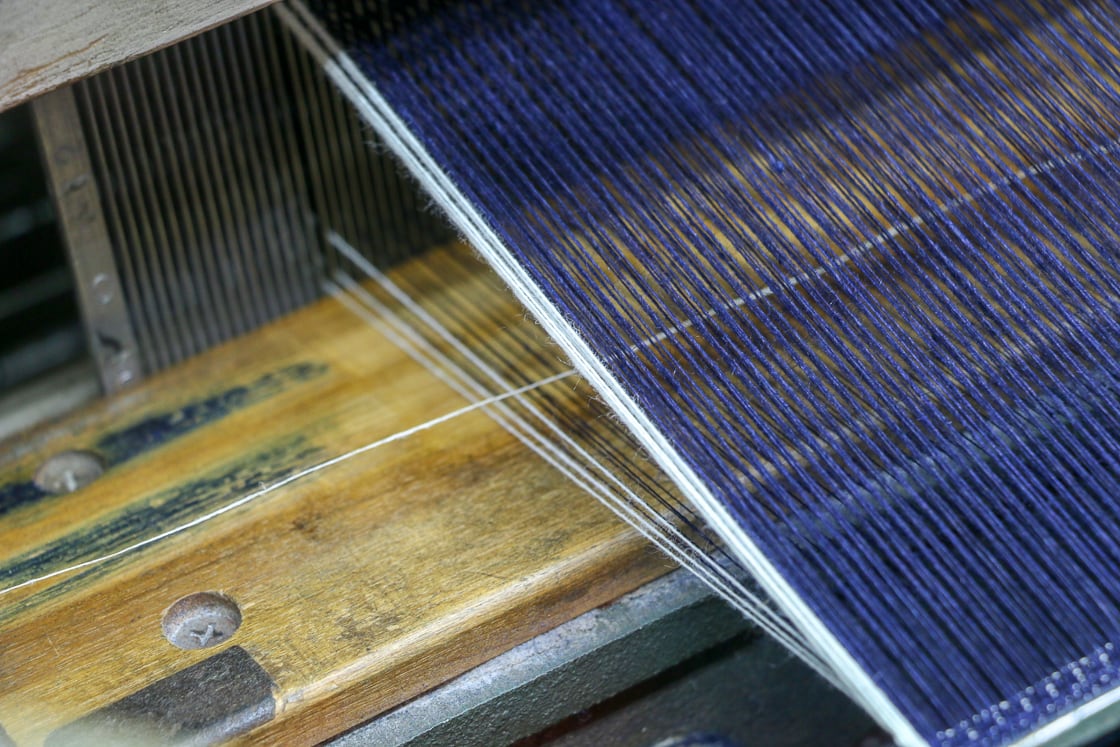全長約700メートルの「帯屋町筋商店街」。
高知中心街のシンボル的存在であり、今や全国にその名を広めた「高知よさこい祭り」の花形演舞場だ。
「もともとよさこいは、高知の商店街を盛り上げようとして始まったお祭りです。つまり、その商店街の中核である帯屋町商店街は、よさこいの歴史そのものなんですよ」
そう語るのは、岩目一郎(いわめ いちろう)さん。
66歳の岩目さんは、今年第66回を迎える「よさこい祭り」と同年代。
帯屋町筋商店街に生まれ、物心つく頃には帯屋町筋のよさこいチームに所属、青年時代には地方車(じかたしゃ:音響機材を搭載した車)に乗ってチームを牽引するようになり、当時最年少で、よさこいの運営母体である「よさこい振興会」の委員にもなった“よさこいエリート”だ。
よさこいと共に生まれ、よさこいと共に生きた岩目さんと共に、商店街と歩んだ「よさこい祭り」66年の歴史を振り返ってみよう。
その歩みには、現在の盛況からは想像もつかない苦境や閑散期を経て、高知の人々を鼓舞し続けた祭りの魅力が浮かび上がってくる。
よさこい祭り誕生のきっかけは、商店街の「夏枯れ現象」
「よさこい祭り」が誕生したのは、今から約70年前。終戦直前の大爆撃とその翌年の震災によって立て続けに甚大な被害を受けた高知市が、町に活気を取り戻そうと奮闘していた最中だった。
 県庁前から東方を望む、昭和28頃の電車通り(出典:高知市編著(1969)『高知市戦災復興史』)
県庁前から東方を望む、昭和28頃の電車通り(出典:高知市編著(1969)『高知市戦災復興史』)
「商店街はよさこい祭りの“育ての親”。会場を貸し、ルールを作り、スタッフを出し、踊り子の接待を66年続けてきた。でも、商店街だけではこの祭りを誕生させることはできなかったよ。“生みの親”は、商工会議所やね」(岩目さん)
そんな「よさこいの生みの親」高知商工会議所が、当時、大きな課題としていたのが「夏枯れ現象」だった。夏になると暑さで客足が減り、商店街の売り上げも煽りを受ける。長年その問題解消に取り組んできたものの、なかなか妙案は浮かばなかった。
そんな彼らの元に、ある「招待」が飛び込んできたのは、昭和27年のこと。お隣・徳島県からの「阿波踊りの舞台で、高知のよさこい踊りを披露してみないか」というものだった。
「よさこい踊り」は、土佐の民謡「よさこい節」に振りをつけた踊り。現在「よさこい祭り」で踊られている「よさこい鳴子踊り」のベースとなった踊りで、戦後、高知市の復興祭で披露するために作られたものだ。商工会議所は、その復興祭の主催だった。
 戦後復興祭として昭和25年(1950年)に開催された南国博の様子(画像提供:高知新聞社)
戦後復興祭として昭和25年(1950年)に開催された南国博の様子(画像提供:高知新聞社)
徳島からの招待を受けることに決めた商工会議所の面々は、昭和28年8月、踊り子隊を引き連れ、阿波踊り会場を訪れた。
その帰途の車中会議が、「阿波踊りに負けんようなものを作るしかない」と熱っぽくまとまったのは言うまでもない。
帰高後まもなく、商工会議所は夏枯れ対策として「よさこい踊り」を活用する方針を決定。この踊りを豪華にリニューアルし、それを目玉とした市民祭を開催することで、商店街へ客を呼びこもうとしたのだ。これが「よさこい祭り」誕生の第一歩であった。
祭りの立ち上げに貢献した、2人の「いごっそう」
「よさこいの立ち上げに関わった人はたくさんいるんですよ。でも、それを取りまとめ、形にしたのは、ほかでもない、浜口さんです」(岩目さん)
プロジェクトの矢面に立ったのは、料亭「濱長」の初代店主で、商工会議所観光部会のメンバーだった浜口八郎(はまぐち はちろう)さん。残念ながら逝去されているが、岩目さんがよさこい振興会の委員になった頃には、まだ現役で活躍中。「若いもんが変えなイカン」と次の世代の背中を押してくれる、おおらかな人物だったという。
 祭りの衣装を着た浜口八郎さん(画像提供:濱長)
祭りの衣装を着た浜口八郎さん(画像提供:濱長)
当時のことを、浜口さんの妻・千代子さんはこう書き記している。
正直申しまして、主人は自分の店の仕事にはそう熱心ではございませんでしたが、人さまに依頼されたり、大勢の人に喜んでもらえることになると大層力をいれました。特に高知県の観光振興には熱心で、高知市の夏の名物行事「よさこい祭り」には、高知商工会議所観光部会の役員だったこともあり、随分と力を入れておりました。(料亭「濱長」サイト内「初代女将・千代子の日記」より)
そんな浜口さんが、自分の店のお客でもあった作曲家の武政英策(たけまさ えいさく)さんを尋ね、ある依頼をしたのは昭和29年6月25日のこと。
「実は、市民の健康祈願祭になにか踊りのようなものをやりたいのだが、民衆にヒットするものを考えてみてほしい」(『よさこい20年史』より)
すでに祭りの日程は8月10日、11日に決まっており、7月1日から練習を始めたいと言う。つまり、わずか5日間で曲と歌詞を作ってほしいという依頼である。武政さんは「まことにムチャな話」と驚きつつも依頼を引き受け、その晩からさっそく制作にとりかかった。
 作曲家の武政英策さん(画像提供:森田繁広さん / 『よさこい祭り60年史』より引用)
作曲家の武政英策さん(画像提供:森田繁広さん / 『よさこい祭り60年史』より引用)
伝統ある阿波踊りに対抗するには素手ではだめだ…、思い付いたのが鳴子。「年にお米が二度とれる土佐において、何かやると言えば、鳴子は最高の圧巻だ。これなら阿波踊りに対抗できる。」(『よさこい20年史』より 武政英策さんの手記)
武政氏が思いついたのは、田畑の「すずめ脅し」として使われていた鳴子(なるこ)を、稲の二期作地帯である高知をイメージした打ち物として利用すること。そうして誕生したのが、現在の踊りのベースとなっている「よさこい鳴子踊り」だ。
よっちょれよ よっちょれよ よっちょれよっちょれよっちょれよ
高知の城下へ来てみいや じんまもばんばもよう踊る
鳴子両手によう踊る よう踊る
土佐の(ヨイヤサノサノサノ)高知の はりまや橋で
坊さんかんざし 買うを見た よさこい よさこい
武政さんは、歌詞の着想を『よさこい節』『土佐わらべ歌』『郵便さん走りゃんせ』などの土佐の民謡から得たことをのちに明らかにしている。
「「郵便さん走りゃんせ」の中に「いだてん飛脚だ、ヨッチョレヨ」というのがある。私は、このヨッチョレの言葉が楽しくてたまらない。また、よさこい祭りというからには、昔から伝わる「よさこい節」も入れた方がよいだろう」(『よさこい20年史』 武政英策さんの手記「鳴子踊りの誕生」より)
 振り付けに難航した、よさこい祭り草創期の鳴子踊り(画像提供:高知新聞社)
振り付けに難航した、よさこい祭り草創期の鳴子踊り(画像提供:高知新聞社)
曲と歌詞が完成したら、残るは踊りである。
浜口さんが次に声をかけたのは、日本舞踊の五流派の師匠たち。のちに争いを生まないように、特定の流派への依頼を避けたのだ。
浜口さんも同席の上で制作を始めたものの、振り付けは難航した。お師匠さんたちの振り付けは、回ったり、後ろへ下がったりと、どうしても優雅な舞台踊りになってしまう。しかし、よさこいは街頭での踊りを想定していたため、前へ前へと進む踊りでなければならなかった。
「それは徳島の阿波踊りなど、先進地の視察も十分したうえでのことでしたが、専門家の振り付けを無視するわけにもいかず、あでやかなお師匠さんたちの中に入って、ああでもない、こうでもない、と注文を付けておりました」(料亭「濱長」サイト内「初代女将・千代子の日記」より)
しかし、そうしている間にも祭りの日はだんだんと近づいてくる。そこで、一回目は仕方がない、と手を打ったのが「三歩進んで、くるりと回り、一歩下がってチョン」という型だった。
 市役所前の本部審査場。左手に四国電力旧社屋、向こうに県民ホールが見える(画像提供:高知新聞社)
市役所前の本部審査場。左手に四国電力旧社屋、向こうに県民ホールが見える(画像提供:高知新聞社)
こうして、昭和29年8月10日・11日、第1回目の「よさこい祭り」が開催された。
水上ショーや酒の振る舞い、郷土芸能などの出し物も話題を呼び、狙い通りの大盛況。翌日の新聞紙面には「人出八万」という言葉が踊った。
初期のよさこいを支えたテレビ中継
 昭和31年開催、第3回よさこい祭りにて、追手門内特別舞台につめかけた観衆(画像提供:高知新聞社)
昭和31年開催、第3回よさこい祭りにて、追手門内特別舞台につめかけた観衆(画像提供:高知新聞社)
ほとんど娯楽がない時代に珍しい参加型のお祭りとあって、「よさこい祭り」はあっという間に市民に受け入れられた。期間中は商店街に人がごった返し、老いも若きも大盛況だった。
「顔は知ってるけど普段は交流のないおっちゃんとかも、祭りの日には気さくに話しかけてきてね。もうみんな酒飲んで酔っ払ってるから『おいボウズ! つまみ食うか!』という感じで絡んでくるんですよ」(岩目さん)
しかしそれも、祭りが始まって数年のうちだけだった。
次第に飽きがきたのだろうか、参加者も参加チームもどんどん少なくなり、ついには踊り子に日当が出る始末。岩目さんも、幼少期には「プラモデルの引換券目当てに踊った」と記憶しているそうだ。
 昭和34年・第6回の祭り時には、市役所前で踊りの中継がされた(画像提供:高知新聞社)
昭和34年・第6回の祭り時には、市役所前で踊りの中継がされた(画像提供:高知新聞社)
そんな、初期のよさこい低迷期の救世主となったのは、当時、県内唯一の民放テレビであった「ラジオ高知テレビ」。昭和34年(第6回)から、祭りの生放送をすることになったのだ。
当時は、テレビに自分の姿が映ることが特別で、画面に見切れるだけでも大騒ぎする時代。その効果は絶大で、祭り当日、中継会場である市役所広場には、例年の何倍もの参加者が押しかけたという。
放送時間が残り少なくなって来ると、参加各団体の代表者はけんか腰。終いには司会者の胸ぐらをつかんで「もし自分たちの団体が放送に出なかったら、俺は町内におられなくなる。どうしてくれるか」などと詰め寄られてこづき回された。(『よさこい20年史』元本部舞台司会者・RKCプロダクション社長 武内清氏の手記「司会者とテレビ中継」より)
結局、30分を予定していた放送時間を延長し、47団体、2千5百余人が参加、午後1時から4時までの丸3時間という長時間の生中継になった。その日、家庭のテレビや電気店のテレビの前は、近所の人々や通行人が群がって、「だれやろさんが映っちゅう!」と大騒ぎだったという。
自由化を加速させた「ニースのカーニバル」
 祭り期間は気温30度超えの暑さ。踊るのも見るのも体力が必要(画像提供:高知新聞社)
祭り期間は気温30度超えの暑さ。踊るのも見るのも体力が必要(画像提供:高知新聞社)
しかし、5年ほどするとテレビ中継も当たり前になり、逆に「家でも見られるから」と観客の数は減っていった。祭りの時期は気温30度を軽く超える猛烈な暑さで、見物も大変。しかも当時は全チームが同じ踊りを踊っていたため、見る方も飽きてしまうのだ。
そんな「よさこい祭り」に、第二の転機が訪れたのは、昭和46年のこと。
フランスのニース市で開催されるカーニバルに「よさこい鳴子踊り」が招待されたのだ。カーニバルには、日本びいきのニース市長の招待で、よさこい鳴子踊りのほか、新潟県の「佐渡おけさ」、山形県の「花笠踊り」、岩手県の「鬼けんまい」が参加するという。
初めての海外遠征に、関係者たちは期待と不安でざわめいた。そこへ、ある「声」をあげた人物がいた。「よさこい鳴子踊り」を生んだ、作曲家の武政英策さんだ。
実は武政さん、当初の踊りは自分の作った曲とイメージが合わず、フラストレーションを抱えていたのである。
「今のままの踊りでは、ニースの人たちに、ほかの踊りとは違うよさこいの魅力を伝えることはできないのではないか」
武政さんは、これを機会に「よさこい鳴子踊り」を、海外の人たちにも楽しんでもらえるよう、サンバのリズムに編曲することにした。
振り付けを務めたのは、若柳流・荒谷深雪師匠。若くて元気いっぱいな踊り娘のひとりだった。諸先輩方からの「日舞の師範が西洋のダンスの振り付けをするなんて!」という批難にもめげず、「受けた仕事は誰に何を言われてもやりきる」と、破門も覚悟でニースに乗り込んだ。
 当時の様子を語る岩目一郎さん
当時の様子を語る岩目一郎さん
昭和47年2月。カーニバル会場に到着したのは、31名の踊り子隊。
フランス国旗にちなんだ、青、白、ピンクの法被の背には、赤い日の丸に「土佐」の文字が誇らしげに染め抜かれていた。
サンバのリズムは、武政さんの予想通り、フランスの人々を夢中にさせた。「ジャパニーズダンス、リズミカル、ベリービューティフル!」と人々は大歓声を上げ、踊り子たちに向かってところかまわず紙吹雪を投げつけたという。
新聞やテレビはその成果を大きく取り上げ、それを見た人たちもまた「よさこいが世界に認められた!」と、何日間もこの話題で盛り上がった。
「ニースから凱旋した踊り子隊は、まさに高知の大スターといった扱いでした。このあたりから、よさこいが市民の祭りから県民の祭りへと変化してきたように思います」(岩目さん)
「よさこいに人生賭ける」と思えた、“青果の堀田の衝撃”
 今では禁止となっている、大型トレーラーを使った地方車(画像提供:高知新聞社)
今では禁止となっている、大型トレーラーを使った地方車(画像提供:高知新聞社)
当時、岩目さんが所属していた帯屋町筋踊り子隊は、資金力もあり、踊り子は300人以上(当時はまだ人数制限がなかった)、地方車も20トントレーラーを使用するなど、ほかを圧倒する巨大チーム。チーム内のポジションも上り詰めていた岩目さんは、そのときまさに「よさこいは自分のための祭り」状態だったという。
そんな岩目さんを驚かせる事件が起きたのは、昭和48年(第20回)。
2年連続でニース・カーニバルによさこい鳴子踊りが招待され、県全体のよさこいへの注目度が上がっていた頃のことだった。
「僕らのチームのひとつ前が、『青果の堀田』チームやったんです。代表の堀田イクは小学校の同級生でした。彼らは2トンくらいのちっちゃな車に5〜60人程度の踊り子、僕らは20トンのトレーラーに300人の踊り子で、そのときは正直彼らのことバカにしとりましたね」(岩目さん)
しかし、「青果の堀田」の音楽がスタートした瞬間、その場にいた人たちは皆、凍りついた。それまでのよさこいは、アレンジといっても整列して振りを合わせるマスゲームである点は変わらなかった。しかし、彼らは、音楽……というよりも、生バンドが演奏する、曲の「ビート」に合わせて、自由に飛んだり跳ねたりしたという。
 「青果の堀田」の衝撃以降、生バンド演奏をするチームが急増した(画像提供:高知新聞社)
「青果の堀田」の衝撃以降、生バンド演奏をするチームが急増した(画像提供:高知新聞社)
代表の堀田イクさんと音楽担当のジュリアン(通称)は、ニースのカーニバルに参加した踊り子の一員だった。その経験を共有し恋仲となった2人は、現地で感じた熱と興奮を持ち帰り、自分たちの踊りで表現したのだ。
「その表情、迫力たるや、ものすごいエネルギーでしたね。思わず見惚れてしまった。そしたら『ピピー!』と笛が鳴って『帯屋町さん、次! 出番です!』って言われて。正気に戻って『おうみんな! 行くぞ!』って振り向いたら、誰もおらんがです。踊り子たちはみんな、堀田の踊りを追っていってしまったんですよ」(岩目さん)
そのときから岩目さんは「よさこいに人生を賭けてもいい」と思うようになったという。悔しさ以上に、アイデアだけでいくらでも人を惹きつけることができる、よさこいの「可能性」を感じたのだ。
交通渋滞、騒音問題、チーム間トラブル…沸き起こる問題の数々
 踊りも衣装も、どんどん自由に変化を遂げる「よさこい祭り」(画像提供:高知新聞社)
踊りも衣装も、どんどん自由に変化を遂げる「よさこい祭り」(画像提供:高知新聞社)
「ニース以降、サンバやロックなどいろいろなリズムが登場するようになり、それぞれの連(チーム)がより自由に個性を出すようになったんです。よさこいを自由にアレンジできる! と若者に火がついたね」(岩目さん)
しかし、隆盛と共に、当然さまざまな問題も現れてくる。
昭和54年(第26回)には、多様化の一途をたどる踊りのスタイルや音楽に、関係者だけでなく市民からも活発な賛否両論が出るようになった。高知新聞の「読者の広場」欄では、両論が「激突」の形で展開される状態だった。
昭和61年(第33回)には、伴奏音楽の「ボリューム合戦」について、「祭りだから良いのでは」という意見と「いくら祭りでも行き過ぎ」との声がぶつかり合った。
そのほかにも、交通渋滞や若者のモラル、チームの資金事情やトラブルなど、当時すでに振興会の委員として活躍していた岩目さんのもとには、さまざまな訴えが届いていたという。
そしてついに、昭和63年(第35回)、事件が起こる。
祭りのムードが最高潮となった、最終日の夜のこと。踊り子たちはいずれも汗にまみれ、興奮し切った表情をしていた。個人賞のメダルを胸に、片肌脱ぎになった女性の踊り子もいた。
そこへ、冷めやらぬ熱を抱えた踊り子の一部が、帯屋町商店街へと流れ込んだ。
地方車まで参加して、音楽のボリュームを上げ、再び踊りはじめたのである。そのときすでに夜10時過ぎ。しかし、その盛り上がりは止まらぬどころか、別の踊り子たちが次々と合流。総勢600人余りとなり、さながら野外ディスコの状態となったのだ。
たまりかねた一般市民の通報で警察の出動となったが、興奮の極みにある踊り子たちの一部は説得を聞き入れなかった。やむなく警察が地方車を強制的に引き離すなどして夜半近くにやっと収めたという。
 平成元年7月29日放送、RKC高知放送のオールナイト公開番組『朝まで討論!どうする?よさこい祭り』収録風景(画像提供:高知新聞社)
平成元年7月29日放送、RKC高知放送のオールナイト公開番組『朝まで討論!どうする?よさこい祭り』収録風景(画像提供:高知新聞社)
そのころ、深夜から朝6時まで徹して語る、よさこい祭りの生討論番組が放送された。ゲストは、高知市やよさこい振興会、競演場の代表、警察など。そこに帯屋町代表として岩目さんも参加していた。
どの議題も「良い・悪い」の大激論。結論はまとまらなかったものの、この番組以後、祭りの問題に対して人々の意識は高くなっていった。改善策を考える上で、「規制」を求める声は次第に大きくなる。
「でもね、よさこいの一番の魅力である根幹の『自由さ』を奪っちゃいけないと思ったんですよ。だから、僕からは『規制じゃなくて、リーダーを作ろう』と。要するに、みんなの手本となるチームをこちらから提示して、自覚を促そうと提案したんです。それが『よさこいグランプリ』誕生のきっかけとなりました」(岩目さん)
よさこい祭り、最大の転機「セントラルグループ」の登場
実は、高知の人に「よさこいの転換期はいつ?」と聞くと、ほぼ全員の口から出るキーワードがある。それが「セントラルグループの出現」。
それは奇しくも、岩目さんが提唱した「よさこいグランプリ」が開始された平成3年(第38回)のできごとだった。
「手本となるリーダーを選出するのに、祭りが終わったタイミングでは意味がない。祭りの前日に『前夜祭』を設け、そこでグランプリを選出しよう!」
第一回よさこいグランプリは、本祭前日の8月9日に開催される前夜祭にて幕をあけた。舞台は中央公園。よさこいは街頭踊りがメインだったが、「正面から見る踊りを楽しんでほしい」との意図もあり、ステージを設け、その上で踊りを披露する形になった。
 前夜祭のステージで乱舞する踊り子たち(画像提供:高知新聞社)
前夜祭のステージで乱舞する踊り子たち(画像提供:高知新聞社)
踊り子たちは舞台上で次々と自慢の踊りを披露し、観客は「どのチームがグランプリに相応しいか」について熱っぽく語り合った。しかし、高知を中心とした総合エンターテインメント企業「セントラルグループ」の踊り子隊 総勢150名が構えをとり、音楽が鳴った瞬間、そのすべてがひっくり返った。
当日、司会役を務めていた岩目さんは、そのときのことを鮮明に覚えているという。
「鳥肌が立ったよね。今までとはまるで違うものだったのよ」(岩目さん)
これまでの踊りは、躍動感すらあれ、ぐるぐる回ったり跳ねたりを繰り返す「動き」を楽しむものだった。しかし、セントラルグループは「動き」に加えて、踊りで「物語」を表現したのだ。4分30秒のなかに、起承転結があり、静と動、明と暗が共存していた。
「すべてのグループが踊り終わったら、投票でグランプリを決めるんです。でも、どの票を開けても『セントラル』。1位と2位の票差が凄まじかった。誰が見ても圧倒的、圧勝やったんです」
 平成9年・第44回よさこい祭りにて、恒例となった前夜祭の様子(画像提供:高知新聞社)
平成9年・第44回よさこい祭りにて、恒例となった前夜祭の様子(画像提供:高知新聞社)
かくして、「前夜祭でグランプリを決定し、踊り子たちの手本となるようなグループを選出しよう」との振興会側の狙いは、予想外の形での達成を遂げた。
その他の取り組みも功を奏したのはもちろんだが、この衝撃的なセントラルグループのデビューによって、よさこいが刹那的な楽しみやお金儲けの手段ではなく、「作品作り」へと変化したのだ。
そして、翌平成4年(第39回)、セントラルグループの踊りに魅せられたひとりの青年が北海道で始めたのが、よさこいを全国に広めるきっかけとなった「YOSAKOIソーラン」なのである。
そして、歴史は繋がれていく
「みんな、もっとキレッキレで踊って!!!!」
そんな怒号が響くのは、2018年7月の帯屋町筋商店街アーケード。一ヶ月後に控えた「よさこい祭り」に向かって、帯屋町筋のよさこいチームが練習をしていた。
現在の帯屋町筋よさこいチームのメンバーは、全部で130名ほど。8割以上がリピーターで、中には20年、30年と、このチームで踊り続けているメンバーもいるそうだ。市内からの参加がほとんどであるが、ここ十数年で随分と県外からの参加も増え、130名中30名ほどが県外メンバーだという。
最近では、よさこいのために移住する人も増え、「よさこい移住」という言葉まで誕生しているらしい。
帯屋町筋の踊り指導を務める清水美優(しみず みゆ)さんは、2017年4月、群馬から「よさこい移住」をしてきた。幼い頃に通っていたバレエ教室の縁で、年に一度、高知に来てはよさこいを踊り、気づけば虜になっていたという。
「踊っていると、お客さんがうちわであおいでくれたり、『頑張れ!』と声援をくれたりする。よさこいは、踊り子も観客も、それぞれのチームも、参加者みんなが一丸となって作り上げるお祭りだと感じます。そこがたまらなく好きなんです」
第66回となる今年、参加チームは合計207。県内が136チームで、県外が71チームだ。海外からは、ポーランドなど世界18の国や地域から集まる「高知県よさこいアンバサダー絆国際チーム」が参加する。本場高知の舞台で踊りたいというチームの数は年々増加の一途をたどり、振興会側も苦渋の決断で数を制限しているほどだという。
岩目さんは、変化を続けるよさこいについてこう語る。
「もともと商業祭として誕生したよさこい祭りは『神なき祭り』。つまり、時代と共に生きていくお祭りなんです。トレンドと共に、その時代の人間が作り上げていく、それこそがよさこいの真髄であり、今、全国の人が熱狂する理由なんじゃないでしょうか」(岩目さん)
神仏に奉納する踊りではないからこそ、「よさこい」は市民の変化と共に、柔軟にその形を変えてきた。歴史を振り返ると、まさにその「自由さ」こそが、高知から全国へ、そして世界へと拡がるよさこいのうねりを生み出したのだということが分かる。
最後に、「よさこい鳴子踊り」の作曲者・武政英策さんが予言のように記していた言葉で終わりたいと思う。よさこいがこんなにも自由な変化を遂げ、世界の「YOSAKOI」となることを誰も想像していなかった時代に書かれたものだ。
「郷土芸能は民衆の心の躍動である。誰の誰べえが作ったかわからないものが、忘れられたり、まちがったりしながら、しだいに角がとれシンプル化していくものである。要は、民衆の心の中に受け入れられるかどうかが問題で、よさこい鳴子踊りにしても、時代や人によって変わってきたし、これからもどんなに変わっていってもかまわないと思っている」(『よさこい20年史』より 武政英策さんの手記)
 平成19年・第65回よさこい祭りにて、帯屋町筋演舞場での帯屋町筋よさこいチームの演舞(画像提供:高知新聞社)
平成19年・第65回よさこい祭りにて、帯屋町筋演舞場での帯屋町筋よさこいチームの演舞(画像提供:高知新聞社)
<参考文献>
よさこい祭り振興会(昭和48年)『よさこい祭り20年史』
よさこい祭振興会(平成6年)『よさこい祭り40年』
よさこい祭振興会(平成16年)『よさこい祭り50年』
よさこい祭振興会(平成27年)『よさこい祭り60年』
岩井正浩(2006年)『いごっそハチキンたちの夏』岩田書院
高知新聞 連載『よさこいの「かたち」』
文:坂口ナオ
写真:二條七海




























 『くいもんや ふるさと』は地元客にも観光客にも親しまれる居酒屋
『くいもんや ふるさと』は地元客にも観光客にも親しまれる居酒屋