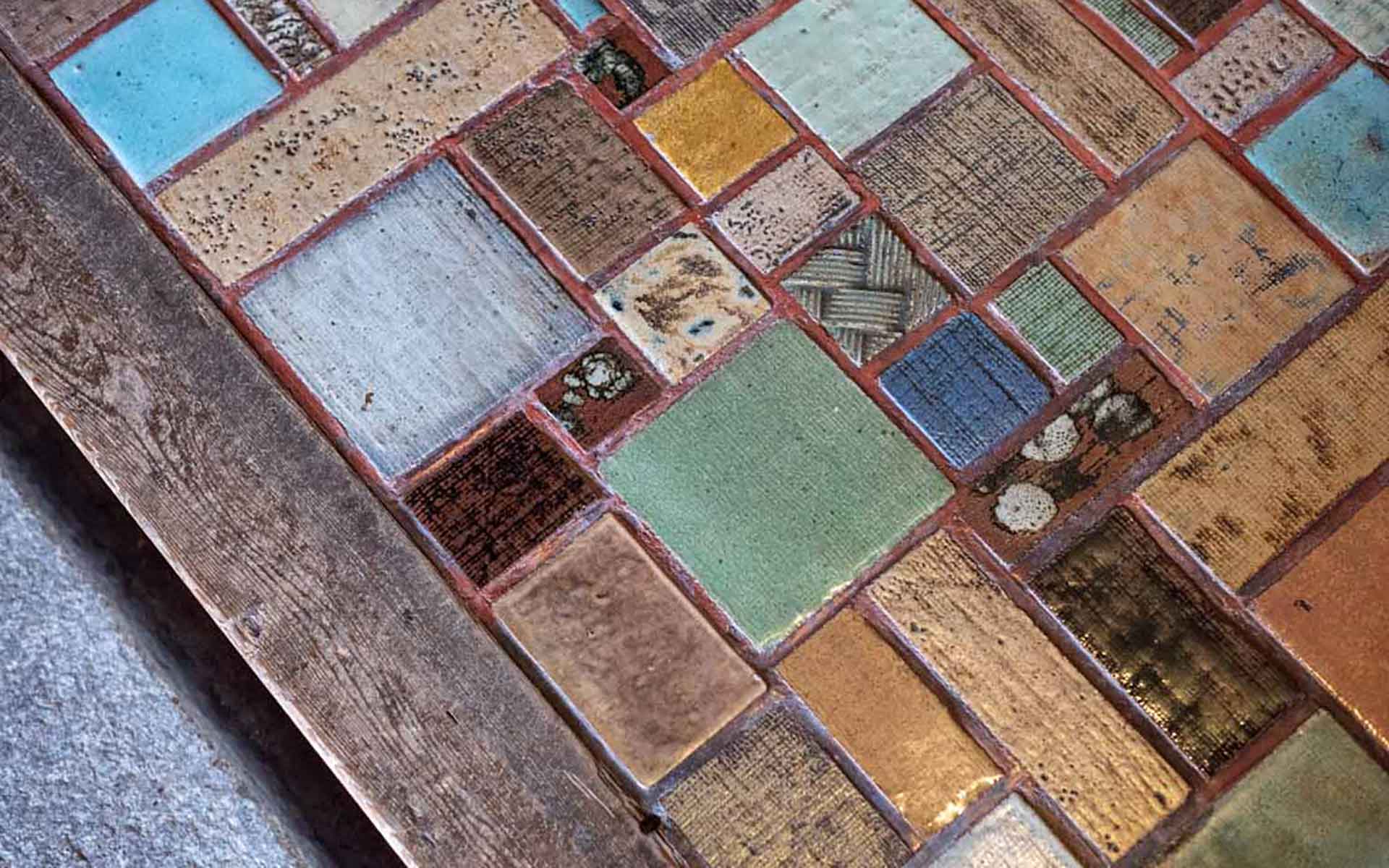こんにちは。THEの米津雄介と申します。
THE(ザ)は、ものづくりの会社です。漆のお椀から電動自転車まで、あらゆる分野の商品をそのジャンルの専業メーカーと共同開発しています。
例えば、THE ジーンズといえば多くの人がLevi’s 501を連想するはずです。「THE〇〇=これぞ〇〇」といった、そのジャンルのど真ん中に位置する製品を探求しています。
ここでいう「ど真ん中」とは、様々なデザインの製品があるなかで、それらを選ぶときに基準となるべきものです。それがあることで他の製品も進化していくようなゼロ地点から、本来在るべきスタンダードはどこなのか?を考えています。
連載企画「デザインのゼロ地点」、今回のお題は「折り畳み傘」です。
梅雨の時期には欠かせない傘。
僕は手に何かを持って歩くのが好きではないのでレインウエア派だったのですが、ここ数年は折り畳み傘を持ち歩いています。
今回は、傘嫌いだった僕が常に持ち歩くに至った傘のデザインの進化をご紹介いたします。
洋傘・和傘・頭にかぶる笠などの歴史に伴う形状の違いや、雨傘・日傘などの用途や機能・素材の違いなど、話が多岐に渡ってしまいますが、可能な範囲で雨傘に焦点絞りつつ、折り畳み傘のデザインのお話ができたらと思います。
神具から生まれた「傘」の歴史
傘を使っていたという世界最古の記録は約4000年前のエジプトやペルシャ。
祭礼のときに神の威光を表するものとして神像の上にかざしていたそうです。
 wikipedia参照
wikipedia参照
一般的に使われだした古代ギリシャでは日傘として従者に持たせるものでした。
東洋でも道具としての目的は主に魔除け。ヨーロッパでも富と権力の象徴であり、用途は日傘が主だったそうです。
 wikipedia参照
wikipedia参照
出自が神具や日傘だったのは少し意外ですね。他の用途はあれど、雨を避けるために生まれたものだと思っていました。
そして、18世紀頃にイギリスで現在の傘に近い構造のものが生まれていますが、やはり当初は女性の日傘。男性は帽子で雨を避けるのが一般的だったようで、男性が雨傘を使うということはファッション的にも相当に変わったことだったようです。19世紀近くなってやっと少しずつ男性が雨傘を使うことに抵抗がなくなってきたとのことです。
世界的にも早い段階で「雨傘」を使っていた日本人
一方日本では、欽明天皇(509年〜571年頃)の時代に朝鮮半島から和傘に近いものが伝わったそうです。
開閉ができるものではなかったようですが、平安時代に製紙技術の進歩や竹細工の技術を取り込んで改良され、平安時代末期から鎌倉時代初期の「鳥獣戯画」にも、雨を避けるためにカエルが蓮の葉を傘のように持っている姿が見られます。
 「鳥獣戯画」東京国立博物館像 提供:東京国立博物館
「鳥獣戯画」東京国立博物館像 提供:東京国立博物館
さらに、鎌倉時代の「一遍聖絵」という絵巻物には、頭にかぶる笠と雨傘の両方が描かれています。しかも画像左下には畳まれた傘が描かれていて、この頃には既に親骨と小骨で構成された番傘の原型が存在していたことがわかります。
 「一遍聖絵」国立国会図書館像 提供:国立国会図書館ウェブサイト
「一遍聖絵」国立国会図書館像 提供:国立国会図書館ウェブサイト
室町時代には和紙に油を塗布する事で防水性を持たせ、現在と同じ用途で広く使用されるようになりました。
それと共に傘を専門に製作する傘張り職人が登場し、さらに江戸時代になると分業制が発達したことでより広く普及するようになったとのことです。
 京和傘 wikipedia参照
京和傘 wikipedia参照
つまり、日本人は世界的に見てもかなり早い段階で雨傘を使っていたことになります。
ちなみに、世界の主要都市の多くは日本と同緯度圏内にありますが、その中でも日本は圧倒的に降雨量が多い国です。海に囲まれ、急峻な山地があり、水流が速く、山地全体の保水量が多い。
おかげで緑が多く地形のバリエーションも豊かで、自然の恩恵を多大に受けている国だと思うのですが、湿度が高く衣類が乾燥しにくいため、濡れることを嫌う人が多いそうです。
1人あたりの傘の所持数でも日本は世界1位(日本3.3本・世界平均2.4本)、1本の傘にかけるお金も世界平均の1.8倍(日本約22ドル・世界平均12ドル)と、日本人と傘は関係が深いことが伺えます。(weather news調査・n=38,603)
では現在使われている雨傘としての洋傘はいつから日本に根付いたのでしょうか?
日本最古の洋傘の輸入記録は江戸後期の1804年(文化元年)。
長崎に入港した中国からの唐船の舶載品目の中に「黄どんす傘一本」との記述が見られます。これが現在、洋傘として特定できる最古の記録とされるものです。
それから程なくして多くの日本人が洋傘を目にしたのは1853年の黒船来航でした。上陸した水兵たちが洋傘をさす様が多くの野次馬の目に触れ、数年後の1859年(安政6年)には本格的に輸入されることになります。
ただ、江戸時代には洋傘はまだまだ高級な舶来品で、一般市民の手に渡ることはなかなかなかったそうです。
そしてついに明治に入ると洋傘の国内生産が始まります。明治18年に国として特許制度が導入されますが、明治23年には「蝙蝠傘・自動開」という特許登録がされています。
国産品が生まれたことでコストが下がり、明治~大正にかけて一気に庶民の手に行き渡ります。明治後期には日本から海外への主要輸出品目にまでなっていたそうです。
 明治時代の傘広告 wikipedia参照
明治時代の傘広告 wikipedia参照
折り畳み傘の登場
さて、やっと「折り畳み傘」の登場です。
少し時間が飛びますが、折り畳み傘は1928年にドイツのハンス・ハウプト氏の考案によって世の中に生まれました。同年に特許を取得し、その特許をもとにKnirps社(クニルプス社)が製造・販売を開始します。
日本でも1950年前後にいくつかのメーカーが折りたたみ傘を開発しています。
中でも、1954年に開発されたアイデアル社(旧・丸定商店)のスプリング式折り畳み傘は、1回の動作で開閉ができることや植木等さん出演のCMによって国内で爆発的にヒットしました。1960年代の洋傘市場は年間2500万〜3200万本ほど(ちなみに現在1億3000万本)。当時アイデアル社は市場の3割以上のシェアを占めていたそうです。
その後も、機構によるコンパクト性能や耐風性(耐久性)など、日本人お得意のブラッシュアップが次々と成されていきます。
1965年には従来二段折り式だったものを三段折り式に改良、加えて真鍮だった素材はアルミ合金に、ナイロン生地から国産化に成功したポリエステル生地への改良など、今日の傘生産の基礎が作られていきました。
高度経済成長と同時にどんどん進化を遂げた日本の折り畳み傘ですが、機構や材質の劇的な変化は現在では生まれにくくなっていると思います。
これは他の製品にも当てはまることですが、昭和の時代には次々に新素材や新技術が生まれ、それが「みんなが求める進化」である確率が高かった、つまり材料から加工まで、工学や化学分野の進化がわかりやすく生活に直結する時代でした。
一方で現在では「生活に直結するわかりやすい進化」はなかなか生まれにくくなっています。
ただ、技術の進化だけが製品開発やデザインの拠り所ではありません。例えば環境が変わればそれに伴う道具にも変化が訪れます。
超軽量折り畳み傘
折り畳み傘の話に戻りますが、僕がここ数年使っているのは「超軽量折り畳み傘」です。
なんだそんなことか・・と思うかもしれませんが、ここに開発やデザインにおける取捨選択の大事な要素が詰まっていると思うのです。
この超軽量折り畳み傘は何社かで発売されているのですが、本当に驚くくらい軽い。
86gのものを使っていますが、現行のiPhone Xが174gなので半分以下の重量。カバンに入っていることを忘れてしまうほどの軽さです。
もちろんレインウエアよりも小さくて軽いので重宝しています。
一方で軽さ以外の面で製品としてどうかというと、広げた大きさは50cmとかなり小さめ(一般的な傘は60cmが多い)で、堅牢性や耐久性という側面から見ても「本当に大丈夫?」と思ってしまう少し華奢な作りです。
ただ、実際に毎日持ち歩いてみて思ったのは、雨の中を長時間歩く機会の少なさです。そもそも都市部は屋根のあるところが多く、僕が物心ついたこの30年くらいでも、交通インフラはかなり整備されました。また、地方でも車移動が多く、長時間雨にさらされながら歩くという機会はかなり減っています。
広げた時には小ぶりで少し華奢な作りのこの傘は、暴風雨の中で使えるようなものではありませんが、もともと折り畳み傘は「もしかしたら降るかも・・」といった場合の保険に近いものだと考えると、軽さに重きをおくのは理にかなっています。
天気予報の精度向上や軽自動車の普及、そして都市インフラの整備など、超軽量折り畳み傘は、技術の進化よりも環境の変化で生まれた側面が強いプロダクトと言えそうです。(もちろん軽量化のための材質改良はありますが)
 KIU AIR-LIGHT UMBRELLA ¥3,240(税込)
KIU AIR-LIGHT UMBRELLA ¥3,240(税込)
5本骨で軽量化を図り90g。UVカット率は色によって変わりますが、80〜90%以上ですので日傘としても使えます。
 mont-bell トラベルアンブレラ ¥5,616(税込)
mont-bell トラベルアンブレラ ¥5,616(税込)
6本骨で86g。7デニールという極薄で撥水性能の高い生地で繊維の保水を防ぎます。
ちなみに、上記の超軽量折り畳み傘はどちらも二段折り式で、折り畳んだときの長さが21〜23cmくらいになります。三段折り式であれば15cmくらいにはなりそうですが、実は三段折り式には折り畳んだときに濡れている側が表にきてしまう、というデメリットがあります。
単純に強度不足や重量増、そしてコストといった問題で二段折り式になっているのかもしれませんが、機能のバランスとしても最良の選択だと思います。
技術がある程度成熟した中で生まれた「良い塩梅」な製品たち。
生活環境の変化に伴ってデザインのゼロ地点も緩やかに進化していくのだと思います。
デザインのゼロ地点「折り畳み傘」編、如何でしたでしょうか?
次回もまた身近な製品を題材にゼロ地点を探ってみたいと思います。
米津雄介
プロダクトマネージャー/経営者
THE株式会社 代表取締役
http://the-web.co.jp
大学卒業後、プラス株式会社にて文房具の商品開発とマーケティングに従事。
2012年にプロダクトマネージャーとしてTHEに参画し、全国のメーカーを回りながら、商品開発・流通施策・生産管理・品質管理などプロダクトマネジメント全般と事業計画を担当。
2015年3月に代表取締役社長に就任。共著に「デザインの誤解」(祥伝社)。
※こちらは、2018年6月26日の記事を再編集して公開しました。良い塩梅な折り畳み傘を持ち歩いて、梅雨の時期も快適に過ごしたいですね。