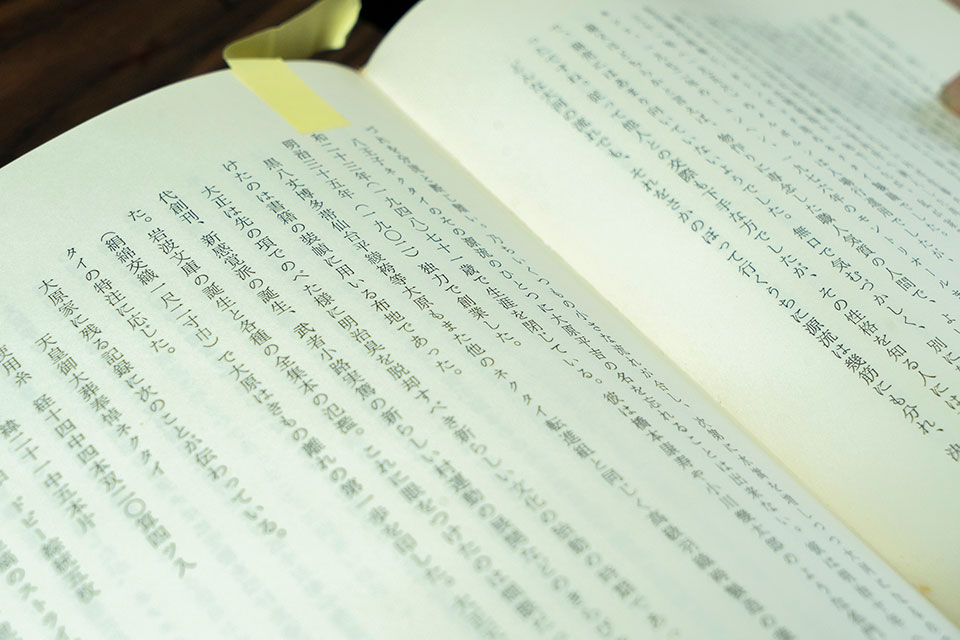溝がないのに食材がすれる、不思議なすりバチ
普段、休日はなるべく僕が料理を担当するようにしています。
料理をするのは好きで、本やネットでレシピを見ていろいろチャレンジをしています。時間に余裕があるときはちょっと手の凝ったことをしたくなって、いろんな道具を使うこともあります。

僕はゴマが好きなのですが、すりゴマを食べるなら自分ですりたい派です。
市販のすりゴマを使えば楽で何より時短になりますが、すっているときに段々と漂ってくるゴマの香りが好きで・・・。
しかし、一般的なすりバチは溝にゴマが詰まりやすくてきれいにゴマが取れず勿体ない気がしていました。
それにゴマをするだけの道具となり、洗い物が余分に増えてしまう・・・。中々積極的に使用できませんでした。
そんな悲しい現実を解決してくれたのが「かもしか道具店 すりバチ」です!

このすりバチ、本当にすれるのか?と思うくらい溝がありません。
手で触るとよくわかるのですが、非常にザラザラな表面に仕上がっています。
このザラザラした焼き締めの土肌が溝の役目を果たしてくれて、見事にゴマをすることができるのです。
これなら溝にゴマが詰まる心配もいりません。

それに、見た目も落ち着いた雰囲気で、自然と食卓に馴染んでくれます。僕は黒を選びましたが、どの色も食卓に馴染んでくれそうです。
このすりバチの中ですった食材と調味料などを和えたりして、このうつわごとそのまま食卓に並べても手抜き感がでません!むしろ手の凝った感じを演出してくれます。
これなら余分にお皿を準備する必要がないので、洗い物が増えません。

さらに!離乳食作りにも大活躍!
妻がよく言っていました。「ブレンダーがあると楽だけど、しらすをちょっとすり潰したいときに使えない・・・。」
湯通ししたしらすをすり潰したいとき、ある程度量がないとブレンダーでは歯が当たらず、満足に潰すことができないこともありました。
そんなに量は必要ないけど、しっかり潰したい。そんな時にこのすりバチが活躍してくれます。
安定した形でほどよく重みもあり、すりバチがぐぐぐとすりコギを受け止めてくれるので、しっかりとすり潰すことができます。

ちなみに最近作って美味しい!と思ったのが「マグロのなめろう」。本来なめろうはアジで作るのが主流ですが、ちょこっとアレンジでマグロを使ってみました。
すりバチでマグロの身をすると、口当たりがとても滑らかに!最後に角切りにしたマグロとアボカドを入れて和えてみました。ごはんの上にのせても美味しい、酒の肴にもぴったりなおかずが完成しました!
このすりバチは底が広めなので、ちょっとしたおかず程度なら、こぼれる心配なく全体に味がしっかり馴染むように食材を混ぜ合わせることができます。
このレシピでも、マグロとショウガやネギが程よく混ぜ合わさって、美味しく仕上がりました。これもうれしいポイントのひとつです。

溝がない不思議なすりバチ。とても使いやすいので、あのレシピもできるのでは?あれも作ってみよう!とアイデアや欲がどんどん湧き出てきます。
このすりバチを使っていろんな料理にチャレンジして、自分の料理のレシピの引き出しを増やしていこうと思います。
編集担当 森田
<掲載商品>
かもしか道具店 すりバチ