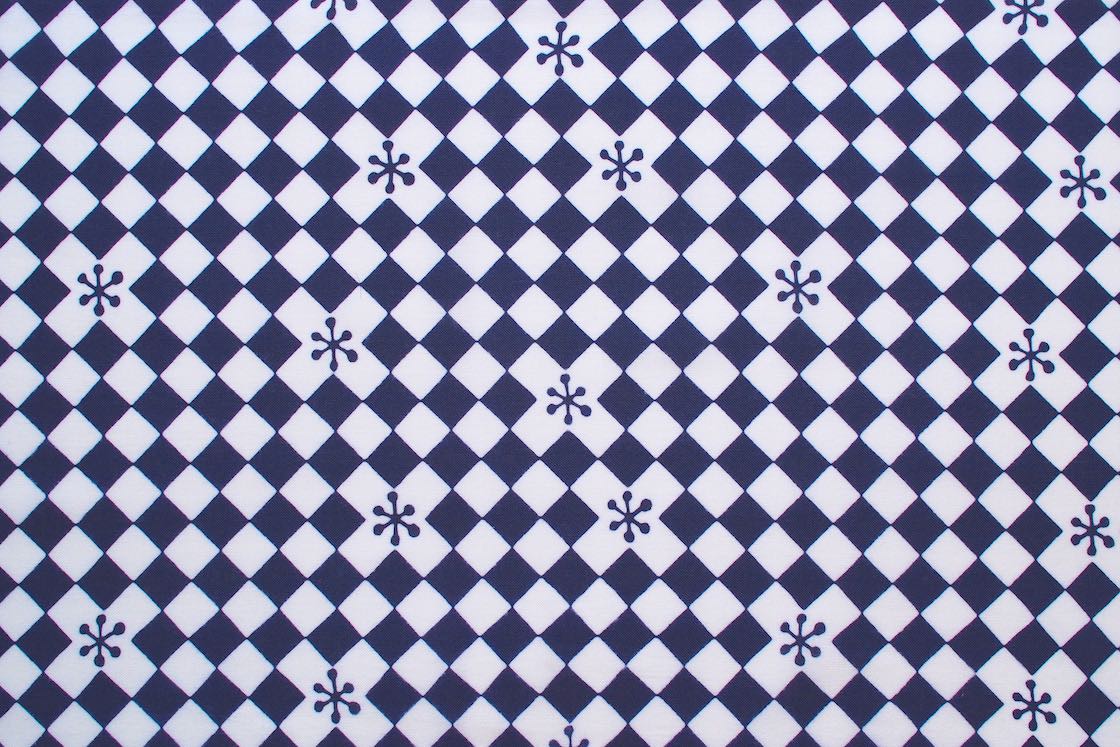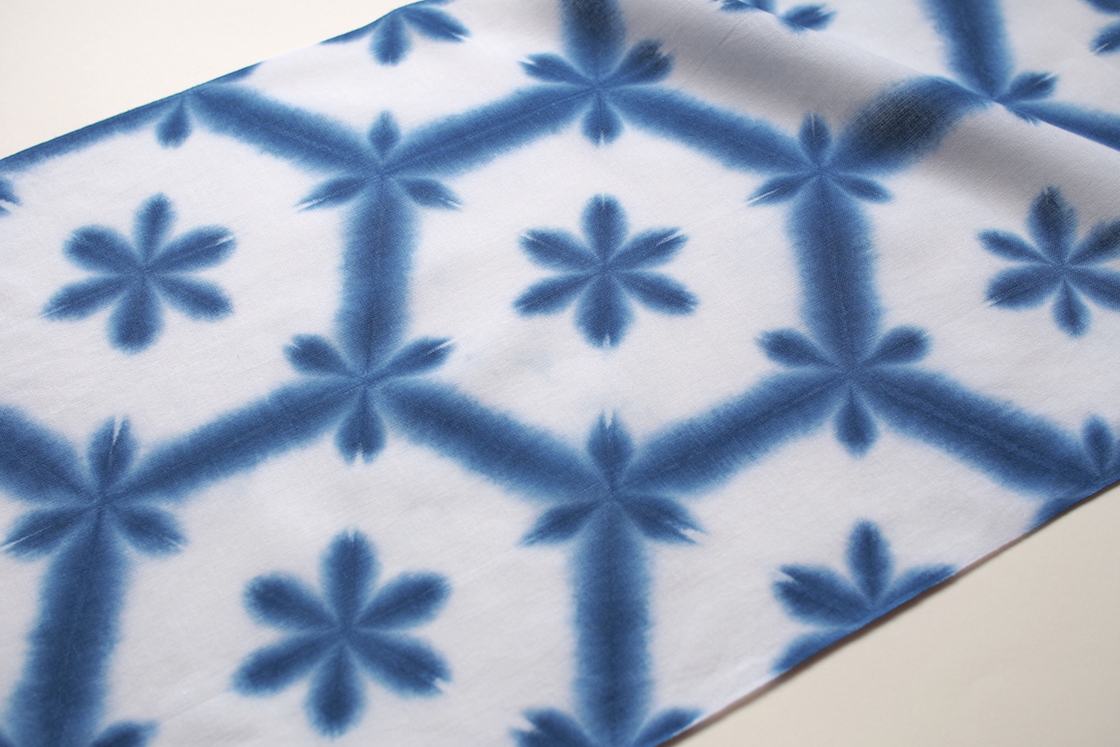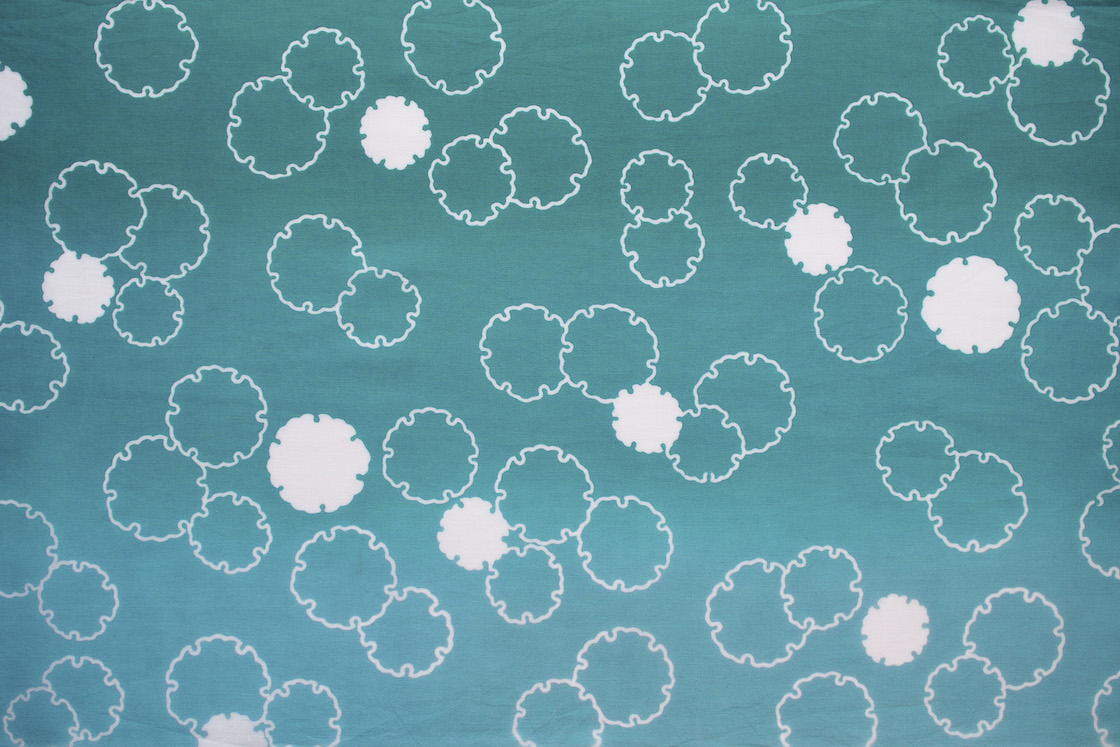はじめまして。THEの米津雄介と申します。
THE(ザ)は漆のお椀から電動自転車まで、あらゆる分野の商品を開発するものづくりの会社です。例えば、THE JEANSといえば多くの人がLevi’s 501を連想するような、「これこそは」と呼べる世の中のスタンダード。THE〇〇=これぞ〇〇、といったそのジャンルのど真ん中に位置する製品を探求しています。
ど真ん中というのは市場にある製品の平均点という意味ではありません。世の中には様々なデザインの製品がありますが、それらを選ぶときに基準となるべきもの、その製品があることで他の製品も進化していくようなゼロ地点、つまり本来在るべきスタンダードはどこなのか?といったことを考えようという試みです。
今日から月に1回、「デザインのゼロ地点」と題して、世の中の様々な製品のゼロ地点を探す旅にお付き合い頂けたらと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
さて、第1回目のお題は「醤油差し」。
器やカトラリーのように食卓で目立つ存在ではありませんが、日本であればどこの家にも1つはあると思います。ところがひとたび買おうと思うと、インテリアショップから量販店や100円ショップまで、材質も陶磁器やガラス、プラスチックなど、選択肢が多くて困ってしまいます。
商品を選ぶ、または開発するとき、僕らは5つの項目で評価をしています。
「形状」「歴史」「素材」「機能」「価格」
商品はこの5項目がそれぞれ密接に絡み合って出来ています。例えば、機能から生まれた形状だったり、歴史的背景のある素材だったり。
そんなことを考えながら、醤油差しの世界を覗いていきましょう。
醤油が生まれた経緯は諸説ありますが、文献上で歴史を辿ると700年代には既に醤油を扱う「主醤」という職業名があったとされています。
当然、保管や輸送方法もその時代背景によって大きく変わっています。
江戸時代より前は甕(かめ)による保管が一般的で、江戸時代に入り醤油が工業的に生産されるようになったタイミングで、割れやすく重かった甕から丈夫で軽い杉樽に変わったと言われています。このころ一般の人々は徳利や壺などを持って醤油を買いに行き、自宅でそのまま保管したり自宅用の甕に移し替えたりしていたそうです。
 しょうゆ徳利(とっくり)ともに野田市郷土博物館所蔵
しょうゆ徳利(とっくり)ともに野田市郷土博物館所蔵
 コンプラ瓶 キッコーマン国際食文化研究センター所蔵
コンプラ瓶 キッコーマン国際食文化研究センター所蔵
 結樽(ゆいだる)キッコーマン国際食文化研究センター所蔵
結樽(ゆいだる)キッコーマン国際食文化研究センター所蔵
明治を経て大正時代にはガラスの自動製瓶機が普及し、醤油の保管や輸送もガラス瓶が一般的になります。おなじみのキッコーマンが会社として設立されたのが大正6年。その後間もなく一升瓶入りで販売を開始していたそうです。
 キッコーマンしょうゆ1.8L瓶
キッコーマンしょうゆ1.8L瓶
つまり、醤油の輸送は陶製から木製へ、そして家庭用容器は陶製からガラス製へと歴史的背景によって形状や素材を変えてきました。
では食卓の醤油差しはどのような系譜を辿ったのでしょうか。
磁器の醤油差しの名品、白山陶器の「G型しょうゆさし」は1958年(昭和33年)の発売。森正洋さんがデザインしたこの醤油差しは今でも多くの人に愛されています。
 陶製の醤油差しいろいろ
陶製の醤油差しいろいろ
「G型しょうゆさし」が生まれた3年後の1961年(昭和36年)、日本人なら誰もが知っているであろう赤いキャップの「キッコーマンしょうゆ卓上びん」が誕生します。それまで大きな瓶で買って自宅の醤油差しに移し替えていた醤油を、買った状態でそのまま食卓に置くことができるデザインに変えたのは、当時20代だったキッコーマンの商品開発者と、後に日本の工業デザイン界の第一人者と呼ばれることになる榮久庵憲司さん(同じく当時20代!)でした。
ガラスで中身が見えることや、液だれしにくいという機能、そして商品パッケージとしての役割を果たすこの「キッコーマンしょうゆ卓上びん」は発売から50年で4億本以上販売し、今では海外でも人気を博しています。
 キッコーマン「しょうゆ卓上びん」1961年〜
キッコーマン「しょうゆ卓上びん」1961年〜
倒れにくさや手で持つ仕草を考慮してデザインされた。パッケージとしての価格帯にも関わらず、液だれしにくい構造にチャレンジし、実現しているのは本当に素晴らしい!
さらに近年では、液だれしないことや量の調節がしやすい利点のあるスプレー式や、1滴1滴垂らすことのできるスポイト式、セラミックとシリコンを組み合わせたもの、パッケージ容器では「ヤマサ 鮮度の一滴」から始まった2重構造の真空ボトルなど、プラスチック製を筆頭に安価で機能的な製品も数多く発売されています。
 ポーレックス「セラミックしょうゆ差し」
ポーレックス「セラミックしょうゆ差し」
ボトル部分はセラミック、口元がシリコンで出来ている。シリコンはガラスや磁器に比べて液体に対する摩擦係数が高いのか、かなり液だれしにくい。磁器の質感の良さと液だれ防止機能がうまく両立している。
 スプレー式の容器
スプレー式の容器
便利ですが「お醤油らしさ」に欠けてしまい、使うのは少し抵抗があるかも!?
 ヤマサ「鮮度の一滴」2009年〜
ヤマサ「鮮度の一滴」2009年〜
醤油差し、とは呼べないかもしれませんが、開封後もほぼ真空状態を保ち酸化を防ぐ、という逆止弁を使ったパウチ容器は画期的でした。最近の新商品は180日間も鮮度を保つとのこと!
 キッコーマン「いつでも新鮮シリーズ」ボトルタイプ 2011年〜
キッコーマン「いつでも新鮮シリーズ」ボトルタイプ 2011年〜
キッコーマンはプラスチック製の逆止弁付きの2重構造ボトルを開発し、密封状態を保つ商品を発売。中身が減っても外観形状は変わらず、内側の袋状の容器が醤油の量に応じて収縮する。前述の卓上しょうゆ瓶の進化版といっても良いかもしれません。
こうして市場の様々な製品の遍歴を振り返ってみると、醤油差しのデザインのゼロ地点はどこにあるべきか、といったことがある程度見えてきます。
僕らの考えたゼロ地点の条件は、
・液だれしないこと
・倒れにくいこと
・醤油の容器だと認識しやすいこと
・中に入っている量が認識できて、安心して差せること
・鮮度を保ってくれること
これらをできるだけ満たしていること。
そう考えるとキッコーマンの「卓上しょうゆびん」は鮮度の面は譲りますが50年以上前から変わらないデザインで醤油差し業界のゼロ地点を担ってきたような気がします。
近年、環境配慮から商品パッケージも簡易包装化が進み、2重構造ボトルの普及に伴って国内の売場では「卓上しょうゆびん」を見かけることが少なくなってきました。もちろん包装資材削減は素晴らしいことですが、一方で醤油にまつわる食卓の風景が少しずつ減っている気がして、少し寂しい気持ちにもなります。
そんなことを想いながら、僕らの考えるゼロ地点に程近いものを、江戸時代創業の老舗ガラスメーカー・石塚硝子さんと作りました。
その名もTHE醤油差し。
こちらも是非ご覧頂けたら幸いです。
醤油差しのデザインのゼロ地点、如何でしたでしょうか?
次回もまた身近な製品を題材にゼロ地点を探ってみたいとおもいます。
それではまた来月、よろしくお願い致します。
<写真提供>
野田市郷土博物館
キッコーマン株式会社
ジャパンポーレックス株式会社
ヤマサ醤油株式会社
(掲載順)
米津雄介
プロダクトマネージャー / 経営者
THE株式会社 代表取締役
http://the-web.co.jp
大学卒業後、プラス株式会社にて文房具の商品開発とマーケティングに従事。
2012年にプロダクトマネージャーとしてTHEに参画し、全国のメーカーを回りながら、商品開発・流通施策・生産管理・品質管理などプロダクトマネジメント全般と事業計画を担当。
2015年3月に代表取締役社長に就任。共著に「デザインの誤解」(祥伝社)。
文:米津雄介