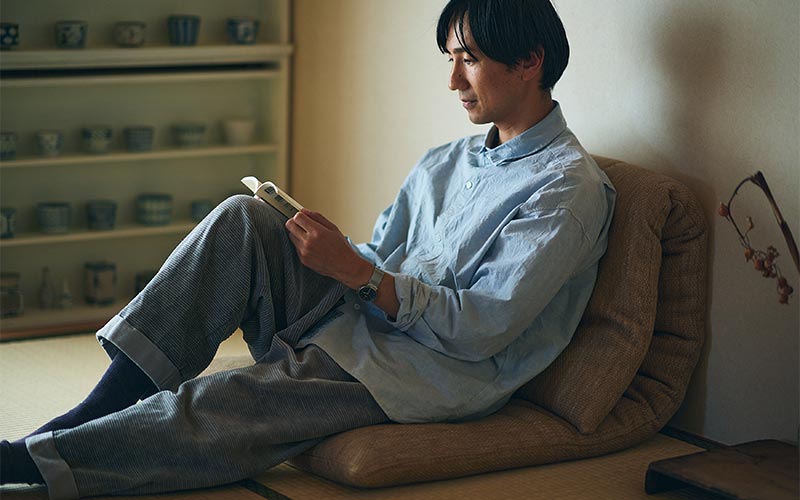「カリッ、じゅわ」お正月にぴったり。本格的なお酒入りの贅沢なボンボン
私はお酒が大好き!とまではいかないのですが、晩ごはんのメニューに合わせてお酒を嗜む日もしばしばあります。
今日はイカのお刺身があまりにも美味しそうで買っちゃったから日本酒を飲もうとか、仕事頑張ったし餃子もカリカリに焼けたからビールをグラスに注ごうとか、休日にお猪口サイズのグラスでウイスキーを味わいながら読書をしよう…という日もあったり。
そんな、ほどよくお酒好きな私が、なんだこれは美味しい!と感動した、大人向けのお菓子をご紹介します。

その名は、『蒸留和酒「浄酎」ボンボン』。
中にお酒が入った、大人のための飴です。
「ボンボン」と聞くと、チョコレートのウイスキーボンボンを思い浮かべる方が多いのでは。
冬になると、お酒入りのチョコレートがコンビニエンスストアに並び出しますが、実はボンボンは、砂糖の殻で、お酒やアーモンドなどが包まれたお菓子を指します。
この『蒸留和酒「浄酎」ボンボン』もチョコレートではなく、小さな砂糖の殻にお酒が閉じ込められています。
ある日、職場のスタッフからお酒が好きなら一度はこのボンボンを食べてみた方がいいよ、と勧められたので早速買ってみました。
仕事から帰って4歳の娘に見つからないように(何食べてるの?と手に持つお菓子を必ず奪われるので)、こっそりソファの影で一粒食べてみました。
「カリッ」「じゅわ」
砂糖の殻をカリッとかじったその瞬間、じゅわっと今までにないお酒の味わいが口中に広がりました。
まるで日本酒の良いところをぎゅっと凝縮させたような、香り豊かな味わい。
「カリッ」と「じゅわ」の二段階で迫る食感。それに加えて、砂糖の優しい甘さとお酒が絶妙にマッチ。
これは、大人のご褒美のお菓子…!
なんでこんなに美味しいのだろうか。
商品担当に聞いてみたところ、中身のお酒と、砂糖の殻に秘密がありました。

まず、お酒の味わいの正体は、広島でつくられている蒸留和酒「浄酎(じょうちゅう)」です。
「浄酎」とは、有機米を使った日本酒を低温蒸留して生まれた、日本酒でも焼酎でもない、第三の和酒のこと。
簡単に言うと、選び抜かれた日本酒を「低温浄溜」という技術で、水分以外のアルコール分などを抽出し、日本酒が持つ香りや甘みをギュッと凝縮させています。つまり、日本酒の良いとこ取りをした贅沢なお酒。
なるほど、納得。そりゃ美味しいはずです。

その手間ひま掛けてつくられる「浄酎」のラインナップの中から、「浄酎 白紙垂」「浄酎 金紙垂」「琥珀浄酎 黒紙垂」の3つが、ボンボンの中に贅沢にも入っています。
ひと箱にそれぞれのボンボンが7個入っていて、全部で21個。
せっかくなので、ちょっとしかお酒を飲まない妻や、お酒好き仲間の職場の人にも食べてもらいました。
それぞれのボンボンの特徴と、味わった感想を紹介しますね。
【浄酎 白紙垂】

透き通るような白さのボンボン。
日本酒の華やかな香りや甘みをそのまま凝縮。濃いけど優しい、不思議な味わいです。
「浄酎」のなかでもスタンダードなものなので、まずはこれから味わってみてください。僕が最初に口にしたのもこちらです。
- クセも少なく、あっさりとした味わい
- 日本酒よりも米感がす少なく、すっきりと甘い
- 妻曰く、「甘みがあるので、普段あまりお酒を飲まないけどこれなら食べられる」
【浄酎 金紙垂】

ほんのり黄色を帯びたボンボン。
「浄酎 白紙垂」をアメリカンホワイトオーク樽で1年以上熟成。樽由来の香ばしさが特徴です。鼻に抜ける香りはウイスキーに近い香ばしさ、そして口中に優しい 甘さが広がります。
- とろみが強いため、バニラのような甘味を強く感じる
- 甘みと香ばしさがマッチ
- 芳醇な香りで贅沢な余韻を味わえる
【琥珀浄酎 黒紙垂】

黄色を帯びたボンボン。
「浄酎 白紙垂」に瀬戸内で無農薬栽培されたミカドレモンの皮で香りづけ、そしてアメリカンホワイトオーク樽で熟成させたもの。
お酒が好きな方にとっては、これが一番満足感があると思います。僕はウイスキーもレモンも好きなので、これが一番好みでした。
- 口に入れてからほどなく、爽やかにレモンが香る
- ウイスキーのような芳醇さで一番強く重厚感があり、余韻が長く残る
- お酒の余韻が残るので、一粒でも満足感がある
とにかく、それぞれ個性があっておもしろい!
お酒好きの方には、ひとつずつ味わっていただきたいです。
琥珀色が強まっていくにつれて重厚感が増していくので、白から順番に味わっていくのがおすすめ。
お酒は嫌いではないけど少々弱い妻曰く、「“浄酎 白紙垂” が一番食べやすかった。たしかに最初はがつんと日本酒を感じるけど、噛んでいくうちに、口の中で砂糖と日本酒本来の甘さが合わさって、贅沢なお菓子だと感じた。これなら食べられる!」とのことでした。

そして次に、砂糖の殻。
この砂糖の殻の甘さと食感が「浄酎」に絶妙にマッチして、大人のお菓子に仕上がっています。
製造は、東京荒川区で100年以上続く老舗飴屋の、ムラマツ製菓さん。
職人が、ひとつひとつ手作業で作っているのですが、実はなんと、このボンボンの原材料は、砂糖と中身の「浄酎」だけ!
こだわったシンプルな素材を、熟練の職人さんが手間ひまかけて、ひとつずつ作っています。
殻は見た目も透き通っていてとても綺麗。
本当に砂糖だけで作っているのか?と思えるほどです。
最初は、カリッ。あとはシャリシャリざくざくと噛む。
噛むほどに砂糖と「浄酎」が合わさっていき、ついついあともう一個…と、手を伸ばしてしまうほど美味しいのです…。
私のなかでは、友人に勧めたい美味しいお菓子ランキングの上位に食い込みました。

これからの季節、年末年始に友人と久々に会ったり、親戚の集まりでお酒を飲む機会が増えますよね。
そんな集まりや帰省などの手土産に、『蒸留和酒「浄酎」ボンボン』がぴったりだと思います。
友人や家族で味比べをして好みの味を見つけてみたり、利き酒ならぬ利きボンボンも楽しそうです。
お酒が苦手なスタッフ曰く、「お正月でお酒を飲んでわいわい楽しむ人が羨ましかったけど、このボンボンなら1個でもその気分に浸れそう」とのこと。

子どもが寝静まった後、夜のゆったり読書タイムのお供にもちょうどよかったです。みんなでわいわい食べるのも良いですが、ひとりでゆったり香りや甘さを味わうのもいいものです。
ボンボンは紅茶との相性が良いのですが、中川政七商店で扱っている「番茶」との相性も抜群。
特に「雑穀と薪火の香り 茶の木番茶」か、「すっきり爽やか 青柳番茶」のペアリングがおすすめです。
「茶の木番茶」は、番茶自体のスモーキーな香りがボンボンに合わさって、贅沢な余韻を生み出します。
「青柳番茶」と合わせると、爽やかな香りとさっぱりとした味わいで後味すっきり。
飲み物とのペアリングによって、さらに味わいの幅が広がるので、ぜひ番茶とのペアリングも楽しんでみてください。
この年末、お正月を楽しむために私はまたこのボンボンをリピートします。笑
そして、本家の「浄酎」のお酒も探して注文してみようと思いました。
ぜひこのお正月に、大人のための贅沢なボンボンをみなさんで味わってください。
※こちらの『蒸留和酒「浄酎」ボンボン』には、リキュールが含まれております。小さなお子様や妊娠中の方、アルコール制限を受けている方はご注意ください。
<掲載商品>
・蒸留和酒「浄酎」ボンボン
・番茶 小袋 雑穀と薪火の香り 茶の木番茶 ティーバッグ3包入
・番茶 小袋 すっきり爽やか 青柳番茶 ティーバッグ3包入
編集担当
森田