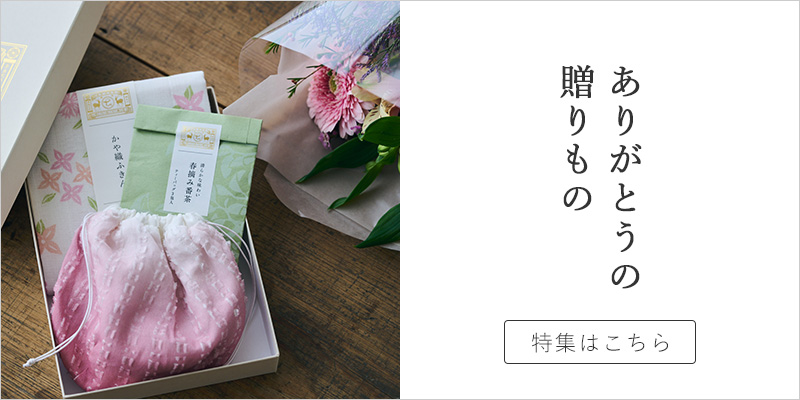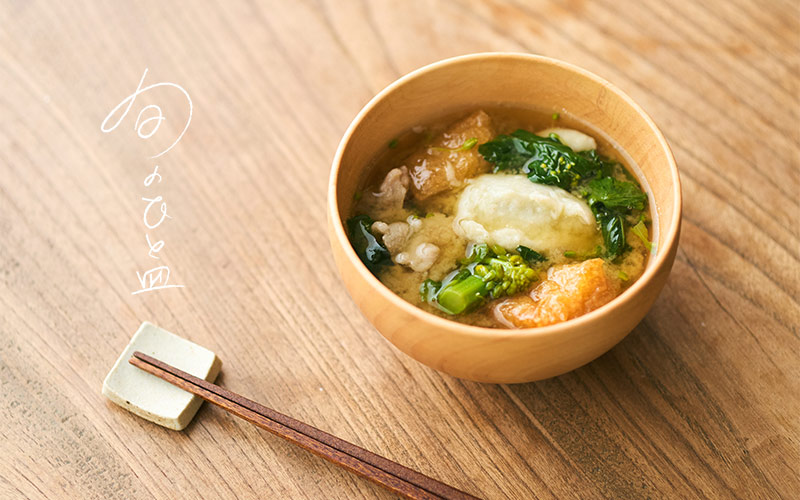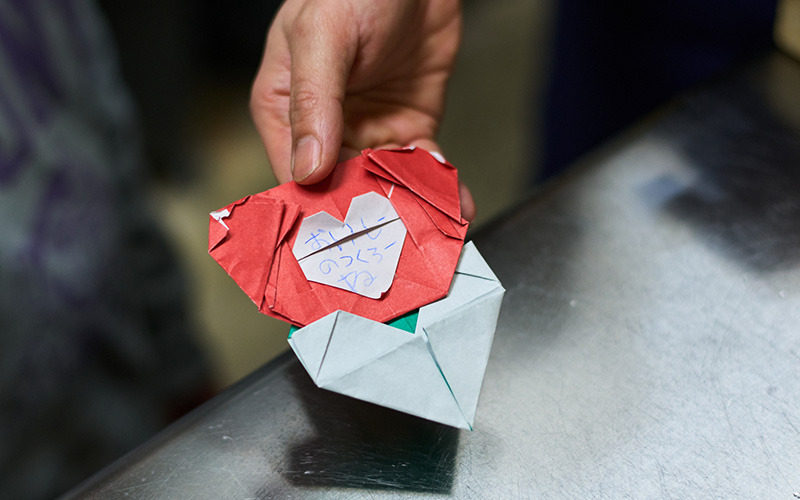1716年(享保元年)に高級麻織物「奈良晒」の問屋として創業し、以来300余年、麻とともに歩んできた中川政七商店。麻を知り尽くした私たちだからこそ伝えたい、うつりゆく季節や暮らしに寄り添う麻の魅力があります。
通気性の高さや生地のシャリ感から夏の素材として想起されやすい麻ですが、実は、ウールと合わせて冬のコートに用いたり、厚手に織り上げた生地を春や秋も着られるボトムスに仕立てたりと、一年を通じて心地好く着られることもぜひお伝えしたい点。
そんな想いから、中川政七商店では「中川政七商店の麻」と名をつけて、麻の魅力を届ける衣服をつくり続けてきました。
デザインを担当する杉浦に、麻の基本と、中川政七商店の麻シリーズのこだわりを聞きました。
日本の衣を長く支える、天然素材
植物繊維の総称である「麻」は、古来より世界各国で用いられてきた天然の繊維。紀元前1万年前には古代エジプトで、その使用が認められたという記録もあるほどです。

日本でも縄文時代には使われていた形跡が残っており、その後、江戸時代には武士の裃として重宝されるなど、武士階級の衣類の中心的存在でした。
また古来「ケガレを祓う」ものとして神事とのつながりも深く、神社でのお祓いに使用する御幣(ぬさ)や、参拝時に鳴らす鈴に垂らされた縄にも麻が用いられています。
今の日本の衣類では綿のほうが多用されていますが、お伝えした通り、昔は多くの場で麻が使われていたのです。
「麻って繊維が強いので、古いものでもまだ残っているんです。正倉院の宝物にも麻を用いた染織品などが残っています。そうやって人の暮らしに寄り添ってきた、歴史の深い素材なんですよ」(杉浦)
ひとことで「麻」といってもその実は20種類近くに分かれ、そのうち衣料用に使われる主な麻には「リネン(亜麻)」「ラミー(苧麻)」「ヘンプ(大麻)」などが挙げられます。
リネンは一般的な麻の衣料にもよく使われる麻。しなやかでやわらかさがあり、麻のなかではやさしい肌触りなのが特徴です。
一方ラミーはシャリ感が強く、清涼感があるため主に夏の衣料に重宝される素材。硬さがあり、繊維として強さのある麻です。
ヘンプは空気を含む特徴があり、保温性・保湿性に優れているため、特に冬におすすめしたい麻。育つのが早く、サスティナブルな素材ともいわれています。
「麻といってもそれぞれの繊維ごとに特徴も違って面白いですよね。『中川政七商店の麻』シリーズではこれに加えて、糸づくりや織り方、布地にする際の加工など、さまざまな要素を組み合わせて生地の質感をつくっています。日本では麻って夏の素材と思われがちですけど、素材の特徴を活かして夏に限らず楽しんでいただけるご提案がしたいなって」(杉浦)
そんな私たちの暮らしを長く支えてきた麻ですが、植物繊維であるがゆえ、年によっては天候不順による不作があるほか、品質も不安定でよい素材を手に入れるのが難しいことも。
その天然の素材を糸にして織り上げるには、長年の経験から積み上げた職人の技が必要とされます。
「織物や染織工芸は水が豊富な土地で特に栄えたので、日本では琵琶湖のある滋賀県や、大きな河川がある地域に多くの染織産地があります。
当社で使用する麻生地は基本的に機械で織っていただくのですが、機械は自分で素材の特徴ごとの調整まではしてくれません。だから職人さんがスピードを調整したり、糸に油分を含ませて織りやすくしたりと、その設定の塩梅に人の技が出るんです」(杉浦)
麻素材の特徴
麻素材の特徴でよく知られるのは通気性の良さ。けれど実はそれ以外にも、暮らしに寄り添う麻の魅力がたくさんあります。
一つ目は「吸放湿性に優れていること」。一年を通して呼吸している素材ともいえる麻は、夏はさらりと着られて、冬は空気を含みあたたかく着られます。
また「見た目の素材感」も魅力的で、洗いざらしでもさまになるようなシワ感は麻ならでは。綿だと洗濯後のアイロンなしではシワが悪目立ちするような場合も、麻のシワは独特の表情をうむためアイロンなしでも着られます。
加えて麻の生地にみられる「上品なツヤ感」は、カジュアルなアイテムでも上品で大人っぽい印象になる嬉しい魅力のひとつ。
さらに、もとはハリのある生地感ですが、だんだんなじんでやわらかくなるのも特徴で、「経年変化の楽しさ」を感じられます。
「表現するなら『古びる』ではなく『育つ』がしっくりくるような。そうやって着るごとに愛着がわくのも、麻の衣料をもつ面白さですね」(杉浦)
汚れがつきにくく落としやすいといわれる素材のため、「洗濯性のよさ」もぜひ知っておきたい点。洗いに強く、先ほどお伝えした通りアイロンいらずでも着られるため、実は扱いやすい生地なのです。
最後になんといっても伝えたいのは「異素材との相性の良さ」。
「中川政七商店の麻」シリーズでも、麻100%で織り上げることもあれば、綿やウールと合わせながら、生地を開発する場合も多くあります。
「例えば綿と合わせて肌あたりのよさを足したり、ウールのあたたかさを足したり、ポリエステルの強さを足したり。他の素材と糸を混ぜたり、交織(素材の異なる糸で織り上げること)しても麻の特性が失われず、むしろ新しい風合いを生み出せて、お互いを活かしあえる素材なんですよ」(杉浦)
中川政七商店と、麻
“誰とでもうまくやれる、コミュニケーション力が高い素材”である「麻」。中川政七商店ではそんな麻の特徴を活かして、定番の麻衣類と、四季折々の麻生地を用いた洋服のシリーズも展開しています。
例えば、定番の麻シリーズで提案するのは、Tシャツやデニムパンツ、また私たちのルーツ・奈良晒と同じ製法でつくる「手績み手織り麻」を使ったシャツ。長きにわたって麻をお届けしてきた中川政七商店だからこそ、いつもの衣類に麻の魅力を取り入れながら、その着心地や表情を楽しんでいただける一着に仕上げています。
 中川政七商店の定番服。左は「手織り麻を使ったフリルシャツ」、右は「麻のデニムパンツ」
中川政七商店の定番服。左は「手織り麻を使ったフリルシャツ」、右は「麻のデニムパンツ」
また、四季折々のコンセプトでつくる「毎月の麻」シリーズでは、毎回、その季節にまつわる言葉とビジュアルを沿えて展開。麻と別素材を合わせたり、麻の特徴にスポットをあてたりと、いろいろな織り方や加工方法で季節に合わせた麻をご提案しています。
「日本には四季があって、気候や、植物の移ろいを表す二十四節季などの美しい言葉もありますよね。そうやって季節の移ろいを楽しみながら、旬の食材を食べたり季節に合わせたしつらいをするように、服にも季節を上手にとりいれて、その時季の風景に自然と溶け込む佇まいになるように『毎月の麻』シリーズは企画しています。
あとは気候だけじゃなくて『新年はこんな服が着たい』といった風に、暮らしや気分に寄り添えるよう生地やデザインを考える月もありますね。そうやって素材や色、形を毎月検討しながら、麻の魅力をもっと知れる機会になればと思ってつくっています」(杉浦)
その懐の広さこそ、他の素材にはない麻ならではの大きな魅力。
江戸時代に麻の商いからはじまった中川政七商店は、これからも、過去にも、未来にも思いをはせながら麻のものづくりを丁寧に続け、皆さんに麻の魅力をお届けしてまいります。
<関連特集>

<関連記事>
・麻とはどんな素材なのか?日本人の「服と文化」を作ってきた布の正体
文:谷尻純子