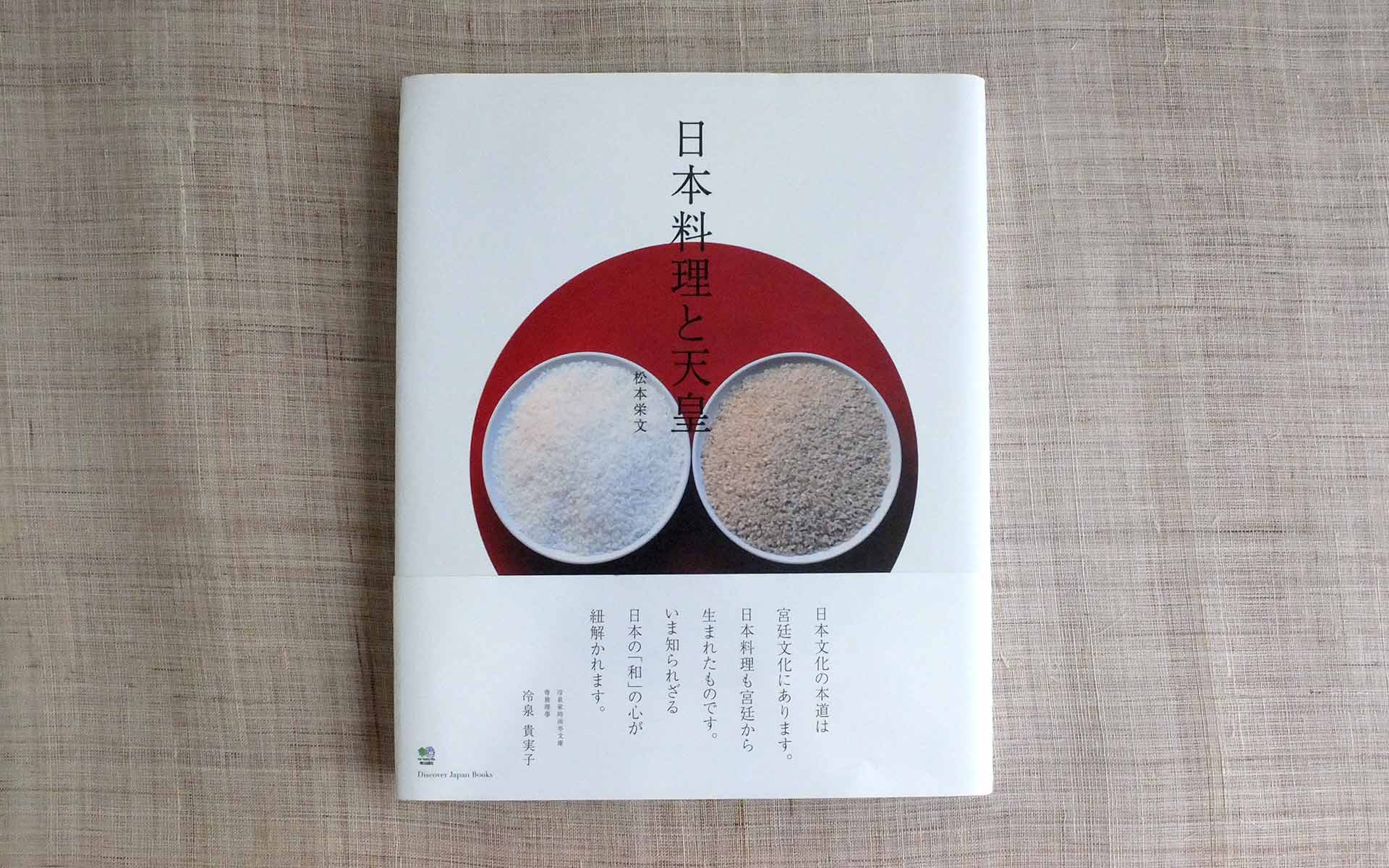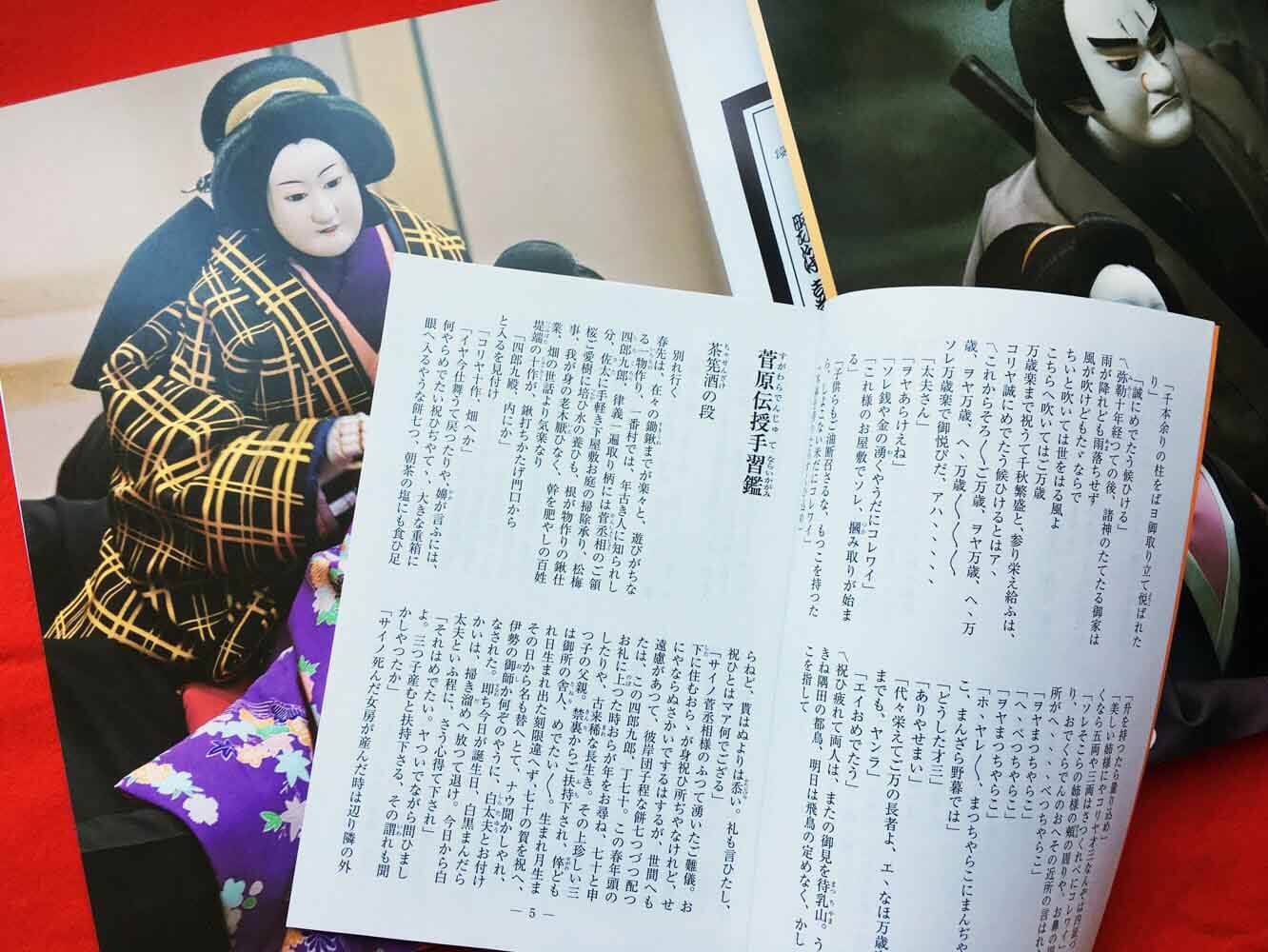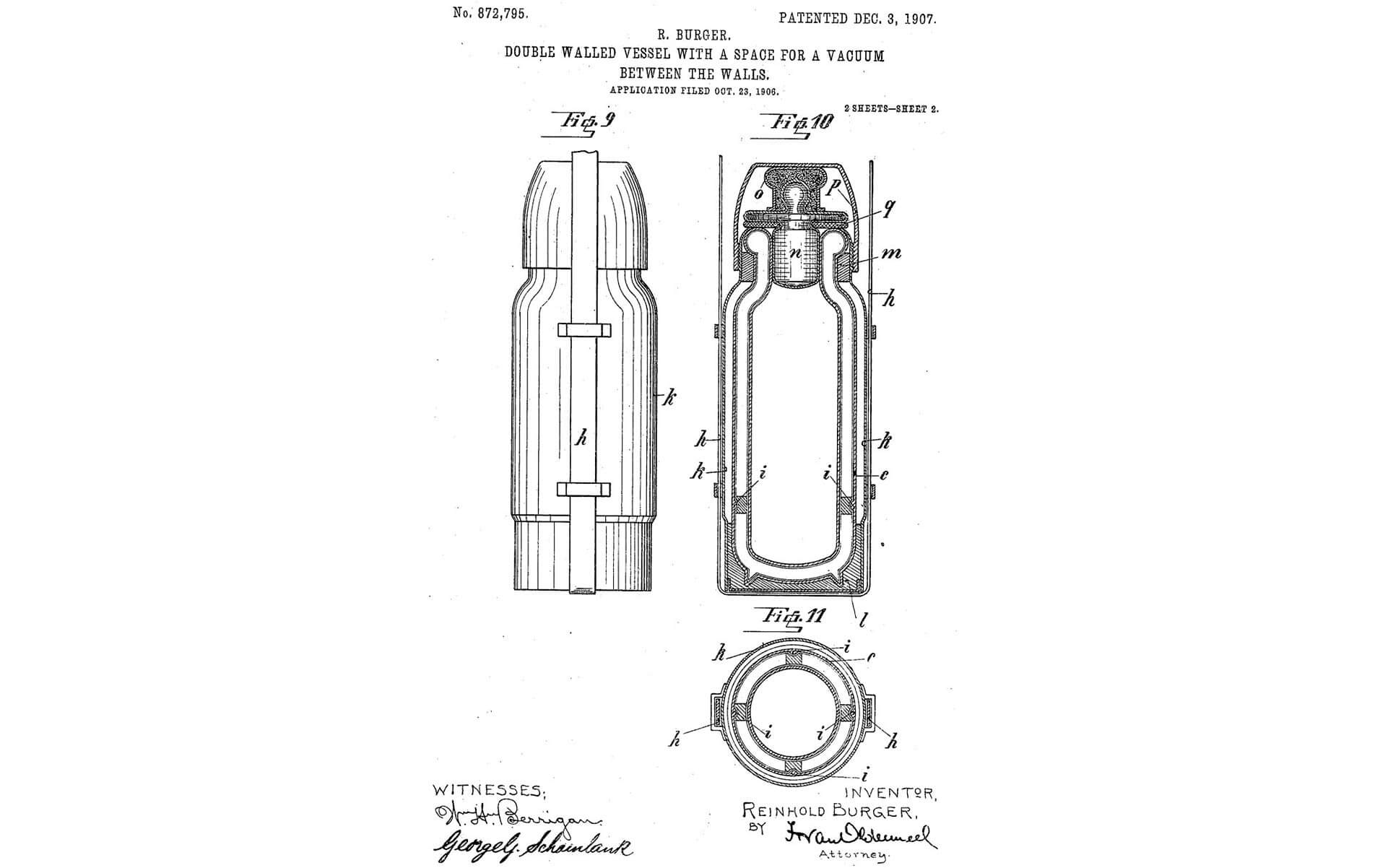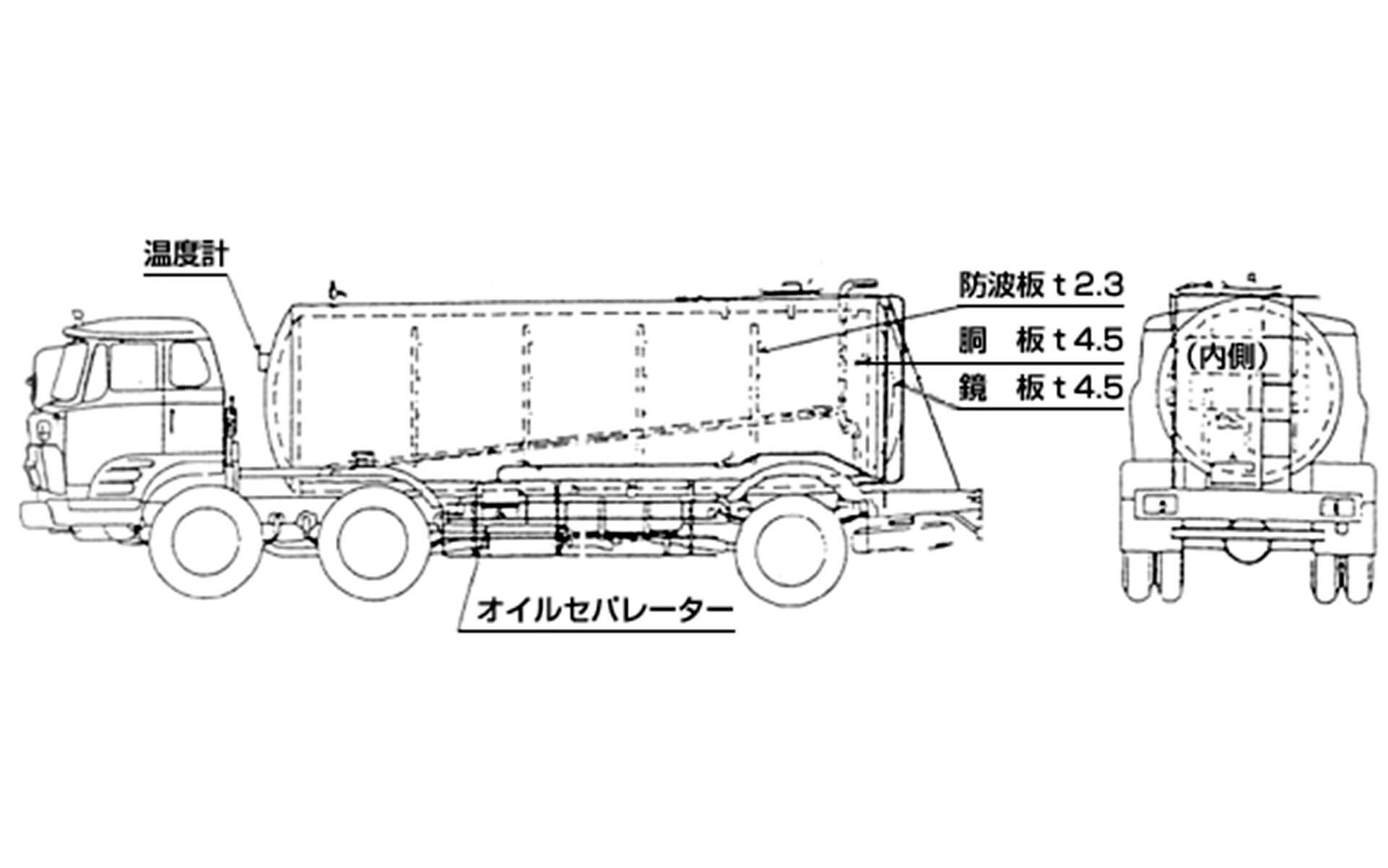こんにちは。ライターの川内イオです。
今回は三重県亀山市関町で店を構える唯一の桶職人のお話をお届けします。
昔ながらの町並み、という売り文句はよく耳にするけど、訪ねてみるとがっかりすることも少なくない。すっかり観光地化されて、似たようなお土産屋さんばかりということも多く、テーマパークのように見えてしまう。
その点、東海道五十三次の47番目の宿場にあたる三重県亀山市の関町は、歴史情緒を感じさせる落ち着いた町並みが、東西1.8キロにわたって続く。特に、江戸後期から明治時代にかけて建てられた町家が200棟以上も現存している町の中心部、中町はそこにしっかりと根付いた生活の息吹を感じて、タイムスリップしたような感覚を味わえる。
 関の中町。週末は観光客でにぎわう
関の中町。週末は観光客でにぎわう宿場として栄えた関は、人や馬が足を洗うために桶の需要が高まり、往時は数軒の桶屋が軒を連ねていたという。その関の中町で唯一いまも店を構えているのが、明治15年創業の桶重。135年の歴史を持つ、桶屋さんだ。
 風情を感じさせるレトロな店構え
風情を感じさせるレトロな店構えガラス張りのお店をのぞくと内側には仕事場が広がっていて、いかにも使い込まれたさまざまな道具や作りかけの花桶が見える。引き戸を開けて挨拶をすると、四代目の服部健さんが迎えてくれた。
一から十まで手作りの桶
服部さんは、今年67歳。小柄で語り口は穏やかながら、向き合うと熟練の職人さんが共通して持っている「静かな迫力」のようなものが伝わってきて、思わず背筋が伸びる。
服部さんは花桶、おひつ、寿司桶、漬物桶、たらいなど「桶」と名の付くものとその類縁にあるものを受注生産していて、修理も受け付けている。価格は最も小さな花桶が7000円と聞いて驚いたが、桶を作る過程を聞けば誰もが納得するのではないだろうか。
 服部さんが作業をしている日は、店先から見学できる
服部さんが作業をしている日は、店先から見学できる服部さんは、創業時から受け継がれる伝統的な技法を頑なに守り続けている。「昔からのものをそのまま伝えるのが、伝統工芸」というのが持論で、既製品を一切使用せず、一から十まで完全なる手作り。「親の代から子の代まで、50年は持つ」というその仕事は、素材を選ぶことから始まる。
よく使うのは、椹(さわら)と槙(まき)と杉。一番高級なのが椹で、信州(長野県)で生えているモノを使う。寒さが厳しい長野の高地で育つと、成長が遅くなり年輪が詰まる。すると目が細かくなり、水が漏れにくいそうだ。漬物桶や味噌桶に使う地元の杉、風呂桶や風呂で使う湯たらいに使う槙も、長年の付き合いがある業者から原木を仕入れていて、市販されているような材木は使わない。
「うちの桶は高いと言われるけど、木が高いんだ (笑)。例えば、おひつや寿司桶みたいに熱いものを入れる桶を作るとき、普通に売っている木を使うと、2、3年もしたら木が歪んで、タガ(桶の周りにはめる輪)も緩む。それで終わりやで。だから、熱いものに使う桶は、自分で仕入れた原木を割ってみて、まっすぐに割れた木しか使わない。そういう素性の良い木を使えば、何年たっても歪まん」
竹一本にまでこだわり抜く
タガや一枚一枚の板を固定する釘としても重宝する竹にも徹底的にこだわる。服部さんが作る桶は、一般的によく使われる接着用の米糊を使わないものもあるので、タガと竹釘が生命線なのだ。
 一本一本、竹を細く割いて作るタガ
一本一本、竹を細く割いて作るタガ服部さんが使うのは、硬くもなく柔らかすぎず加工がしやすいという「生えてから4年、5年経った、関東の雑木林の南斜面にある真竹」だが、これは最初の条件に過ぎない。
求めているのは、暦の上で1年に6回ある「八専(はっせん)」と呼ばれる期間のうち、11月頃の八専が終わった直後に刈った竹のみ。その時期の竹は水を吸い上げる力が弱っており、刈った後に虫がつかないという。
竹を刈る日も、限られている。竹の中にある節が闇夜には上を向き、月夜には下を向く。節が下を向いている竹のほうが作業しやすいため、月夜の晩に刈ったもの限定。これも、信頼関係のある業者から条件に合った竹を一括で仕入れ、暗闇の中で保管する。
そうして注文が入ると一本、一本引きだしてきては竹を細かく裂いてタガにする。指先に乗るような直径数センチほどの竹釘も、この竹を使ってひとつひとつ手作りする。
これだけで気が遠くなりそうな作業量に思えるが、服部さんは「なんも大変なことない。昔から普通にやっていたことやんか」と笑う。
 鉄の釘は弾力性がなく水で錆びてしまうため、柔軟性があり強度もある竹釘を使う
鉄の釘は弾力性がなく水で錆びてしまうため、柔軟性があり強度もある竹釘を使う小さな花桶の製作にかかる日数とは?
原木を割り、必要な大きさに切った木材は、一度、3年ほど乾燥させる。その後、「せん」という道具で荒削りしてから、注文に合う大きさのカンナで削りだす。刃の部分が湾曲しているため、桶の円周に近づいていく。一枚、一枚、「正直台」と呼ばれるカンナで削る角度をこまめに確認し、ミリ単位の調整をしながら作業を進める。寸胴ではなく、上口から下口へすぼまる形の桶の場合、その勾配の角度(落ち)は計算せずに感覚で決めていく。
「落ちが強いとみっともない。ちょうどええ形になる角度がある」
 桶用のカンナ。よく見ると桶の形に合うように刃の部分が婉曲している
桶用のカンナ。よく見ると桶の形に合うように刃の部分が婉曲しているひと通り側板ができたら、キリで側面に穴をあけて竹釘を打ち込み、ときには米糊を塗って板と板をつなげていく。そうして一度桶の形にすると、内側と外側を改めてカンナで削り直し、滑らかに整える。それから底板をはめ込み、編み込んだタガで桶を締め上げる。
完成品にはわずかなズレもなく、きれいな円や楕円を描く。その見た目は凛として清々しく、桶としての機能性も抜群に高い。
「水が漏れないようにするのが桶屋の技術。桶の寿命は50年と言われているから、その感覚で作ってます」
これこそまさに、圧倒的な経験値と技術に裏打ちされた手仕事の極みだろう。しかし、冒頭で7000円と書いた小さな花桶が完成するまでに、2日半。旅行者用に手ごろな値段に設定しているとは言っていたが、つい頭のなかで時給の計算をしようとして諦めた。日給で考えても厳しすぎる金額だ。
 ちょうど作業場で作り途中だった7000円の花桶
ちょうど作業場で作り途中だった7000円の花桶服部さんが、作り置きをせず、インターネットで販売もせず、受注生産に絞っている意味がわかった。服部さんの技術力を認めている人が注文し、その価値に見合った対価を支払うという形にしなければ成り立たない。
すべてを変えたプラスチック
裏を返せば、自分の腕に相当な自信がなければできないことで、服部さんは「うちが他所より(質が)落ちるとは思わない」とはっきり口にする。
とはいえ、幼い頃から桶屋を目指して修業を積んできたわけではない。「本気で桶屋をやろうと思ったのは、40歳ぐらいから」と照れ臭そうに笑う。
そこには、時代の荒波に揉まれてきた桶重の歴史が関係している。
「初代は重蔵という名前で、明治15年に関でこの店を開いて、桶重と名付けたんだ。その頃、桶はライフ用品でしょう。風呂桶、おひつ、寿司桶、行水する大たらい、小さなたらい、水桶、井戸で使う釣る瓶。とにかく需要が多くて、初代と二代目までは羽振りが良かったみたい」
 初代がつけていた台帳。三重県伊勢市の銘菓として知られる赤福餅を作っている老舗の和菓子屋赤福の名も
初代がつけていた台帳。三重県伊勢市の銘菓として知られる赤福餅を作っている老舗の和菓子屋赤福の名もそういうと、服部さんはアルバムを見せてくれた。そこには、二代目が巨大な桶を作っている写真が収められていた。かつて味噌桶や漬物桶として使われていたもので、大きなものは7尺(約212センチ!)もあるそう。こうした大掛かりな注文のほかにも桶屋の需要は幅広かったが、あるときを境に、完全に流れが変わった。
「先代まではね、冬場になると京都に作業場を借りて、職人を連れて京都で仕事をしていました。冬に売られる京都の千枚漬けってあるでしょう。昔は贈答用で千枚漬けを木の桶に入れて送ってたんだ。でも、昭和40年代にプラスチックが出てきて、木の桶が必要なくなった。いまは千枚漬けもプラスチックの桶を使っているところが多いな」
 二代目と三代目の作業の様子
二代目と三代目の作業の様子安く、大量に作ることができるプラスチック製品は便利な生活用品となって一気に広まり、木桶はあっという間に駆逐された。三重県の伝統工芸品として知られる「関の桶」も、時代の変化の波に押し流され、「ひとつの町に必ず2軒はあった」という桶屋は、どんどん廃業した。
先代の粘り腰
しかし、先代は店をたたまなかった。桶重では桶の修理もしている。長年使いこんだ桶を修理したいという顧客もいるし、おひつや漬物桶など「やっぱり木桶じゃないと」という取引先もわずかながらに残っていたからだ。
先代は、日雇いのアルバイトをしながら、激減した注文に応える日々を選択した。
そうして粘っているうちに桶屋は全国的にも姿を消していき、わずかに残っていた需要が桶重にまで届くようになった。「いつか桶一本に」と思っていた先代は、腹をくくって再び桶づくりに専念。もともと三重県の名工に認定されていた先代の評判を聞きつけて、少しずつ注文が増えていった。その姿を見て、服部さんも覚悟を決めた。
「その前は手伝うぐらいで、うわべだった。店をどうするかわからんかったしな。親父ももう辞めようかなと言っていた時期もあって、やっていけんのか、ものすごい不安やんか。でも、取引先や修理に持ってくる人がいて、店がなくなったら困るやろなと思って。それに、買ってもらえなかったら自分が悪いし、こういう風にしたほうが良いとか自分の責任で工夫ができるのが良い。スポーツでもなんでも腕一本で勝負するのが好きやし」
後を継ぐと決めてからは、先代からマンツーマンで教えを受けた。見て盗め、というまどろっこしい方法ではなく、手取り足取り仕込まれた。もちろん怒られることもあったが、「仕事してるときは弟子と師匠の関係や。自分ができるようになったら親父もなにも言わへん」と割り切っていたから、耐えられた。
 よく使い込まれた様子の道具。初代から使っているものもある
よく使い込まれた様子の道具。初代から使っているものもある竹や木材の知識、刃物の使い方、水が漏れないようにするための技術など憶えることは無数にあったが、1990年代の半ば、修業を始めて5、6年が経つと先代はこう告げた。
「もうお前に教えることはなにもない」
「死ぬまで修行」はアホ
それから先代が亡くなる1999年までふたりで店を切り盛りし、名工のあらゆる技を吸収した。いま、関に残る唯一の桶屋として店を守る服部さんは、こういう。
「中途半端に習ったら、真似事の世界。極めた人に教えてもらうと、あとは自分の技量次第でなんでもできるようになる」
 タガを打ち込んで桶を引き締める
タガを打ち込んで桶を引き締めるいま、服部さんのもとに届く依頼は「変わった桶ばっかり」。宣伝は一切していないが、口コミで腕の良さが広まり、一般の客だけでなく、全国の神社やお寺などで使う特別な桶の注文がくる。例えば、静岡の神社からは昔から使っていた桶を再現してほしいと声がかかり、関西の神社からは作り手がいなくなった卵型の桶を作ってほしいと連絡が来る。作ったことがない形や用途のものもあるが、それでも、ここには書けない一度の例外を除き、依頼を断ったことがない。
「職人は死ぬまで修行ですという人いるけど、アホかこいつと思う。お客さんがせっかくお金出して買うてくれてるのに、失礼な話や。でも職人の世界はな、例えば昔の古い桶、これと同じものを作ってくれとか修理してくれとか言われたときに、うちはこんなんできんと言うのはありえん。誰が、いつ作った桶でも作れなきゃ、直せなきゃあかん。それができるのが職人、できなかったら単なる趣味や」
小さな花桶を作るのに2日半かかる桶屋の仕事が、決して楽なわけではない。それでも依頼が届く限り、現代の匠は作業場で桶と向かい合う。どんな注文にも応えてみせるという誇りと気概を持って。
「人とグループで仕事してもつまらん。なにがええんかなって。生きとるっていう感じがせんわけよ。桶は一から十までひとりで作ってるからこその達成感があるし、大事に使って喜んでもらうのが一番好き。商売やから、それでなんとか儲かったら嬉しいなって」
 服部さんが作ってきた桶の数々
服部さんが作ってきた桶の数々<取材協力>
桶重
三重県亀山市関町中町474-1
0595-96-2808
文・写真:川内イオ