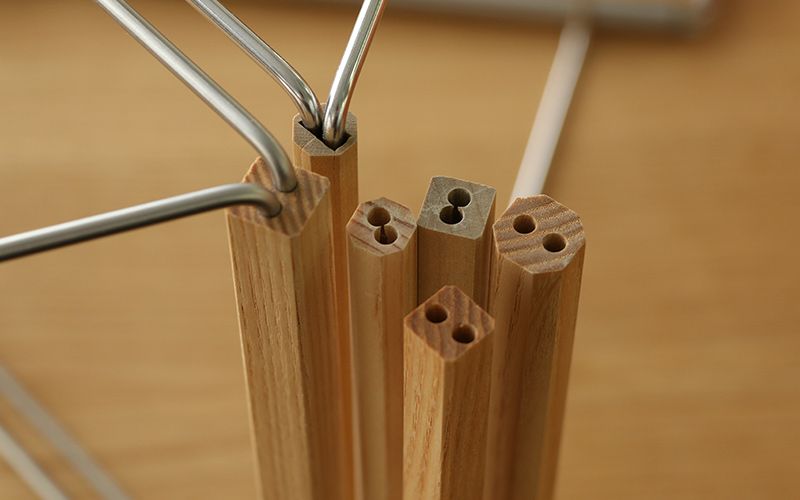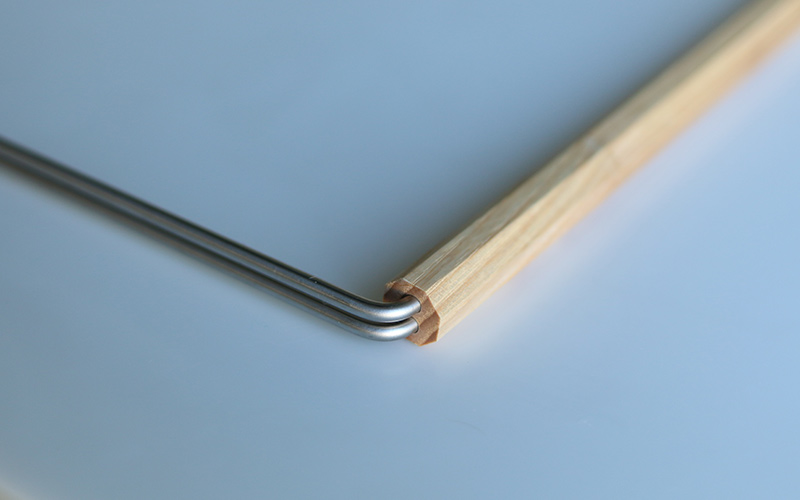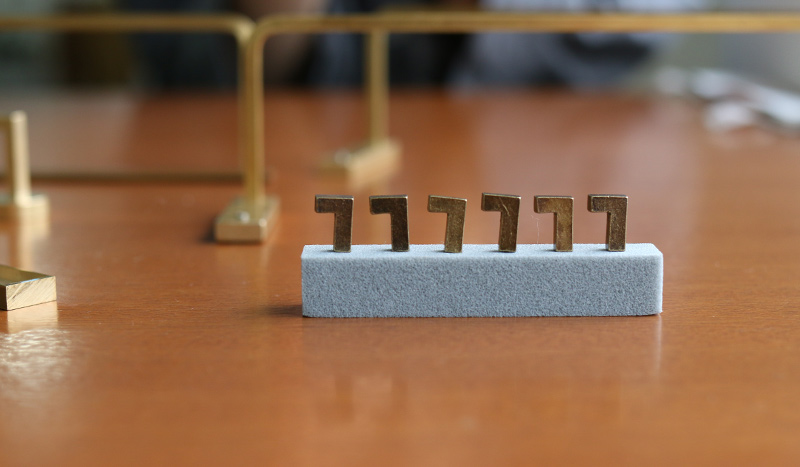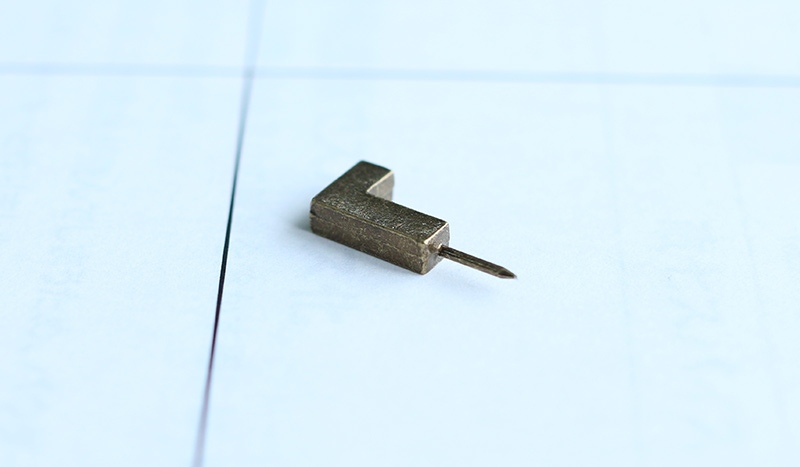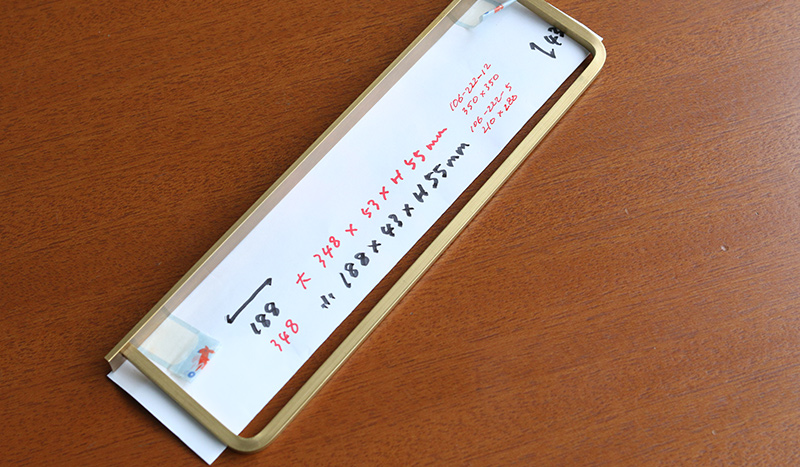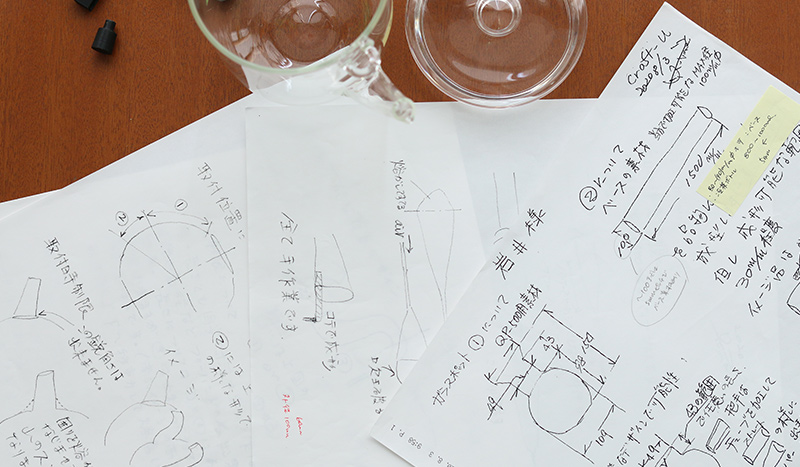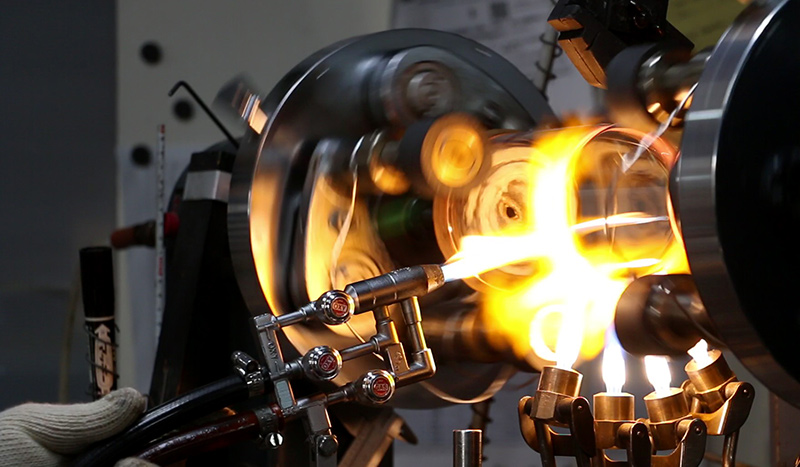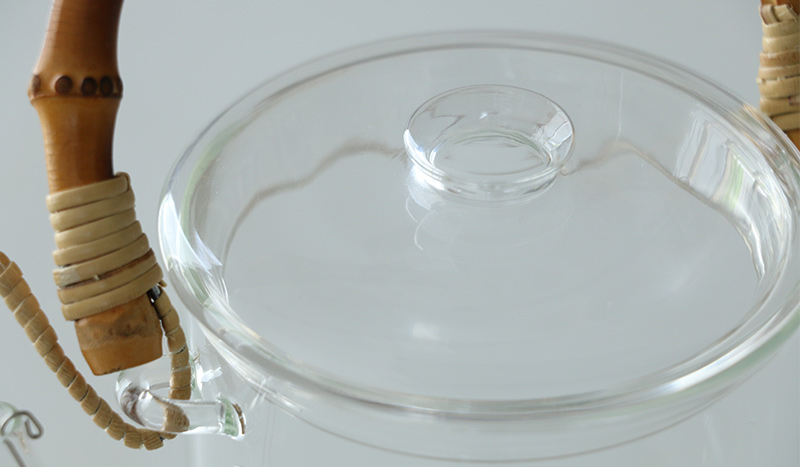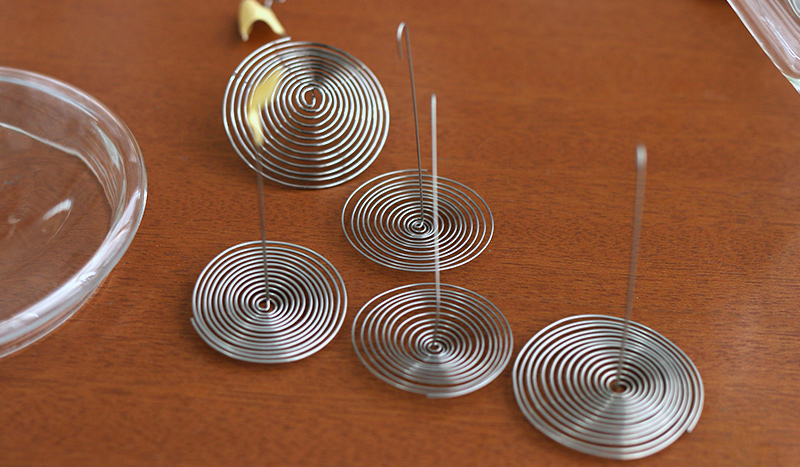小鍋にもちょこっと使いにも便利な「鍋だけじゃない産地の鍋の素!」
産地のごはんシリーズから登場した「産地の鍋の素」。
産地のお鍋から学んだ味だからですが、名前が変わってるな・・という印象でした。
我が家で作るお鍋は、昆布で出汁をとった水炊きか、寄せ鍋が王道なところ。変わり種でもキムチ鍋、豆乳鍋、トマト鍋。
そずり、山椒香る生姜味噌、飛鳥風、聞いただけではどんな味かわからないですよね。しかしそこがですね、産地シリーズの興味惹くところなんです!自分では作り出せない味わいにワクワクしませんか。
私は奈良出身なので、飛鳥鍋は食べることがあるのと牛乳大好きなので、ダントツ「牛乳で作る飛鳥風鍋の素」をおすすめしたい気持ちでいっぱいです。自分で作る豆乳鍋よりも、鶏ガラダシに白味噌が入ってる分美味しい!!コクと味わいがしっかりしてるといいますか、とりあえず美味しい!!豆乳鍋好きさんには、ぜひ食べていただきたいです!
「牛だしのそずり風鍋の素」は、3種類の中では定番のお鍋な感じがします。しかし寄せ鍋とも違うし、生姜が入ってるからさっぱり感があります。このお鍋でおすすめしたいのが、シメにお蕎麦です。もちろん雑炊にしてもうどんでも美味しいのですが、無性にお蕎麦を入れたくなるんですよね。ぜひいろいろ試してみてください。
「山椒香る生姜味噌鍋の素」は、最初の印象がスパイスカレー?と思ったくらい香りがスパイシー。それもそのはず山椒に八角、シナモン、陳皮、クローブ、とうがらしと、お鍋には珍しい調味料が入っているのです。そしてこの香りがたまらなく食欲をそそるんです。3種類の中で一番個性ある味わいですが、我が家の高校生の息子はこれが一番好きだそうです。味がしっかりしていて、シメにはご飯を入れてチーズに生卵と、がっつり食べています。

お鍋のいいところは、だいたいの野菜、お肉、魚介類を受け入れてくれるところ!
我が家の冷蔵庫の余りものも、鍋の素の種類を変えるだけで「今日もお鍋?」と子供に言われることもありません(笑)
この鍋の素の便利なポイントは、キャップが付いたスパウトパウチというところ。1回きりではなく、キャップを締めて冷蔵庫に入れておけば、ちょこちょこっとずつ調味料のように使えるのがとっても便利なんです!
例えば、お鍋をするときも最初は控えめに入れておいて味見しながら足していけるし、出汁が少なくなってきて追い足しする際も、お湯に必要分だけ溶かしたものを足せば水っぽくならない。
さらに我が家の受験生男子の塾帰りのご飯や夜食に一人分の小鍋をさっと作れるし、調味料のように別のアレンジも簡単にできるんです。
子供イチオシ「山椒香る生姜味噌鍋の素」で、いきなりシメご飯は、夜食にがっつり食べたい時にオーダーが入ります(笑)

ちょっとずつ使えるから、冷蔵庫の余りもの鍋にするときも、私はあっさりお魚鍋、子供はしっかりスープ鍋と、お互い好きなものを入れて作ることもできます。


私のイチオシ「牛乳で作る飛鳥風鍋の素」を使えば、クリーム系の一品も簡単です。こういう簡単調味料のいいところは、それだけで美味しい味に出来上がるところ。牛乳にプラスするだけでクリームパスタもムニエルのソースにも!!塩コショウもいらないですよ!
ただ、味変に子供が「国産素材のかける薬味みそ」をかけるのは、私もオススメしたいところです。なんにでも合うのですが、クリーム系との相性は抜群です。

寒くなってきた時の、我が家の朝食はスープが多くなるのですが、ここでも鍋の素はすごく使いやすい。
お湯をわかして、味見しながら鍋の素を入れるだけで、スープベースが出来上がり。あとは適当に野菜やソーセージなどを入れるだけ。お腹の足しになる「トック」(韓国のお餅のようなもの)を足したら、朝食のできあがりです。小さなお鍋ひとつで出来るので、簡単ですよ。

鍋だけじゃなくて、ちょこちょこっと使える鍋の素は、私の毎日のご飯のお助けアイテムとして大活躍です。

まだまだこれからが冬本番、だんだん外に出たくなくなってきても美味しいお鍋に料理にと、楽しみながら冬を越そうと思います。
<掲載商品>
産地の鍋の素3種はこちら
小鍋にもなる伊賀焼のスープボウルはこちら
小鉢から麺類までサイズが豊富な食洗機で洗える器はこちら
担当編集者 平井