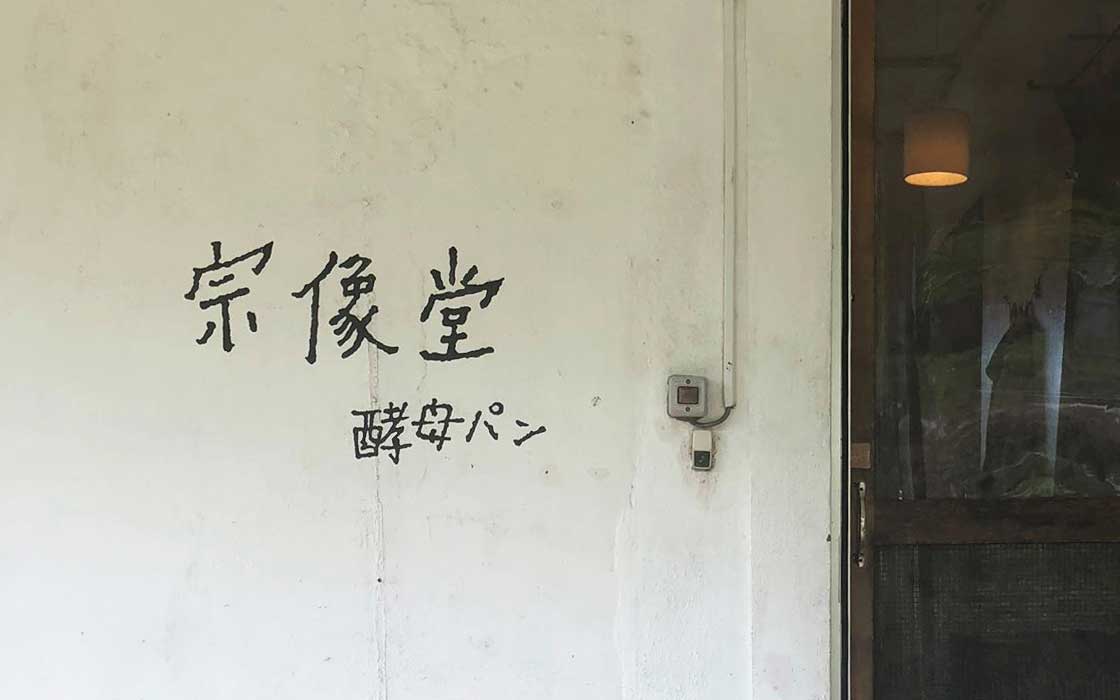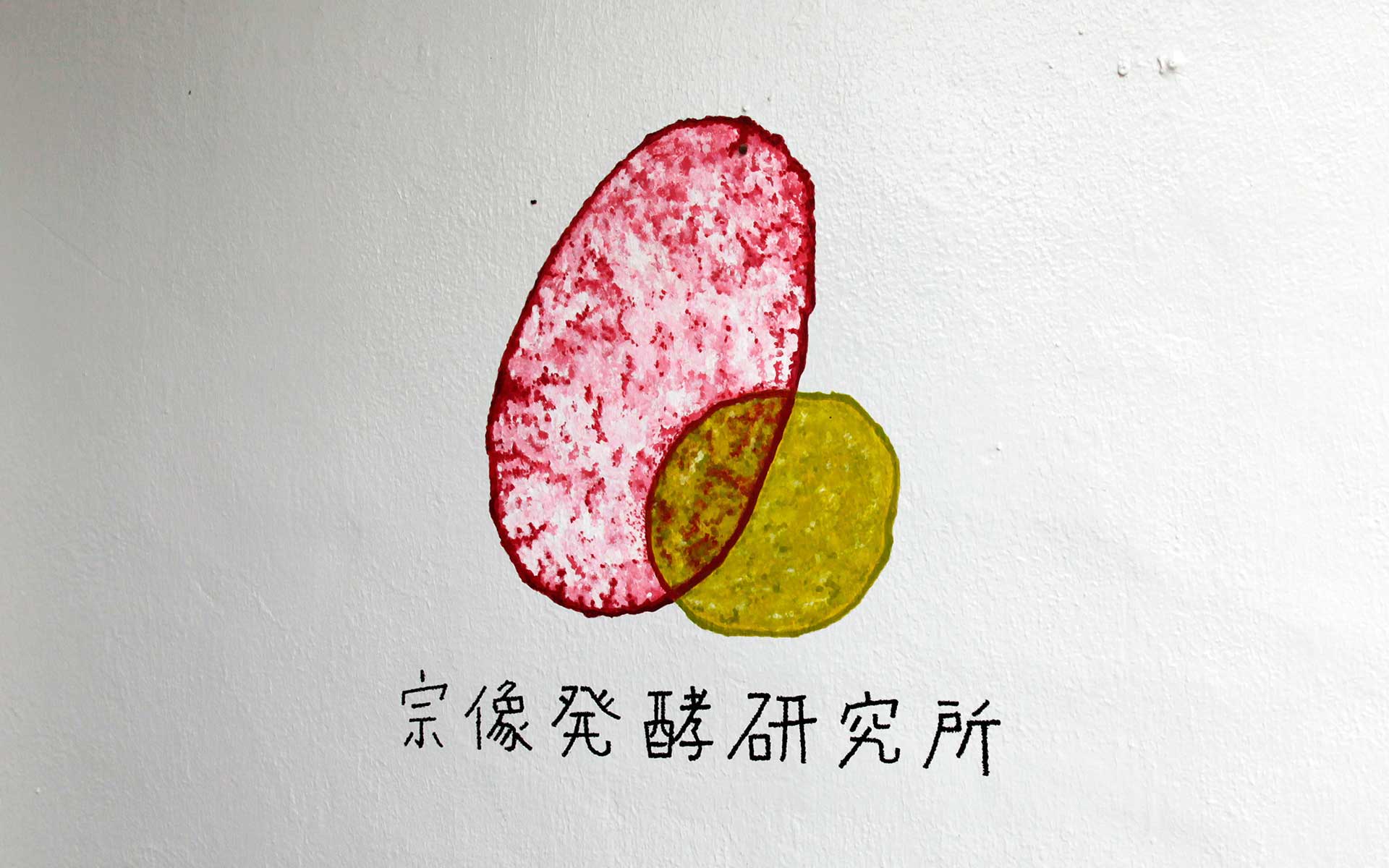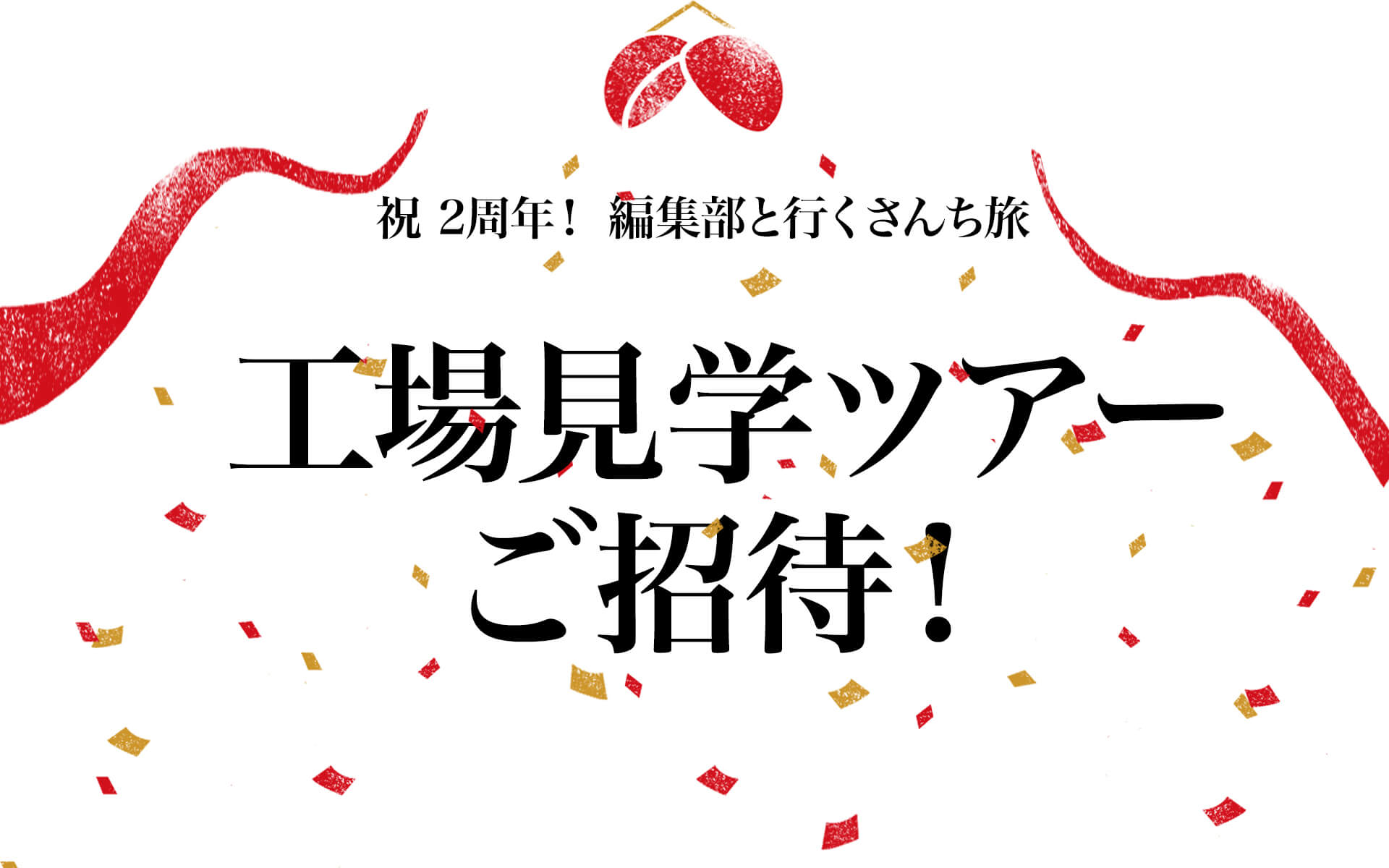「こんぴらさん」の通称で古くから親しまれてきた、讃岐の金刀比羅宮(ことひらぐう)。江戸時代、庶民が「旅」を禁止される中で、唯一許されていたのが神仏への参拝旅でした。
伊勢神宮への参拝「お伊勢参り」に並び、「丸金か京六か」といわれ、一生に一度の夢だったのが四国の金毘羅大権現(今の金刀比羅宮)と、京都六条の東西本願寺への参拝。どちらも当時は庶民のあこがれの旅先として、一大ブームになったといいます。
今回は香川県仲多度郡琴平町、金刀比羅宮へ。「こんぴらさん」をお参りします!
こんぴらさん、こんにちは。
金刀比羅宮は、香川県西部の象頭山(ぞうずさん)の中腹に鎮座しています。島である四国の山の中にあるため、参拝をするには海を越えなければなりませんし、さらには長い長い石段を登らねばなりません。
そうまでしても人々が訪れた「こんぴらさん」参りには一体どんな魅力があるのでしょうか。
 琴平駅を降り立つと、「ようこそこんぴらへ」の看板がお出迎え。
琴平駅を降り立つと、「ようこそこんぴらへ」の看板がお出迎え。本宮まで続く、785段の石段
賑やかなお土産やさんが並ぶ表参道を抜けると、石段がはじまります。ここから御本宮までは785段。記念すべき第1段を踏み出し、スタートです!
 第1段め。このときは785段の凄まじさを知る由もありませんでした…。
第1段め。このときは785段の凄まじさを知る由もありませんでした…。 皆さんも、登り始めは軽快です。手に杖を持っている方が多数。
皆さんも、登り始めは軽快です。手に杖を持っている方が多数。 皆さんが手にしているのは、こちらでしょうか?
皆さんが手にしているのは、こちらでしょうか?石段を登る人々が手にしている杖は、観光案内所や土産物店で貸し出している竹の杖。私も杖を持って臨みたいところですが、今回はカメラを抱えているので断念。
日頃の運動不足からか、ほんの数十段登っただけで息があがってしまいます。石段の両側にはさまざまな土産物店が並んでいるので、休憩しながらゆっくり登ります。
 こちらは「石段かご」というもの。これに乗ればこの石段もらくらく、でしょうか。
こちらは「石段かご」というもの。これに乗ればこの石段もらくらく、でしょうか。 そう、修行ではないので、土産物店をのぞきながら一歩一歩進んでいきます。
そう、修行ではないので、土産物店をのぞきながら一歩一歩進んでいきます。 やっと100段!
やっと100段! 100段を過ぎてから、石段が急に。やはり修行のような気がしてきました…。
100段を過ぎてから、石段が急に。やはり修行のような気がしてきました…。 石段の傍に座りこんで休む方もちらほら。私もひざが痛いです…。
石段の傍に座りこんで休む方もちらほら。私もひざが痛いです…。 やっと200段!756段まで、まだまだ1/4を越えたところです。
やっと200段!756段まで、まだまだ1/4を越えたところです。そうこうしていたら、なんだか軽快な足音が聞こえてきました!私を追い越し、颯爽と石段を登っていくのは「石段かご」。いやはや、お客さんは楽々ですが、かごとお客さんを担ぎながら登る両側のおじさま達は、相当な脚力と気力が必要ですね。
 2人で息を合わせてお客さんを運んでくれる「石段かご」。かなりの力仕事です。
2人で息を合わせてお客さんを運んでくれる「石段かご」。かなりの力仕事です。 294段目。ようやく先に大きな建物が見えました。
294段目。ようやく先に大きな建物が見えました。石段365段目、神域へ。
365段目にある大門をくぐると境内に。かの水戸光圀の兄にあたる松平頼重から寄進されたもので、二層入母屋造(にそういりもやづくり)の瓦葺。ここからは、いよいよ神域に入ります。
 大門。ここからぐっと神社らしくなります。
大門。ここからぐっと神社らしくなります。大門をくぐったところには、平らな石畳「桜馬場」。こちらでは大きな和傘をさして飴を売る「五人百姓」に出会えます。
「五人百姓」は、境内で唯一商いを許された存在なのだそう。4月頃には傘の上に桜の花がみられるでしょうか。
 参道の両側に店を構える「五人百姓」。
参道の両側に店を構える「五人百姓」。 一人ひとり、同じ飴を同じように販売しています。
一人ひとり、同じ飴を同じように販売しています。 古くは、神社へのお供えもののお米を使ってつくられていたという「加美代飴」。付属の小さなトンカチで割っていただくそう。
古くは、神社へのお供えもののお米を使ってつくられていたという「加美代飴」。付属の小さなトンカチで割っていただくそう。ちょっと代わりに行ってきて。こんぴら狗の「代参」ものがたり
 「こんぴら狗」の銅像。
「こんぴら狗」の銅像。
さらに進んで石段を数十段登ると、右手にキャラクター感のある銅像が。この「こんぴら狗」の銅像はイラストレーターの湯村輝彦さんのデザイン。ではここで「こんぴら狗」のお話を。
冒頭でお話したように、江戸時代「こんぴらさん」へのお参りは庶民のあこがれであり、人生の一大イベントでした。江戸から四国の「こんぴらさん」への旅は海を越え山を越えていく大変なものだったので、当人に代わり、旅慣れた人に代理参拝をお願いすることがあったそうです。これが「代参」。
かつて森石松が、清水次郎長の代わりに「こんぴらさん」へ代参し、預かった刀を奉納したと伝えられています。
この代参、実は人だけではなく、なんと犬が飼い主の代わりに参拝することがあったのだそうで。犬は首に「こんぴら参り」と記した袋を下げて四国を目指します。
袋の中には、飼い主を記した木札、初穂料、道中の食費などが入っていて、犬は旅人から旅人へと連れられて、街道筋の人々に世話をされながら「こんぴらさん」にたどり着きました。
この、こんぴら参りの代参を務めた犬が「こんぴら狗」と呼ばれていたそうです。当時は飼い犬に代参を頼んでまで「こんぴらさん」にお参りをしたいという強い思いがあったのですね。
御本宮まで、あと少し。
 「こんぴら狗」左手の広場にある馬屋。
「こんぴら狗」左手の広場にある馬屋。金刀比羅宮の馬屋には神さま専用の馬である「神馬(しんめ)」が居ます。神馬は神さまの馬なので、人は乗せてはいけません。これまでも人を乗せていない馬でないと、神馬になれないのだといいます。
白い道産子馬の神馬「月琴号(げっきんごう)」。この日は馬屋で会えましたが、朝早くに付近を散歩していることもあるのだそうです。
 白い毛の「月琴号」は現在12歳。人間でいうと、40代半ばなのだとか。
白い毛の「月琴号」は現在12歳。人間でいうと、40代半ばなのだとか。円山応挙の襖絵が公開されているという「書院」や、日本洋画の開拓者とされる高橋由一の作品を収めた「高橋由一館」など、歴史的な美術品も豊富な金刀比羅宮の境内。
さらに進むと国指定重要文化財の「旭社」が。ここまでで石段628段。ずいぶん登ってきたので、目の前の立派な建物に、「これが御本宮か!」と思ってしまいそうですが、御本宮まではまだもう少しです。
「旭社」は江戸時代天保年間に、金毘羅大権現の金堂として建立されたもので、高さ18メートル、銅板瓦の総檜造二重入母屋造。この時代の腕の良い宮大工が琴平に集められ、鳥獣や草花などの華麗な装飾がほどこされたのだそうです。
 「旭社」では、屋根裏や柱などの装飾彫刻を堪能。
「旭社」では、屋根裏や柱などの装飾彫刻を堪能。 「旭社」の扁額は、正二位綾小路有長の筆。
「旭社」の扁額は、正二位綾小路有長の筆。 「旭社」を超えて、あと少し。この急な階段を登りきれば御本宮が!
「旭社」を超えて、あと少し。この急な階段を登りきれば御本宮が!785段!ついに御本宮へ
 つ、着いたー!ようやく785段の石段を登りきり、御本宮です。
つ、着いたー!ようやく785段の石段を登りきり、御本宮です。「こんぴらさん」のメイン、御本宮にいよいよ到着です。象頭山の中心に鎮座する金刀比羅宮。象頭山は、瀬戸内海を航行する人々の目印でもあったため、金刀比羅宮は海の守護神として、人々に愛されてきました。
この辺りの山々は古くから霊場として知られており、たくさんの寺社がありましたが、江戸時代から金毘羅大権現がひとまとめに統括。ご祭神は大物主神(おおものぬしのかみ)と崇徳天皇で、海の神さまのほかにも、 農業、殖産、医薬などさまざまな神さまとして親しまれています。
主役である御本宮は、江戸時代は朱に彩られ豪華絢爛な装飾があったそうですが、明治以降は現在のような素木造りの社になったのだそうです。
 御本宮拝殿は檜皮葺(ひわだぶき)の大社関棟造。全て角材が用いられ、一切弧をなしていないというのが他にない特徴なのだそう。
御本宮拝殿は檜皮葺(ひわだぶき)の大社関棟造。全て角材が用いられ、一切弧をなしていないというのが他にない特徴なのだそう。「二礼、二拍手、一礼」。決して楽ではない785段の石段を登ってたどり着き、その達成感もあいまってすっきりした気持ちで参拝しました。
金刀比羅宮の「まるこん」
 ふと横を見ると、御本宮の傍には大きな提灯が。
ふと横を見ると、御本宮の傍には大きな提灯が。この「金」の字は、御社紋(ごしゃもん)という、いわゆる神社の紋で「まるこん」と呼ばれて親しまれているそう。「金」の字を隷書体(れいしょたい)で表したものです。
そういえば、参道のお土産やさんで販売されていたうちわにも、○の中に「金」の字が書かれていましたがこの字体ではありませんでした。それもそのはず、本来の「まるこん」は、この御宮と直轄の6社だけが使えるのだそうです。
 参道のお土産物やで販売されていたうちわ。まるに「金」の字ですが、御本宮の提灯とは字体がちがいます。
参道のお土産物やで販売されていたうちわ。まるに「金」の字ですが、御本宮の提灯とは字体がちがいます。香川の伝統工芸品として「丸亀うちわ」がありますが、実はこの「丸亀うちわ」が栄えたのには、江戸時代の庶民のあこがれ「こんぴら参り」のお土産として、「金」の字が入ったうちわをつくったのが始まりだったといいます。
当時は「金」の字の入ったうちわをお土産として持って帰ることも、大きなステータスだったのかもしれません。その土地の伝統工芸として根付かせるぐらいの力があったということから、「こんぴらさん」の相当な人気が伺えますね。
ご利益たっぷり!「幸福の黄色いお守り」と、犬の縁起物
さて、御本宮の隣には神札授与所が。ここで人気なのは「幸福の黄色いお守り」。金刀比羅宮の色である鮮やかな黄色のお守りです。
鬱金(うこん)からとれる染料を使って染められた糸で織られ、ていねいにつくられているお守りだそう。私は「ミニこんぴら狗」とのセットをいただくことに。
 神札授与所。お札やさまざまなお守りが並びます。
神札授与所。お札やさまざまなお守りが並びます。 「幸せの黄色いお守り」と「ミニこんぴら狗」のセット。こんぴら狗は磁器製でずっしり。
「幸せの黄色いお守り」と「ミニこんぴら狗」のセット。こんぴら狗は磁器製でずっしり。 「ミニこんぴら狗」を讃岐平野に掲げて。
「ミニこんぴら狗」を讃岐平野に掲げて。 御本宮の北東側は展望台になっており、讃岐平野の彼方に瀬戸大橋や讃岐富士などを望めます。
御本宮の北東側は展望台になっており、讃岐平野の彼方に瀬戸大橋や讃岐富士などを望めます。ちょっと気になるおみくじを発見。「こんぴら狗の開運みくじ」は、初穂料100円をお賽銭箱か狗の首の袋にいれると、おみくじをいただくことができます。可愛い袋の中には金色の小さな狗のお守りも入っています。
 「こんぴら狗」がたくさん。大きな狗の背中におみくじが入っています。
「こんぴら狗」がたくさん。大きな狗の背中におみくじが入っています。 金色の狗のお守りはお財布などに入れて持ち歩くのが良いそう。
金色の狗のお守りはお財布などに入れて持ち歩くのが良いそう。御本宮の参拝の後、さらに山を登る奥社へも足を運ぶとトータルで1368段の石段を登ることになります。
霊験あらたかな奥社は空気がきりりと引き締まる感じ、山道の静かな樹木の間、石段をただただ無心に登った先には、奥社・厳魂神社が鎮座しています。健脚の方はぜひ。(もちろん私も参拝しました!)
年間に約400万人もの人々が訪れるという金刀比羅宮。長い長い石段は決して楽なものではありませんが、その道中で繰り広げられる大小のエンターテイメントの数々は、石段を登るひざの痛みを和らげ、あがった息をも整えてくれるような気がしました。
長い石段は人生のようなものかもしれません。あわてずに、一段一段。ふとひと息ついて、足元から目線をあげてみると、こころが喜ぶような自然や、「こんぴらさん」のもつ魅力にたくさん出あえそうです。
———と、人生を語るのはまだ私には早かったようで、翌日からひどい筋肉痛の日々ではありましたが、とにもかくにも、まだまだご紹介しきれなかった魅力が満載の、讃岐「こんぴらさん」。一生に一度はぜひお参りを。
<取材協力>
金刀比羅宮
香川県仲多度郡琴平町892-1
0877-75-2121
http://www.konpira.or.jp
文・写真:杉浦葉子
こちらは、2017年4月5日の記事を再編集して公開いたしました