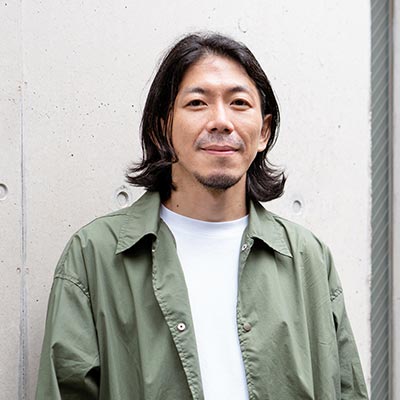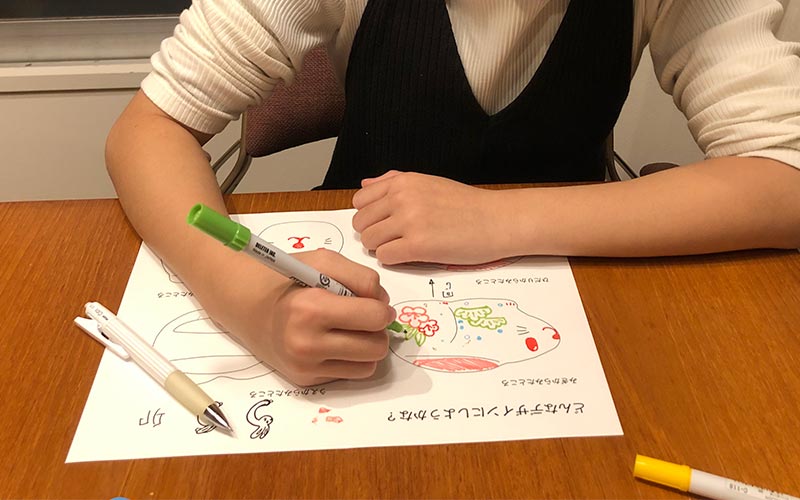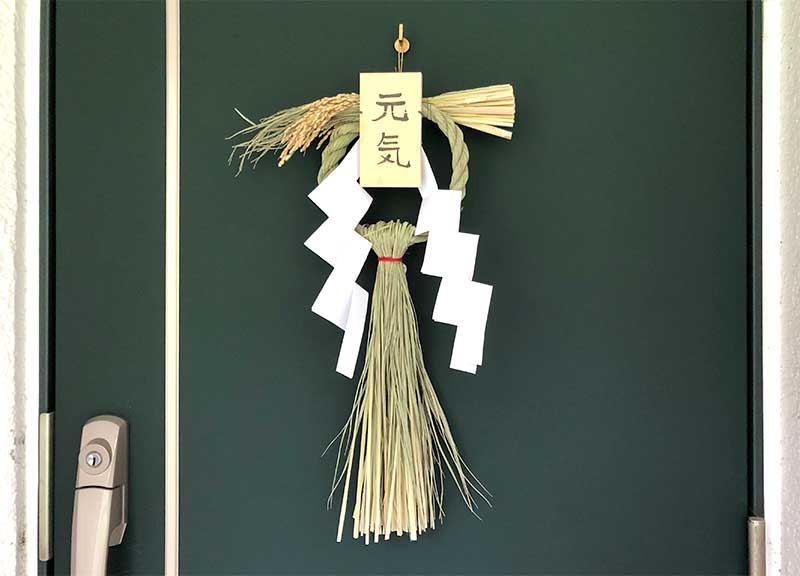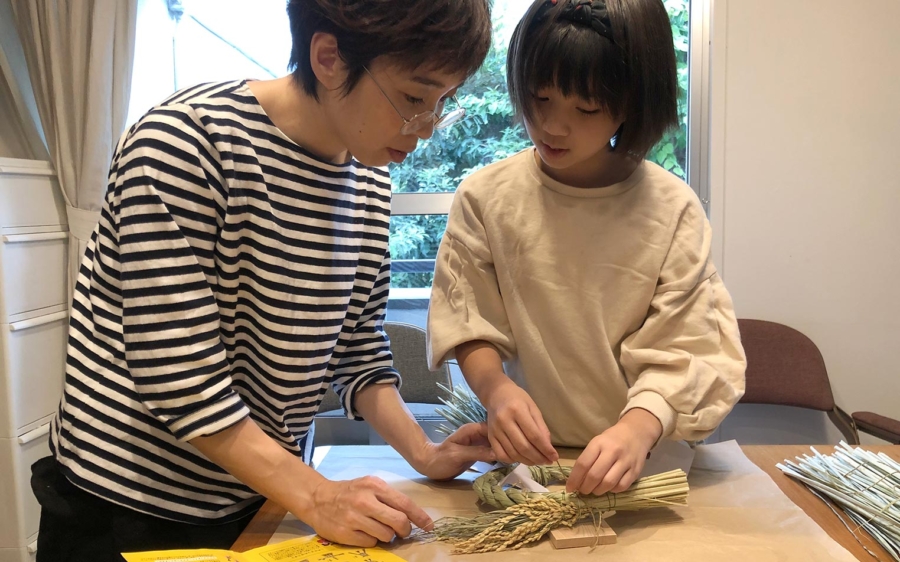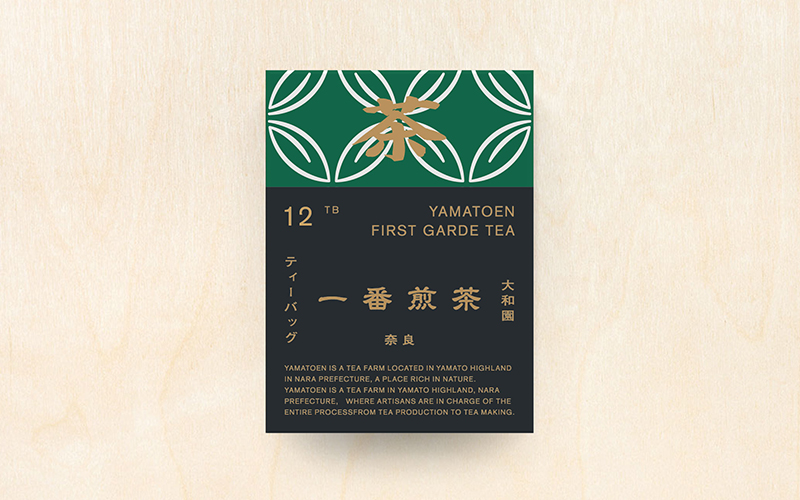いよいよ師走にはいり、今年も残りわずかとなりました。
慌ただしく過ぎていく時期でもありますが、皆さまいかがお過ごしですか?
年の切り替わりって、やっぱり気持ちの上でも特別なものですよね。
今年1年を振り返ってみたり、新しい年に向けての豊富や目標を立ててみたり。
新年を機に改める、そんなタイミング。
新しいこと、と思うとなんだか気負ってしまいますが、日々の暮らしをちょっと見直してみるだけでも、気持ちが一新されるような気がします。
そこで今日は、中川政七商店の定番商品の中から、私たち自身が、日々使っていて心地好い道具をお届けしたいと思います。
全国のスタッフが、実際に愛用している推し商品に投票してみました。スタッフみんなの「好きなもの」を、前後編に分けてお届けします。
前編では、「食」の道具をスタッフの愛着コメントとともにご紹介します。
・台所道具
・食卓の道具
・食品
では、早速どうぞ。
台所道具編
1位:スタッフ愛用率No.1の暮らしの道具「花ふきん・かや織ふきん」

もはや殿堂入りと言った方が正しいかもしれません。
スタッフ使用率No.1。私たちの代表商品です。中でも、大判薄手の「花ふきん」は特別。ふだん「かや織ふきん」を使っているという方にも、ぜひ一度使っていただきたい、中川政七商店一の推し商品です。
スタッフのコメント
「拭き掃除が苦痛から楽しみに変わる!道具を変えると暮らしが心地好くなる象徴的な商品だなと思います」
「今年から台所や洗面所の手拭きとしても使い始めて、改めて肌触りのよさ、乾きの速さを実感。より一層大好きになりました。
家に知人が遊びにきた時に必ず “このタオルいいね!”と言われます。“タオルじゃなくてふきんなんだよね”というと毎回驚かれます」
「我が家は家に置くものの色数を絞っているので、白百合と竜胆(りんどう)の2色を使っています。台所に白と紺がキリっと並んでいる佇まいが好みです。
花ふきんの白百合を食器用、竜胆を手拭き用に。かや織ふきん よろけ縞の紺を台拭き用に。使い分けることで分かりやすく、夫や子供も間違えずに使ってくれています。
古くなったふきんは、目印をつけて雑巾に。竜胆の紺は、雑巾にしても汚く見えないので、その点も気に入っています」
「スペースの節約のため水切りカゴを使っていない我が家。ふきんの上に家事問屋の食器立てを置いていますが、放置しても全く臭くならないんです!速乾性が高いので、使う場所を選びません」
「かや織ふきんは可愛い柄が出る度に購入しています。飲食店を経営する知人に贈っても好評で、お店で活用してくれています」
「趣味を問わないため、ふきんは、ちょっとした贈り物にも最適です。花ふきん、かや織ふきんのストックは常にたっぷり持つようにしています」
2位:この商品は発明だと思います!「二重軍手の鍋つかみ」

スタッフのコメント
「これを使い始めてから熱い思いをしたことがありません。土鍋を持つときにも5本指でしっかり持てて安心です!使うたびによさを実感します」
「レンジから取り出す時に、使いやすさを実感します。
つかむ蒸し皿や焼き皿も決して安いものではないので、指先が使いやすくしっかり持てる
鍋つかみだと安心してレンジから器を取り出せます」
「母にプレゼントしました。5本指でしっかりと掴めるのがいいと気に入ってくれています」
「五本指でしっかり掴めて安心。熱さも感じずバッチリです。“軍手が一番熱さに強い”というストーリーも、使っていてとても納得感があります」
3位:“へたらなすぎて替え時がわからない!”の声が続出「抗菌キッチンスポンジ」

スタッフのコメント
「買い替えタイミングがわからないほど、丈夫で長持ちします。
今年の梅雨時に、1年使ってようやく買い換えました。新品と比べてやっとへたっていることがわかるくらいです(このスポンジと出会うまでは、月一でスポンジを買い換えていました)。
そして何より嫌な臭いが残らないのは清潔感があって本当に魅力です」
「泡立ちのよさ、水切れのよさ、へたりにくさ、の三拍子が揃って愛用中です。スポンジを頻繁に買い替えていたことを後悔するほど…早く購入しておけばよかったと感じます」
「本当にへたらない!へたらなすぎて使い終わりが分からない。THEのキッチンスポンジと合わせて我が家では二刀流で使用しています。どちらも本当に丈夫です」
「半年ほどこまめに熱湯消毒をしながら使い続けましたが、替え時がわからないほどにクタクタにもモロモロにもなりません。我が家の救世主です」
「色んな人から“これはすごい”と聞いていましたが、実際使ってみるとあまりのへたらなさに驚きました。クタクタのスポンジでは洗った気にならないので、いつでもしっかりしてくれるスポンジに頼もしさを感じています」
4位:いつの間にか食器寄りの一軍選手「波佐見焼の保存の器」

スタッフのコメント
「台所のすぐに手の届く場所に大中小を置いてます。常備菜を入れるつもりで買ったけれど、もっと食器寄りの一軍選手です。ちょっと残ったおかずを入れて次の日のお弁当のおかずにしたり、塾で帰ってくるのが遅い娘のごはんを取り分けたりと、ことのほか便利。色は白を持ってますが、どんなおかずもおいしそうに見える色です」
「保存の器は見た目にすっきりで、開け閉めが蓋をのせるだけなので便利です。」
「そのまま食卓に出せるシンプルデザイン。プラスチック製の容器だと温め直した後に色がついたり、油が落ちにくかったりしますが、陶器なのでそれがありません」
5位:これ1本で取りまわせる、毎日の料理の相棒「最適包丁」

スタッフのコメント
「もうこれ一本で日々取り回せてて、私的最適。台所の相棒です」
「初めて使った時、素晴らしい切れ味に思わず声がでました!」
「最適包丁は取り回しやすいコンパクトなサイズ感がとても使いやすいです!
洋にも和にも寄りすぎず、洗練されながら素朴さもある。バランスが絶妙で安心して使えます。直線的で素直なデザインも素敵な佇まいです。
毎日使っていて柄の塗装が薄くなってきたので、自分で蜜蝋を塗ってメンテナンスしようと思っています。先日近所の研ぎ屋さんに出したら、ピカピカになって帰ってきて、より愛着が増しました」
「これまで使っていた包丁に、特別困っていたわけではありませんが、たしかにちょうどよさそうなサイズ。
使ってみると、これまでペティナイフを使っていたようなシーンで大活躍!もちろん普通の包丁としても使いやすいので、毎日この1本でまかなっています」
食卓の道具編
1位:毎日使うから、洗いやすさ“も”大事「ごはん粒のつきにくい弁当箱」

スタッフのコメント
「弁当箱は2個持っていて、妻と揃いで使っています。たまに蓋を入れ替えて、バイカラーの弁当箱にしても楽しいです。
何より洗うのが楽なので、日常使いには非常に重宝します」
「これを購入するまでお弁当箱の迷走が続いてました。購入してから3~4年ほど経ちますが、ずっと飽きずに使い続けています。お昼ご飯はしっかりと食べたいので、600ml入るところも推しポイントです」
「機能性とシンプルなデザイン、和洋中どんなメニューでも詰めやすい点が気に入り愛用しています」
「お弁当箱にごはんの跡がつくのが本当にストレスでしたが、全然付かないし洗いものも楽すぎます!!詰めやすい形状も最高です!」
「サッと汚れが落ちるので嬉しいです。疲れて帰った後に助かります」
2位:選ぶのが楽しい日本のうつわ「産地のうつわ きほんの一式」

スタッフのコメント
「美濃焼の平皿を使用しています。パスタにカレーにワンプレートランチにメインディッシュになんでもござれ。もともと美味しい家人の料理がより一層美味しくなります」
「お気に入りのうつわでごはんを食べると、より一層料理が美味しくなります。釉薬の個性や手ざわりの違いから好きなものを選ぶ楽しさもあります」
「有田焼の飯椀を使っています。磁器なので、軽く、目止めのお手入れをせずとも使えるのが嬉しいポイントです!有田焼きの白と藍のシンプルな見た目なのですが、個人的にこの配色がご飯を美味しく感じるので好きです!」
「信楽焼のこっくりした色味がとてもお気に入りです。少しずつ集めているので、早く揃えたいです!」
「美濃焼の小皿を使っています。小さすぎず大きすぎない丁度良いサイズが、お気に入り。かいらぎや土灰の釉薬は、全体的に渋めな印象ですが、一つひとつの表情が豊か。個人的に、美濃焼のシリーズが一番好みです」
「益子焼のマグカップを持っています。ぽってりとしたフォルムが癒されます。また、口にフィットして飲みやすいです。
益子焼は、シリーズの中でも一番個体差がある食器だと思います。なので我が家のひとつを選ぶのがより楽しくもあります」
「素朴な作りで飽きがこない!どっしり重厚感があるところもお気に入りです!」
3位:佇まいはそのままに、負担なく毎日使える「食洗機で洗える漆椀」

スタッフのコメント
「中サイズを日々のお味噌汁用に使っています。ものすごく品よく美味しそうに見えます。低さもいい感じで引き出しの食器棚に入れやすいのも◎できることなら全サイズそろえたい!」
「触った時の、なめらかな手ざわりが大好きです。漆器でも物によって色んな手ざわりがあると思いますが、マットでなめらか。口当たりがとてもいいんです。中サイズを使っていますが、深すぎず浅すぎない形状もちょうどいい!丁寧に作られているものの使いやすさを実感します」
「気軽に使えて、家庭料理がワンランクアップします!」
「一般的な漆器に比べて手入れが楽なので、気持ちの負担も少なくついつい手が伸びます。漆器の品のある佇まいで、食事が美味しく感じます」
4位:0.1ミリ単位の箸先の仕上げが使いやすい!「拭き漆のお箸」

スタッフのコメント
「拭き漆の箸は、箸先にきちんと面がとってあるのが肝で、豆などつかみにくいものが非常につかみやすく、箸捌きが上手くなったと錯覚します」
「細めで繊細なところがお気に入り。使いやすいのでリピートしています」
「先がかなり細く仕上げられているのに、丈夫でとても使いやすいです。もう何年も毎日の食事に使っています」
「茶をつかってます。同色の店頭サンプルが、良い感じの色になってきているのですが、我が家のも同じように育ってきました!」
5位:気軽に遊べる食卓の味方「産地のうつわはじめ(豆皿)」

スタッフのコメント
「お皿の色は白がきほん。際限がないから、土ものには手を出さない!と夫婦で決めているのですが、豆皿で遊んでいます。
ちょっとお漬物を盛ったり、薬味を入れたり。小さなものの取り皿兼用で箸置きとして出したりと、使い道はさまざま。たくさん揃えているので、季節ごと、乗せるものに応じて選べるのも楽しいです」
「有田焼の豆皿を使っています。豆皿に小分け作戦で、バランスよく食べさせることで、息子の好き嫌いの克服に役立ちました。3歳の頃からもう4年近く使っていますが、磁器なので割れにくく、今でも現役です」
「ワンプレートに美しく盛る、お弁当箱にきれいに詰めるなど、組み合わせて美しく盛るのが苦手な私。豆皿やそば猪口など小さいうつわにちょっとずつ盛ることで、料理の見栄えを担保しています。我が家の食卓に欠かせない道具です。
さまざまな色柄のうつわを使うので、ごちゃごちゃしすぎないよう、素地が白い有田焼の豆皿を使う機会が多いです。淵の茶色がいい塩梅です」
食品編
1位:大らかにいれられるから、気付いたらこればかり「番茶」

スタッフのコメント
「番茶なのにこんなに種類があることに驚きです!渋みが少ないから飲みやすいし、定番の四種どれもおいしくて飲み飽きません」
「番茶シリーズは、水出しできるところ、簡単にいれられるところ、季節感があるところ、味を選びながら毎日楽しめるところ…好きなところを挙げたらキリがありません!」
「お湯でも水出しでも美味しくいただけるので、番茶ばかり手に取ってしまいます。季節ごとに出る味はハーブティーのように楽しめるものも多く、毎シーズンの発売が楽しみです!」
「茶の木番茶の香ばしいところが好みで日常使いで楽しんでいます。3個セットにして気軽なギフトにできたりと、贈りもののシーンにも大活躍。大人から子供まで安心して飲めるというのもうれしいポイントです」
「定番の四種の中では、茶ノ木番茶が大好きです。とくに秋冬はほっこりしたやさしい味わいが美味しい。味だけでなく、身体が美味しいと思うものってあるんだなと感じます」
「夏場はほぼ毎日水出しの青柳番茶を飲んでいました。すっきりした味わいが大好きです」
2位:フリーズドライなのに、贅沢な味わい!「汁物シリーズ」

スタッフのコメント
「何よりもまず、美味しかった!が一言目に出てきます。フリーズドライなのに、具の食感も残っており、特に里芋のほろっと崩れる食感には感動しました…!」
「選ぶのが楽しい味の種類!
汁物シリーズは300円代でしっかり食べ応えのあるスープが飲めて魅力的だと思います!一袋300円というと少しお高いと感じるかもしれませんが、日頃頑張っている自分のご褒美に買うと嬉しくなります」
「朝食はパン派なので、手軽に美味しいスープが食べられて便利!朝食の満足度が増します」
「手軽に食べられて美味しい!特にクラムチャウダーが好きで、貝と酒粕とクリーム、野菜の甘みのバランスがよく、美味しいです」
「パッケージのデザインも素敵でギフトにしやすい!何度もプレゼントしています」
3位:ぬか床をはじめる人続出。初心者に優しい「ぬか床」

スタッフのコメント
「ゆずと花椒のぬか床は、さわやかな柚子の香りで癖がなく食べやすい。
にんにくと唐辛子のぬか床はにんにくの風味と味がしっかり効いているので、ごはんがどんどん進む美味しさです」
「人生で初めて漬物を自分でつけた、ぬか床は初心者の私にも扱いやすかったです。また、手軽にごはんのお供を一日で作れてしまう革命的な出会いでした」
「ゆずと花椒のぬか床を愛用しています。夏場は家庭菜園で育てたきゅうりをぬか漬けにして、美味しくいただきました。」
「ぬか床初心者でも美味しく始められます。おすすめの食材について、スタッフやお客さまと情報交換することが楽しいです。私のお気に入りはミョウガです」
「どちらの味もそれぞれ別添の香辛料がついているので、調整して自分好みの味に仕上げれます。腸活にもおすすめ。にんにくと唐辛子のぬか床に、ゆずと花椒の足しぬかを混ぜて使っても美味しいです」
4位:一度食べるとリピート確定?「吉野杉桶造純米酢のマヨネーズ」

スタッフのコメント
「こちらに変えてから今まで使っていたマヨネーズは味気なく感じてしまい、買っていません!それほどハマってしまった商品です!
卵の味がしっかり感じられ濃厚さがありますが、甘ったるさはなく素材の味が活きていてこれだけでも充分美味しい!野菜スティックにちょっとつけるだけでもう、絶品です!
私はいぶりがっこと大葉、クリームチーズで作る大人のポテサラの味付けにこのマヨネーズが一役かっています!
あとは炒め物でマヨソテーで何でも合います!」
「高いマヨネーズに手を出したことがなく、どんな味がするんだろうと気になっていました。
まずは、一口食べてびっくり!これだけで美味しい!卵の香りもあり、全体的にまろやか!からしの効果か、少し和風ベースの香りが漂う。面白いなぁと思いました!
すくった時もトゥルンとしていて、それだけで食べてしまいそう。今までに経験したことがないマヨネーズで驚きです!」
「マヨネーズは、ブロッコリーなど茹でただけの野菜の味もぐっとひき出して美味しいです。
マヨネーズによくある油っぽい重さを感じないのに、他の調味料と混ぜてもしっかり存在感を感じます」
「もともとマヨネーズの酸味があまり得意ではない私ですが、このマヨネーズはツンと来ず、食べやすいです!そのまま舐めても美味しい卵のふくよかな味わい。白だしで作る和風ポテトサラダと相性良しです!」
「マヨラーですが、人生最高のマヨネーズに出会い、常備しています」
5位:レトルトとは思えない具材の食感!「産地のカレー」

スタッフのコメント
「レトルトとは思えない具材の食感やルーのとろみなど、それぞれが他にはない特徴が素敵です!癖が少なくふとした時に食べたくなり、ついついリピートしてしまいます」
「日本の食文化を知るきっかけになり、バリエーションがあるので選ぶのも楽しい!ひとつ試すと、次はあっちを試してみようという気持ちになります」
「いろんな種類があってどれもおいしく、手土産にも最適です」
「土地ごとの味ということで話もふくらみますし、辛みが強くないので、人にプレゼントしやすいです。聞いたことない味だったりするけど、意外と癖も強くない。
とくに、瀬戸の手羽先八丁味噌カレーと大分の胡麻と鯖カレーはごろっと具材が入っていて、贈りものにすると喜ばれます」
以上、「食」の道具編をお届けしました。
好きなものの情報交換って楽しいですよね。
私も、皆のコメントを読んでるうちに色々欲しくなってきてしまい、二重軍手の鍋つかみとマヨネーズとスポンジを購入してみました。
二重軍手の鍋つかみは両隣のスタッフからのプッシュがすごかったのですが、確かに安心感抜群です!秋冬は鍋やグラタンなど熱々料理が多いので活躍しそう。あれ作ってみようかな~など、道具から料理が広がっていくのが楽しいです。
身の回りの暮らしの道具をアップデートすると、少しずつ毎日の暮らしが楽しくなるのを実感します。家を購入した友人にも贈ろうかと検討中です。
次回は、「衣・住」の道具編です。お楽しみに。
<掲載商品>
花ふきん・かや織ふきん
二重軍手の鍋つかみ
抗菌キッチンスポンジ
波佐見焼の保存の器
最適包丁
ごはん粒のつきにくい弁当箱
産地のうつわ きほんの一式
食洗機で洗える漆椀
拭き漆のお箸
産地のうつわはじめ(豆皿)
番茶
汁物
ぬか床
吉野杉桶造純米酢のマヨネーズ
産地のカレー
あわせて読みたい
【わたしの好きなもの】年末スタッフ投票「食の道具」編