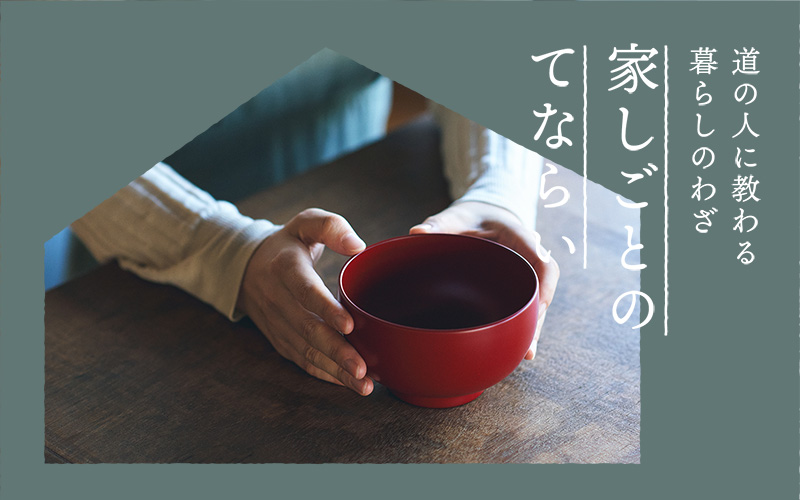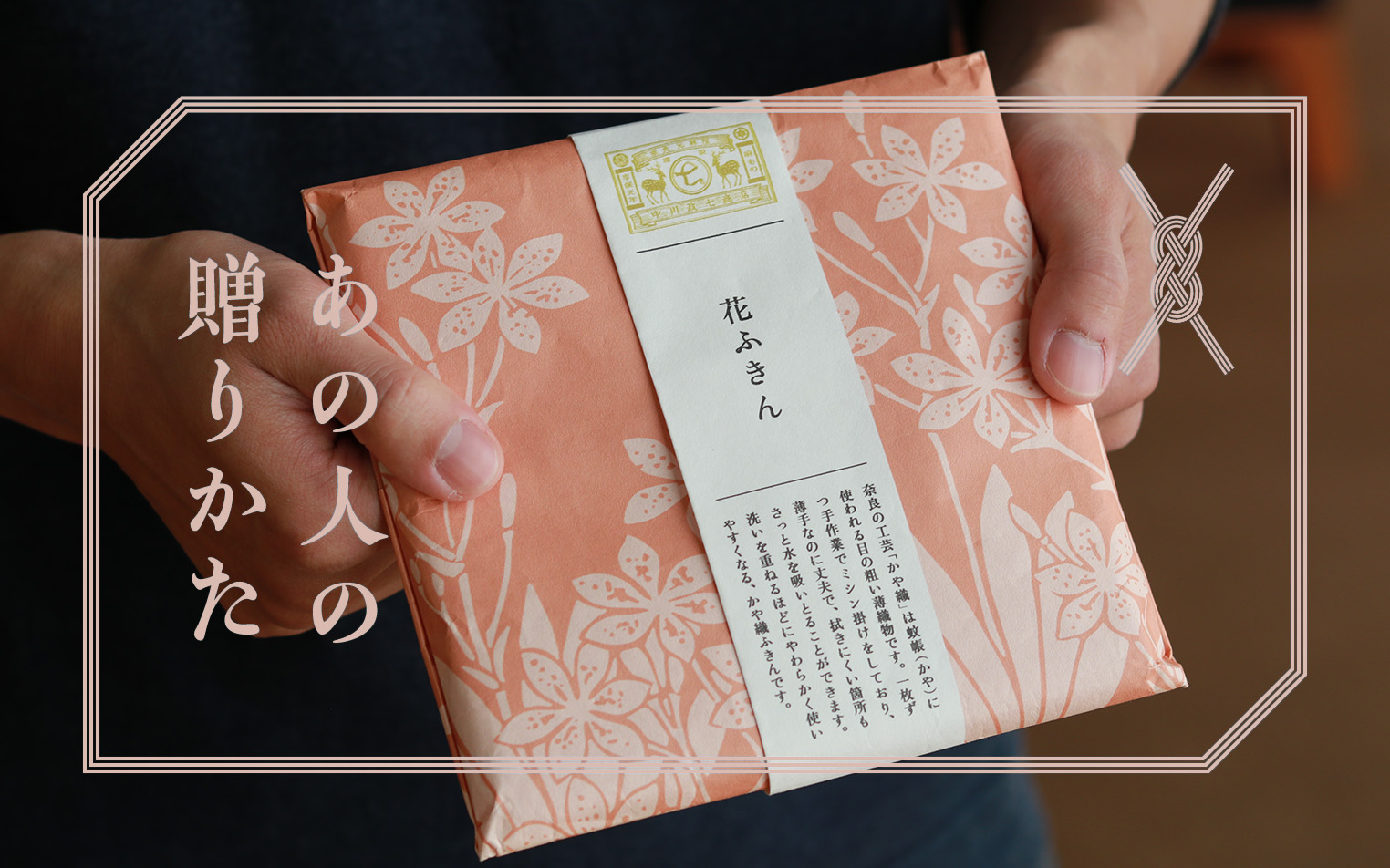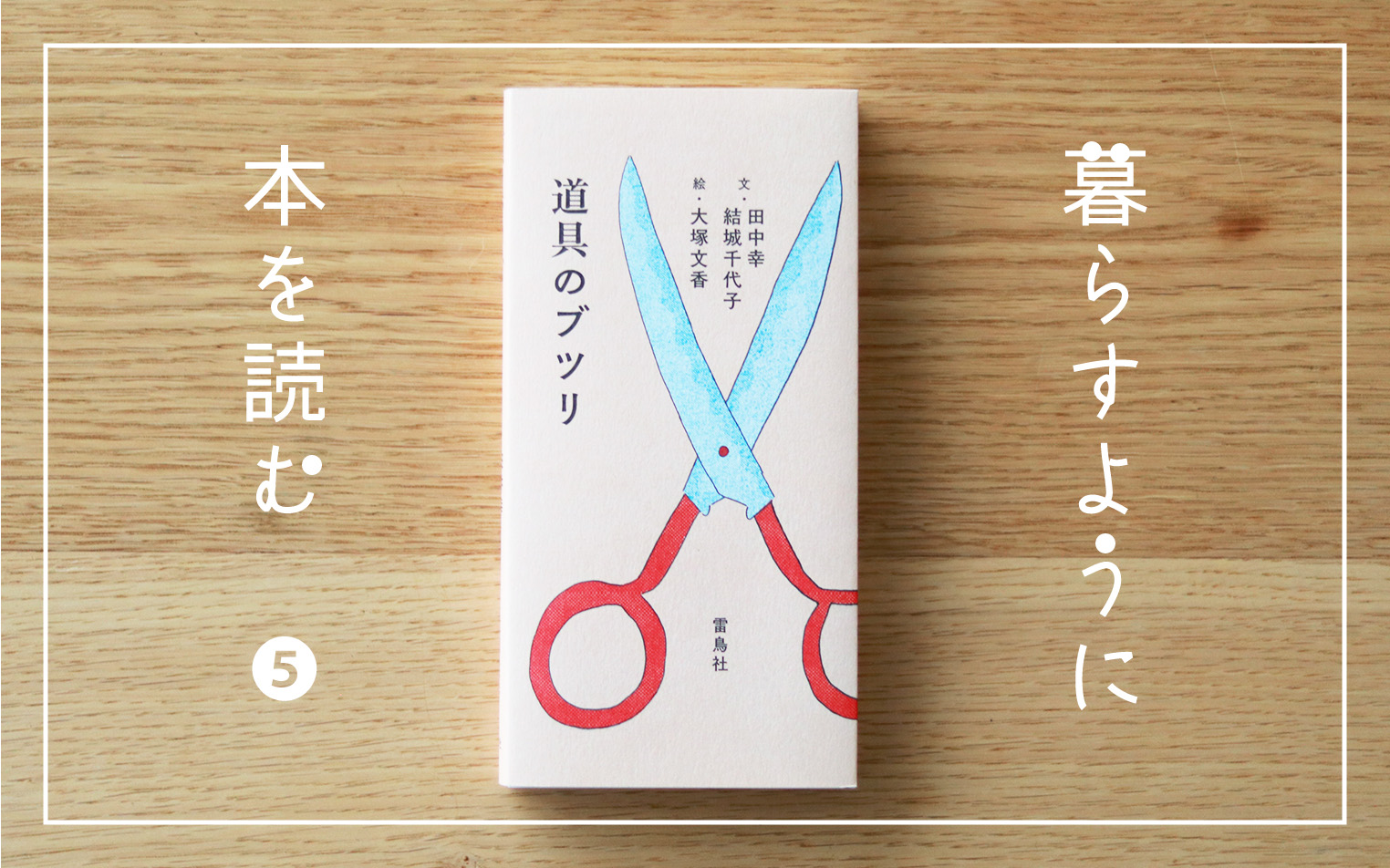毎日の家しごと。それなりに何とかできるようになり、だいたいは心得たつもりだけれど、意外と基本が疎かだったり、何となく自己流にしていたりするものってありませんか?
そのままで不都合はないものの、年齢を重ねてきたからこそ、改めて基本やコツを学んでみたい。頭の片隅にはうっすら、そんな思いがありました。
この連載では、大人になった今こそ気になる“家しごとのいろは”を、中川政七商店の編集スタッフがその道の職人さんたちに、習いに伺います。
とはいえ、難しいことはなかなか覚えられないし、続きません。肩ひじ張らず、構えずに、軽やかに暮らしを楽しむための、ちょっとした術を皆さんにお届けできたらと思います。
今回のテーマは「漆器を扱いこなす」。越前漆器の老舗・漆琳堂の8代目当主であり、越前漆器伝統工芸士の内田徹さんを講師に迎え、編集チームの谷尻が習いました。
今回の講師:漆琳堂 代表取締役社長 内田徹さん

1976年福井県生まれ。 大学卒業後に家業で今年で230年目を迎える漆琳堂に入社。 10年余り祖父・父から漆器製造の下地・塗りを習い、 産地最年少で越前漆器伝統工芸士に認定される。 2019年漆琳堂の代表となり、現在に至る。
https://shitsurindo.com/

そもそも、漆とは
漆とは、ウルシの木の樹液を原料とする天然塗料のこと。自生しているウルシを傷つけることで樹液が流れ、それを集め精製して作ります。
人間がケガをすると血が出て、治癒に向けてかさぶたが出来るのと同じで、ウルシの木も傷がつくと樹液を流し、傷を修復するために固まる性質を持ちます。これを利用してうつわの塗膜として塗ったり、金継ぎのように接着剤として使われたりするのです。
 ウルシの木(撮影:廣田達也/読みもの「漆は甘い、のか」より)
ウルシの木(撮影:廣田達也/読みもの「漆は甘い、のか」より)
国内の漆は95%ほどが中国産、5%ほどが日本産。原料価格の安いことが理由ではなく、その質や採れやすさなどの理由で、100年以上前から中国産漆は使われてきました。ちなみに、日本産の漆は岩手県や茨城県で採られます。
漆の産地が中国や岩手・茨城にありながら、日本における漆器の産地は石川県(輪島塗・山中塗)や福井県(越前漆器)など、別の場所にあります。これは、漆の精製技術がそれらの産地ですぐれていたこと、また漆は湿気で固まるため、曇天で湿度の高い日が多い東北や北陸の地域に産地が集中したからといわれます。
内田さん:
「実は漆器は陶磁器と違い、材料や見た目、作り方が産地ごとに大きく異なるわけではありません。それは木地屋さん(きじや:木を削り、塗る前のうつわを作る職業)が全国の山を渡り歩いて漆器を作っていたことや、陶磁器のなかった時代にどの地域でも木を削って漆器を食事に使っていたことが主な理由です。ただ、越前漆器の場合は日用品や業務用、山中漆器だとギフト用、輪島塗だと美術工芸がそれぞれ多いなど、発展の仕方に傾向はありますね」

漆器のよさは、熱の伝導率が低いので熱いものを入れてもうつわが熱くならないこと。熱いものは熱いまま、冷たいものは冷たいまま食べられます。また陶磁器に比べて軽くて割れにくいのも漆器ならでは。漆を塗ることで強度が増すため、丈夫で長持ちするのも嬉しいところです。
一般的には汁物用としてのお椀のイメージが強いものの、かつてはご飯をよそう際の飯椀としても多く使われており、ご自身も家では漆器にご飯をよそっている、と内田さん。
「漆には衛生的にも効果があると言われており、洗い残した部分があっても菌が増えにくいという研究結果もあるようです。昔からお正月には漆器の重箱が使われますが、それももしかしたら、料理が長持ちする実感があったのかもしれませんね」
参考:うるし振興研究会による検証結果
育ていけるのが、漆器の楽しさ
また徐々に固くなっていく性質も、漆の特徴の一つ。一般的な化学塗料の場合は塗った日が一番美しく、その日から劣化の始まるものが多いのですが、漆の場合は「100年かけて硬化する」といわれています。つまり、私たちが手にする漆器はまだ育つ過程のもの。次の世代へ渡ったときが、一番ベストな状態かもしれません。
内田さん:
「最近嬉しかったのは、お客さまから修理の依頼をいただいたうつわの育ち方。中川政七商店さんの『食洗機で洗える漆椀』の塗り直し依頼だったのですが、手元に届いたものを見て、表面にツヤが増しているサマがすごくいいなと思いました。恐らく、ふきんなどで水分を拭き取ったりしているうちに漆の粒子が磨かれ、ツヤが出てきたんだと思います。大切に使ってくださったんだなって、とっても嬉しい気持ちになりました。お客さまに『新品をお渡しするんで、これはうちに頂けませんか?』と申し出たくらいです。
もちろん塗り直しで新品同様の見た目にもできますが、うつわの表情が変わっていくのも育てる楽しみの一つです」
 左が5年間使用されたお椀、右が新品
左が5年間使用されたお椀、右が新品
【漆器を扱いこなす】其の壱:選び方
漆の基本を押さえたら、次に選び方を伝授いただきます。せっかく迎えるからには、自分にとってのベストなものを選びたい!どんな視点で求めるとよいのでしょう。
サイズ
まずは意外と難しいサイズから。日本料理店ではお吸物のお椀として、4寸(直径約12cm)が基本とされています。両手の親指と人差し指でお椀にちょうど手が回るくらいが、4寸の目安。
一般家庭でも昔はこのサイズを使うことが多かったそうですが、ただし、それはごはんと汁物、香の物が献立の主だった頃のこと。今はそこにハンバーグや野菜炒めなどのおかずも付く場合が多いため、お椀を4寸にすると献立全体の量を多く感じるかもしれません。
ご自身の食べられる量にもよりますが、今は汁物専用の場合、直径約11~12cm(3.6寸以上、4寸以下)のものを使うことが多くなっています。
内田さん:
「4寸だと具だくさんの豚汁とか、ちょっとした丼に合うサイズですね。5寸(直径約15cm)くらいだとうどんのような麺類に合うサイズになってくる。とはいえ、小さいと汁物限定になるので、多用途に使いたい場合、まずは4寸より少し大きいくらいの直径13~14cmのものを買っておくと使い勝手がよいと思います」
どんな用途に使うことが多そうか。イメージしながら選んでみましょう。

形
一般的にお椀は、布袋さんのお腹を横に見た形といわれる「布袋型」と、羽を反らしたような「羽反(はぞり)型」の二つが主とされます。布袋形のお椀は中腹にふくらみが出るので、汁を飲み干すときに角度をつけて持つことになり、他方、羽反型はフチが反っているので角度をつけずとも飲みきりやすいと、形によって所作が異なります。
 左が布袋型・右が羽反型(写真提供:漆琳堂)
左が布袋型・右が羽反型(写真提供:漆琳堂)
内田さん:
「羽反型だと顎を上げすぎず飲めるため、所作が美しくなると思います。また別の視点として、羽反型の場合すぐに汁が口もとへ流れてきますが、布袋形だとほどよくすすれます。だから、猫舌の人は布袋形がおすすめ、のような言い方もできますね。そんな違いを意識しながら選んでいただくといいのではないでしょうか」

加えて、もう一つ気になるのは高台の高さ。高い方が格式高いと思われる方も多いのですが、高低に用途の別はなく、好みで選んで問題ありません。
内田さん:
「もともと日本では囲炉裏の枠にうつわを置いて食事をしたり、外での田んぼ仕事の途中に草むらに置いてごはんを食べたりしていたので、持ちやすいことが高台が高くなった由来だとされています。『ハレの日の席では高くなくてはいけない』のようなことは全くなく、デザインのお好みで選んでいただいて大丈夫です」
色
続いては、色。漆器と聞いて思い出す色といえば、黒と赤。最近は色漆のものもよく見ます。
内田さん曰く、歴史を紐解くと黒は庶民の色、赤は高貴な色とされていたのだそう。そのためかつては、赤色の漆器は目上の人や男性用という使い分けもあったといいます。
内田さん:
「もちろん今は色による差別はなくなっていますが、赤が高貴な色だったことから、ハレの日のうつわだと僕は赤色をおすすめしています。一方で、法事のときは赤色は使わないなど、シーンに合わせて色を変えることはあると思います」

内田さん:
「あと、色の使い分けでもう一つ言うと、黒いうつわに白米を入れるとめっちゃはえるんですよ。つまり、美味しそうに見える。『黒いうつわでごはんを食べると肥える』って、昔から言われているくらいです。
一方でお味噌汁を飲み終わった後の味噌かすは、黒いお椀よりも赤いお椀の方が目立ちにくいので、汁物用には赤いお椀が広まったと聞いています。なので、ごはんをよそうなら黒、汁物なら赤、のような考え方でもいいですね」
ちなみに、漆琳堂さんが手がける漆器には、青やピンクのような色漆の商品も。生漆(きうるし)は精製すると有色透明になり、そこに顔料を加えて色を作るそうです。さまざまな色をした現代的な印象の漆器は、これまで漆器に盛られてこなかった洋食や中華にも使い勝手抜群です。
 漆琳堂さんが手がける人気の「RIN&CO.」シリーズ。色展開豊富な他、高台をなくして洋食にも対応できるような形状に
漆琳堂さんが手がける人気の「RIN&CO.」シリーズ。色展開豊富な他、高台をなくして洋食にも対応できるような形状に
なお、ツヤの有無については特に気にせず好みで問題ありません。
内田さん:
「ただ、例えば値段の張るお料理屋さんなどは間接照明がメインで少し暗いことも多いので、うつわにツヤがないと貧相に見えるんですね。なので僕たちは、ツヤのあるものをおすすめしています。反対に今の一般家庭では明るい照明がついているため、ツヤを消したマットな色のものをご提案する場合が多いですね」
重さ
お椀はだいたい100g前後。特に選び方の決まりはないので、持ちやすい重さの物を選ぶようにします。なお同じシリーズでも木の育つ環境や、手塗りの場合は漆の厚さで微妙に質量が違うこともあり得ます。可能であれば、持ってみてしっくりくるものを迎えるとよいでしょう。
価格
漆器と聞くと高価なものに思えますが、現代では100円ショップや雑貨店での販売も見かけるようになりました。一方で、百貨店などでは一つ3万円ほどするような高価なものも。中川政七商店でも3000円台から、2万円弱の価格帯まで幅広く扱っています。
漆器の価格には主に、素材と塗料の組み合わせが関係します。例えば安い品は、塗料を塗る前のうつわが木ではなく、ABS樹脂のような素材で作られるため価格を抑えられるのです。また樹脂のなかでも、ピュアなものを使うこともあれば、別の用途で使われた後にリサイクルされた樹脂が使われる場合も。
さらに木地に木は使っているものの、木そのものを削るのではなく粉にして固める技法も、漆器の価格を抑えられる作り方の一つです。
内田さん:
「1000円から5000円くらいの品だと、木の粉を固めて作ったうつわに漆を塗ったものが多いと思います。現代と伝統技術のハイブリッドみたいなやつですね。
逆もあって、木地は木を削ったものだけど塗装はウレタンという場合もあります。このあたりの識別は、商品の品質表示を見ていただくのが一番です。
伝統的な木を削って作る技法のものだと、1万円以下は少ないと思いますね。
木を削って作るお椀って、そのお椀の大きさになるまで木の成長を待つしか作る術がないんですよ。『一寸倍』って言葉があって、一寸大きくなれば木地の値段は倍するといわれているほどです。なので、伝統技法で作られた大きなお椀だと3万円くらいのものもあります」

なお、一概にどれが悪い・いいという話ではありません。漆琳堂さんでも、お客さんの状況や価格別にさまざまな作り方を提案したり、挑戦したりしているそう。
内田さん:
「例えば業務用漆器であれば注文数が多く、納期が短い場合が多いため、ベストなサイズの木を探してそれを削って‥‥ってしていると時間が足りないんですね。だから木を削るのではなく、木の粉を固める技術を使ってうつわを作ることもありますよ」

<漆器を扱いこなす心得:選び方>
・サイズ:汁物専用なら直径11~12cm、多用途の場合は13~14cm、麺類に使う場合は15cmがおすすめ
・形:布袋型と羽反型が主。望む所作や、飲みやすさで自分にあったものを検討する
・色:日常では気にせず好きな色を使って問題なし。ハレの日は赤色がおすすめ
・重さ:使いやすいものを好みで選ぶ
・価格:素材と塗料の組み合わせで変わる。品質表示を確認し、自分が望むものを迎える
【漆器を扱いこなす】其の弐:扱い方
選び方を心得たら、続いて扱い方を習います。何となく扱いにくいイメージの漆器ですが、どんなポイントに注意すれば長く使って行けるのでしょう。
使用頻度
意外にも、「漆器の状態を保つには、よく使うのが一番」と内田さん。
使わないまま長期で保存するよりも、毎日使った方が健やかな状態に保てるのだといいます。高頻度で使った場合、傷みが早くなると気にされるかもしれませんが、修復サービスを使えばきれいになるので気にせずたくさん使ってあげましょう。
洗い方
中性洗剤を使い、スポンジの柔らかい部分で洗います。堅い部分は塗膜を傷つけてしまうので注意しましょう。水で洗っても問題ありませんが、うつわに付いた汚れを無理にこすると塗膜が削れるため、お湯で浮かせながら洗うのがおすすめです。汚れがひどい場合は、10〜20分ほどお湯につけてから洗うと汚れが落ちやすくなります。
ただし、長い間水につけておくと塗膜が変色する原因となるため、洗い桶に入れっぱなしにしたり、お味噌汁を入れたまま冷蔵庫で半日以上置く、などは避けてください。保存容器としては使わないようにしましょう。
また意外と見落としやすいのが高台裏の汚れ。洗う際には裏までしっかり洗うようにしてください。
なお食洗機に対応している、していないは、塗料の種類により異なります。商品パッケージや取扱説明書などを確認し、個別に判断してください。
 スポンジの柔らかい部分で、やさしくキュッキュッと洗います
スポンジの柔らかい部分で、やさしくキュッキュッと洗います
しまい方
しっかり乾かせるよう、食器かごに斜めに置いて水分をきります。漆器にカルキ分が残ると白い跡になり目立つので、気になる方は柔らかいふきんで拭いてから乾かすようにしましょう。布で拭くことで、もともとは不揃いな漆の粒子が均一になりツヤも増します。
長期で保存する場合は乾燥に注意。うつわ同士がくっつくのを避けるため、重ねる場合は薄い布やキッチンペーパーなどを挟み、乾燥しにくい場所に置きます。
とはいえ上述の通り、うつわにとって一番いいのは頻度高く使い続けること。2年も3年も使わないのはうつわの状態を悪くしかねないため、大切に取っておくのではなく、よく使ってあげてください。


修理
凹んだり塗膜がはがれてもご安心を。漆琳堂さんをはじめ、修復サービスをしている漆器屋さんに相談すれば、ひどい状態のものでなければ対応してもらえます。
凹みや塗膜の傷には漆を塗り直し、ヒビの場合は漆で詰め物をしてから塗装して、新品同様の表情でまた手元に戻ってきます。
内田さん:
「うちだと修理期間は4~6か月ほど。状態によって異なりますが、修理金額は購入金額の半額ほどで対応させていただいてます。長く使うために、ぜひご活用ください」
<漆器を扱いこなす心得:扱い方>
・使用頻度:頻度高く使う方が、漆器にとってはよい
・洗い方:中性洗剤を使い、スポンジの柔らかい部分で洗う
・しまい方(短期):水気をきってしっかり乾かす
・しまい方(長期):重ねる場合は薄紙などでしきり、乾燥しない場所で保存
・修理:ヒビや塗膜の剥げは修理可能。それぞれの状態にもよるので、詳しくは修理対応をする漆器屋へお問合せを

【漆器を扱いこなす】其の参:料理との合わせ方
最後に教えてもらったのは、食卓での“意外な”使い方。漆器といえばお椀のイメージが強く、お味噌汁やお吸いものは合わせる料理の定番ですが、それ以外にどんな料理に合わせられるのでしょう?
内田さん:
「汁物だけでなく、僕は白ご飯も漆器で食べます。あとは形にもよるんですけど、グラノーラを入れることもあるし、平皿っぽいものにはパスタやカレーを盛り付けたりもします。漆器は天然由来の素材かつ軽くて割れにくいので、お子さんが使うのにもおすすめです」
というわけで、まずは定番の汁物を盛り付けてみました。いつもの汁物も漆器によそうだけで、キリッとした表情になるような気がします。
 汁物を入れたうつわは「食洗機で洗える漆のスープボウル 大 濃茶」、料理には「里いものとん汁」を使用
汁物を入れたうつわは「食洗機で洗える漆のスープボウル 大 濃茶」、料理には「里いものとん汁」を使用
続いて別のうつわにグラノーラを入れてみました。口径が広く、少し深さのあるうつわを選べば何かと使えそうです。
 「RIN&CO.越前硬漆 平椀 INDIGO03」を使用
「RIN&CO.越前硬漆 平椀 INDIGO03」を使用
内田さんの例にならい、カレーも合わせてみました。漆器でカレーを食べるのは初めてですが、陶磁器のうつわとはまた違った佇まいのよさが。
 うつわは「RIN&CO. 越前硬漆 深ボウル L NORTH GRAY 01 」を使用。「産地のカレー 近江の黒鶏黒カレー」を盛り付けました
うつわは「RIN&CO. 越前硬漆 深ボウル L NORTH GRAY 01 」を使用。「産地のカレー 近江の黒鶏黒カレー」を盛り付けました
内田さん:
「あとはお蕎麦に使える大きさのものがあれば、ラーメンを入れるのもいいですよ。漆器は熱伝導率が低く、温かいものを盛り付けても手に持ちやすいし、料理も冷めにくいのがいいところ。ぜひ和食だけでなく、いろいろな料理に活用いただければと思います」
提案いただいた通りに、ラーメンを盛り付け。大椀があれば、麺類から丼ものまで幅広く使えそうです。熱い料理も冷めにくく、料理の美味しさをそこないません。いつものインスタント麺もちょっとリッチな印象になり、気分が上がります。
 うつわは「食洗機で洗える漆椀 大椀 朱」、料理には「産地のラーメン きのこと食べたい鯛だしラーメン しょうゆ味」を使用
うつわは「食洗機で洗える漆椀 大椀 朱」、料理には「産地のラーメン きのこと食べたい鯛だしラーメン しょうゆ味」を使用
なお、料理に使う際は電子レンジでの使用は避けましょう。油や酸は、料理に使われる程度の量であれば心配無用。酢の物や揚げ物にも、気にせず使って問題ありません。
ただし、高温に熱した油を入れるのは傷む原因となりますので避けてください。
また汁物や、漆器を洗う際の湯の温度は、人の手がやけどしない程度であれば気にせず使って問題ありません。
<漆器を扱いこなす心得:料理との合わせ方>
・料理の種類:和食にとらわれず、洋食や中華などいろいろな料理と合わせられる。お気に入りの使い方を見つけると楽しい
・使用を避けるケース:電子レンジ調理、やけどする熱さの湯や高温に熱した油を入れるのは避ける
重厚な佇まいやお手入れが難しいイメージなどから、普段使いのうつわとしては、どうも自分にはハードルが高いと感じてしまっていた漆器。選び方や扱い方、また種類の幅や料理との相性などを教えていただくことでそんな気負いも消え、食卓への登場頻度が増えそうです。
万が一の際も修理をすれば、一生付き合っていける食卓道具に。私だけの漆器として育てていきたいと、改めて大切にしたい気持ちになりました。内田さん、どうもありがとうございました。

 越前の街を見わたせる公園にもご案内いただきました。天気もよく、気持ちいいお散歩でした
越前の街を見わたせる公園にもご案内いただきました。天気もよく、気持ちいいお散歩でした
<関連商品>
中川政七商店では漆琳堂さんと一緒に、普段から気軽に使える漆椀をつくっています。
・食洗機で洗える漆椀
・食洗機で洗える漆のスープボウル
・越前漆器の豆皿
・ワイズベッカー越前漆器 酒器
<関連特集>
その他、漆琳堂さんが手がけるオリジナルブランドの商品も多数販売中です。
・RIN&CO. -北の地のものづくり-
・お椀やうちだ
文:谷尻純子
写真:奥山晴日